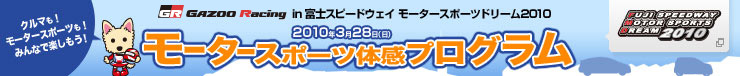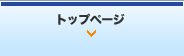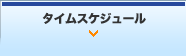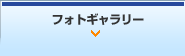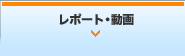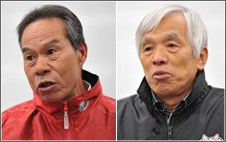コアなファンだけでなく、幅広い層の人々にモータースポーツに触れてもらい、その楽しさを知ってもらおうという趣旨のもとに、2年前から始まったファン参加型のサーキットイベントである「FUJI SPEEDWAY MOTORSPORTS DREAM」。3回目、そして富士スピードウェイのリニューアル5周年記念となる今回は、クルマの「楽しさ」と「夢」を広げる活動の一環として、トヨタが推進するGAZOO Racingプロジェクトによる「モータースポーツ体感プログラム」も実施。いっそうパワーアップしての開催となった。
プログラムは盛りだくさんである。レーシングコースでは、プロのレーシングドライバーが運転するFSWオフィシャルカーとGAZOO Racingのマシンに同乗するサーキットタクシー、クラブやチームのオフ会にサーキット走行をプラスしたオフ会体験走行、フォーミュラ・ニッポンのデモ走行、ドリフトマシンによるD1 GP同乗体験走行、2座フォーミュラ同乗体験走行、スーパータイヤ転がしGPなどがラインナップされていた。
加えてGAZOO Racingの企画による「ハイブリッドチャレンジ」。全国から集まった60台のハイブリッド車がレーシングコースを舞台に燃費を競う、日本初となる本格的なハイブリッド車のエコラン競争で、今回の最大の話題となった。
このほかGAZOO Racingでは、ショートコースにて「ドライビングレッスン」、モビリタ(トヨタ交通安全センター)にてiQ GRMNオーナーのための「ドライビングレッスン」、またジムカーナコースにて、「スムーズスラロームチャレンジ」といった、参加者が楽しみながら走りを「学ぶ」、あるいはモータースポーツに「挑む」プログラムを実施していた。
いっぽうイベント広場では、500台近い“痛車”が集まったその名も「痛車サミット」を開催。パドックやイベントステージではドライバーのトークショーおよびサイン会、キッズカート教室、さらに弾き語りやお笑いのライブ、そして子供向けの戦隊ショーまで、バラエティに富んだプログラムが用意されていた。
この日の富士スピードウェイは、午後からは小雪交じりの雨が降るあいにくの空模様だった。しかし見ているだけでは凍えてしまいそうでも、参加して楽しめるとなると話は別。約5000人の来場者は、エンディングまで存分にモータースポーツを体感していた。
GAZOO Racingによる「モータースポーツ体感プログラム」、そして今回の「富士スピードウェイモータースポーツドリーム2010」の目玉として、注目を集めたプログラムが「ハイブリッドチャレンジ」である。
サーキットを舞台にした本邦初の、ハイブリッド車による本格的なエコラン競争だが、ベースとなったのはGAZOO Racingが2008年から全国各地で開催してきた「プリウスカップ」。これはプリウスを使った地域ごとのトヨタ販売店の対抗戦だったが、「ハイブリッドチャレンジ」では広く一般から参加を募った。
オープンイベントということでプリウス以外のハイブリッド車にも門戸を開放し、全国から集まったエントリー車両は計60台。内訳は44台の現行プリウスを筆頭に、先代プリウスが11台、トヨタSAIが2台、そして現行および先代ホンダ・インサイトが1台ずつ。さらに、先代プリウスのプラグインコンバージョンが1台だった。
「それらの参加車両にドライバーとナビゲーター(小学生以上)の2名でチームを組んで乗り込み、全長約4.5kmのレーシングコースをあらかじめ設定された基準タイムにしたがって2周走行。その間の燃費を競う」というのが、競技の内容である。基準タイムは9分から9分20秒で、これより早くても遅くてもペナルティが課せられ、実燃費から減算されるという仕組みだ。
レース前、パドックに整列した60台のハイブリッド車の眺めは、なかなか壮観なもの。一般参加のチームに交じってトムス会長の舘信秀氏やレーシングドライバーの木下隆之氏らの顔も見え、また自動車専門メディアのチームもいくつか参戦していた。
出走車両は見たところほとんどがノーマルだったが、なかには自作のエアロパーツを装着し、随所に軽量化を施すなどの独自の“エコチューン”を実践した車両も見られた。
そうした本気モードのチームがいるかと思えば、ハンディキャップになるのを承知で後席に家族や友人を乗せてドライブ気分のチームもいる。2シーターの初代インサイトを除き、ナビゲーターのほかに2名まで同乗OKという、いい意味でユルいレギュレーションが生んだ光景である。このようにさまざまな志向を持った人々が同じ土俵で戦えるのは、燃費レースならではといえるだろう。
しかし、本気モードであれドライブ気分であれ、大半のチームはサーキットを走ること自体が初めて。いっぽうプロを含めたサーキット経験者にとっても、ハイブリッド車によるエコランは未知の体験。そもそもこのプログラム自体が初の開催であり、ある意味イコールコンディションに近い状況のなか、60チームが20チームずつ3組に分かれて競技開始となった。普通のレースとは異なりエグゾーストノートがとどろくことも、タイヤのゴムやオイルの焼けた匂いが漂うこともなく、文字どおり静かな戦いが繰り広げられた。
結果はというと、1位は先代プリウスで、記録はリッターあたり43.6kmだった。これは基準タイムを超過したペナルティとしてマイナス5kmを課された数字で、実燃費はなんと48.6km/リッター! 続く2位は現行プリウス、3位は先代プリウスだったが、彼らも優勝チームと同様に基準タイムを超えていた。
聞けばこれらトップ3はプリウスオーナーのSNSに参加する仲間同士で、普段から燃費に関する情報を交換したり、ときには何台か集まってエコラン競争をしているのだという。つまり彼らは、ペナルティを課されても遅く走ったほうがいい結果につながることを経験上知っていたので、そういう戦略で臨んだのだ。作戦勝ちというわけである。
興味深いのは、ゆっくり走ったからといって必ずしも燃費がよくなるわけではなかったこと。40位以下にタイム超過のペナルティを受けたチームが少なくなかったことが、それを証明している。いっぽうではモータースポーツのプロがドライブしたチームも、本気だったかどうかはさておき上位入賞は果たせなかった。
こうした事実からも、今まさに始まったばかりで勝利の方程式が確立されていないハイブリッド車のエコラン競争は、知的かつチャレンジングな、新しいモータースポーツであると言える。しかもハイブリッド車のオーナーでさえあれば、誰もが気軽に参加して楽しむことができ、環境への負担も最小限で済むのだ。
GAZOO Racingは、これからも参加型のモータースポーツ活動を広げていきたいと考えている。そのうちのひとつとして生まれた「ハイブリッドチャレンジ」には、今後の発展が大いに期待できそうである。
日本人初のルマン24時間のウィナーで、現在はSUPER GTに参戦するチーム・トムスの監督、そしてフォーミュラ・トヨタ・レーシングスクールの校長を務める関谷正徳氏の監修のもとに作られたショートサーキット。全長は1km未満だが、コース幅は10~12mあり、ストレートの最高速度は優に100km/hを超える。また高低差もあるため、テクニカルかつチャレンジングなコースである。
ここを舞台に、運転技術の向上とクルマを操る楽しさを体感することを目的としたドライビングレッスンが行われた。
事前応募から抽選により参加した受講者は30名で、1回につき6名、計5回のレッスンが実施された。1回の受講時間は90分で、最初と最後にブリーフィングルームで行われる座学を除いては、インストラクターがマン・ツー・マンで受講者を個別指導する。レッスンの使用車は「レクサスIS」である。
スムーズで安全な車両コントロールのための、「走る」「曲がる」「止まる」の基本操作から学ぶ今回のレッスン。見たところサーキット走行に慣れていない受講者が少なからずいたようだった。しかも午後からは雨がパラつきはじめ、コースはプロでも神経を使うセミウェット状態に。最初のうちは恐る恐る走っているだろうドライバーの存在が、はた目にもわかった。しかし、インストラクターの指導を受けて、徐々にペースアップしていくのが、これまたはっきりと目で確かめられた。
レッスン終了後、そうした受講者のひとりに声をかけたところ、やはりこの種のイベントへの参加は初めてとのこと。レッスンの感想を尋ねると、こんなコメントが返ってきた。
「最初は加減がわからずにおっかなびっくりだったんですが、アドバイスに従っているうちになんとか自分なりに走れるようになりました。インストラクターの指摘は非常に的確で、わかりやすかったですね」
「IS」の車内では、こちらが予想したとおりの状況が展開されていたのである。
いっぽうインストラクターにも尋ねてみた。
「初心者は素直にアドバイスに耳を傾けるので、驚くほど上達が早い場合もあるんです。今日、ひとりいらした女性の方が、まさにそうでした。はじめのうちは“走るシケイン”状態だったのに、終わるころには前を走るクルマを突いてしまいそうなほどでしたから。まるでスポンジのような、すばらしい吸収力ですよ」
先に話を伺った受講者が、帰り際に「今日はとても充実した時間を過ごせました。この場で体感したことを忘れずに身に付けられるよう、ぜひまた参加したいですね」と言い残していった。同じような思いを抱いた受講者は、少なくなかったことだろう。
富士スピードウェイ内にあるトヨタ交通安全センター「モビリタ」。35度バンクや低ミュー路なども備えた広大な安全トレーニング用コースで実施されたのが、「iQ GRMNドライビングレッスン」である。
「iQ GRMN(GAZOO Racing tuned by MN)」とは、「トヨタiQ130G」をベースに6段MT、専用サスペンション、専用アルミホイールやリアディスクブレーキなどを備えるメーカー製チューンドカー。昨年11月に100台限定で市販開始され、瞬く間に完売となったのは、GAZOOファンの記憶に新しいところだろう。
「iQ GRMN」ドライビングレッスンは、自身の「iQ GRMN」で参加可能なオーナーのみを対象とする、20名(台)限定のプログラム。その趣旨は、コンパクトなボディに秘められた「iQ GRMN」の高度なポテンシャルと走りの特性を理解し、より楽しく安全に走るためのノウハウをプロが伝授するというものだ。インストラクターは、1970年代に“スターレット使い”としてその名をツーリングカーレースの世界にとどろかせた後、幅広いカテゴリーで活躍した鈴木恵一氏。ゲストとしてレーシングドライバーの木下隆之氏、「iQ GRMN」の生みの親であるトヨタのマスターテストドライバー成瀬弘氏も参加した。
当日は午前と午後にわかれて、10名ずつのオーナーが受講。レッスン時間はそれぞれ3時間とられていた。受講者はまずオリエンテーションを受け、正しいドライビングポジションなどを確認した後に、いよいよコースイン。ペースカーに続いて隊列を組んでウォームアップしたのち、インストラクターの指示に従ってコーナリング、ブレーキング、スラローム、ヒール&トウなどのレッスンを受けた。
午後の組のなかに女性がひとり、それも日本在住のイギリス人女性が参加していた。レッスンをひと区切り終え、ほおを紅潮させて「iQ GRMN」から降りてきた彼女は、開口一番「GreatFun!」(めっちゃ楽しい!)。聞けば彼女に付添ってきていた、「iQ GRMN」を共同所有するボーイフレンドの勧めで参加したそうだが、ドライビングレッスンを受けるのは初めてとのこと。流ちょうに日本語を操るアメリカ人の彼氏のほうは、「もちろん僕もすごく参加したかったけれど、1台につき1人というので、泣く泣くあきらめた」のだそうだ。
ちなみに彼は、身長2mという偉丈夫(いじょうぶ)。だが「ドライビングポジションはまったく問題ない。iQは僕のために造られたんじゃないかと思うくらい」という。しかも「運転の楽しさは、以前に乗っていたBMWM5やインプレッサSTIと比べても勝るとも劣らない」と大絶賛していた。
それにしても、受講者は1回につきたった10名で、レッスンはたっぷり3時間。しかも講師陣は一流。100台限定のスペシャルな「iQ GRMN」にふさわしい、スペシャルなドライビングレッスンだった。
この日GAZOO Racingが企画提供したプログラムのなかで、もっとも気軽に(当日先着順受付)、もっとも多くの来場者が参加でき、それでいてモータースポーツの魅力を体感できると好評を博したのが、ジムカーナコースで行われた「スムーズスラロームチャレンジ」だ。
パイロンで作られた全長約600mのコースを、用意された「トヨタ・カローラアクシオ」で走り抜けタイムを競うものだが、単純にタイムが速ければ勝ちというわけではない。加速・減速およびコーナリングの際に発生する縦方向、横方向のG(重力)をアクシオの車内に設置されたセンサーが計測し、大きなGがかかると警告音を発生、鳴らした回数分がペナルティとして走行タイムに加算されるのだ。プログラムのタイトルに冠されているとおり、スムーズかつ速く走らせなければいけないのである。
話を聞いただけでは、そう難しいとは思えないかもしれない。だが、走り終えてクルマから降りてきた参加者たちは、判で押したように「想像していたよりずっと難しかった」と語った。
タイム計測は参加者1名につき2回行われるので、1回目はいわば様子見。たとえ警告音を鳴らしてしまっても、2回目は注意すればいいように思える。
「ところが、1度鳴らすとビビってしまうんです。どこが限界なのか加減がわからないので、あたふたしているうちに終わってしまいました」とは、ある参加者の弁。
見た目に派手さはないものの、クルマの物理特性を理解し、それに逆らわず運転できる腕がなければいいタイムは望めない、じつに奥深いゲームなのだった。
ちなみにこの日のトップタイムは1分05秒08で、もちろんノーペナルティ。参加者にルールや走り方を説明していたプロのレーシングドライバーいわく、「我々が走っても04秒台が出せればいいほうですから、優勝者はかなりレベルが高いです」とのことだった。
当日、富士スピードウェイには元祖・日本一速い男こと星野一義氏やルマンのウィニングドライバーである関谷正徳氏をはじめ、そうそうたる面々が来場していた。彼らがチャレンジしたら、はたしてどんなタイムを叩き出したのか? そう考えたのは、おそらく私だけではないはずだ。
この日のオープニングを告げたプログラムが、レーシングコースにおけるサーキットタクシー。抽選によりプロドライバーの駆るGAZOO Racingのマシンに同乗走行できるという、ファンの夢を実現したプログラムである。
GAZOO Racingが用意したマシンは全部で5台。すでにおなじみの、ニュルブルクリンクで鍛えた「レクサスIS250」と「アルテッツァRS200」のレーシングバージョン、そして「ヴィッツ・ターボMN」に加えて、今年の東京オートサロンでデビューしたばかりの「iQ GRMN+スーパーチャージャー・コンセプト」と「GRMNFRホットハッチ・コンセプト」というラインナップである。
いずれも貴重なマシンだが、なかでもとりわけレアなのが「GRMNFRホットハッチ・コンセプト」だ。欧州専用のFFモデルである「トヨタ・アイゴ」をFRに仕立て直した、市販化の可能性は限りなく低いと思われるスペシャルなモデルである。
抽選で同乗する権利を獲得した来場者といえども、実際に乗る「タクシー」を選ぶことはできない。高い競争率を勝ち抜いただけでもラッキーなのに、さらにこうしたレアなモデルに同乗できた来場者は、強運の持ち主に違いない。
これらのマシンをドライブしたのは、フォーミュラ・ニッポンやSUPERGTに参戦する井口卓人選手や国本雄資選手らゲストを含むトヨタのドライバー。
同乗走行であるから、十二分に安全マージンをとってのドライビングであることは言うまでもない。とはいえ、そこはプロのレーシングドライバー。コーナーではイン側のタイヤを縁石に乗せてみせたり、ときにはテールを大きくスライドさせてみたりとエンターテイナーぶりを発揮して、同乗者を喜ばせていた。
できるだけ多くの来場者に体感してもらえるよう、同乗体験はひとり1周に限られていた。それでも走行を終えて降りてきた来場者は、間近で見るプロのテクニックと五感で味わう非日常的な刺激に、一様に興奮を隠せない状態だった。
このサーキットタクシーは午後も2回にわたって行われた。