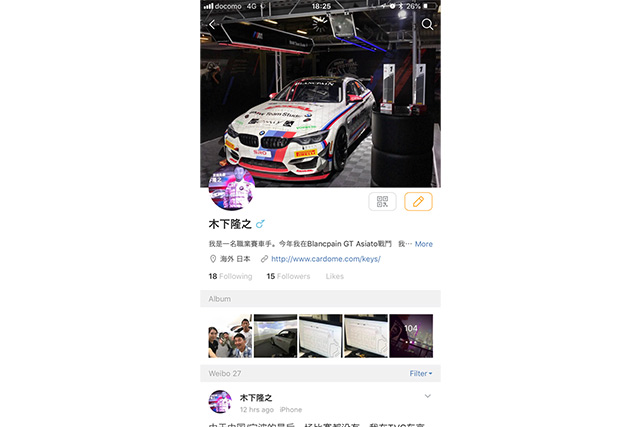229LAP2018.10.10
中国語でレースするの件
世界各国でレースを続けてきた木下隆之にとっても、中国でのレース参戦は初めてだったという。とはいえ、どこかでDNAが共通する隣国だから、コミュニケーションは容易いと想像していた。ところが、実際にはそう簡単ではなかったようなのだが、豊富な海外経験を持つ木下隆之はどうやって中国戦を攻略したのだろうか。
世界巡業レーサーの公用語は
思えば随分と海外のレースに参加したものである。1990年代の日産契約時代に、スカイラインGT-Rとともに挑んだスパ・フランコルシャン24時間(ベルギー)が、海外レース参戦の皮切りだったように思う。ドイツのニュルブルクリンク詣も、もう28年になろうとしている。
その間に、イギリスでツーリングカーレースに参戦した。オランダやハンガリーでGT耐久に参戦したのもいい経験だ。スズキのアルトワークスで、スイスのシャモニー24時間参戦などという希少な体験もしている。スーパーGTを戦ったマレーシア・セパンにももちろん参戦している。
しかも、である。今年はBMW Team StudieとともにブランパンGTアジアに全戦参戦することで、アジア詣が続いている。開幕戦のマレーシアやタイのブリーラムは勝手知ったるサーキットだからそれほどの混乱はないが、中国・上海にステージを移すと様子が変わる。最終戦の舞台となる中国寧波(NINBO)なんて聞いたことも見たこともない。純度100%の不安に押しつぶされそうである。
それでも、英語が通じる国であれば心は休まる。なんといっても英語は世界共通語だから、異国の地では頼りになる。とくに、英語や米語圏ではない国の人との会話は優しいから安心だ。お互いに100%ネイティブではないので、伝えたい事柄を簡潔に整理して、きわめてシンブルな単語で話そうとするからだろう。正統派英国人のクイーンズイングリッシュも、まだ救われる。最悪なのは、ヤンキー訛りのアメリカンイングリッシュだ。おおいに聞き取りづらいのである。
アメリカ英語をカタカナで伝えるのもどうかと思うが、数字の「21」は英語なら「トゥエンティーワン」となるところ、アメリカ英語になると「チュアニーヤン」に聞こえる。こいつが厄介だ。小鼻に力を入れて、鼻腔から息を抜くようにしつつ、舌先を巻きながらで甘えるように喋るとアメリカ英語になる。僕の乏しい経験からくることだから誤解もあるかもしれないけれど、少なくとも僕にはそう聞こえる。そう聞こえるから意味が通じないのだ。
もっとも、レース用語はたいてい英語だからなんとかなる。タイヤはタイヤだし、ブレーキはブレーキだ。欧州ではエンジンをモーターと呼ぶくらいの違いはあるにせよ、レースの運営に困るほど深刻ではない。数字の21は使わなきゃいいのだ。
-
-

-
初の中国・上海サーキットでは中国語が不可欠?
-
-
-

-
中国では僕にキャッチフレーズが与えられた。日本語に訳せば「直線台風」となるらしい。僕はそんなに荒々しいか?
-
英語よりも中国語
「トゥエンティーワン」と「チュアニーヤン」が聞き取れないのならまだいい方で、中国では、一部の国際人以外は100%会話が成立しないのだから難題である。
なんといってもこっちが中国語をまったく聞き取れない。「ニィハオ」「シェイシェイ」が僕の手持ちの中国語のすべてだ。そっちはそっちで「ノー」も「イエス」も理解しないから、会話にはまったくならないのだ。(国際経験のある人たちは流暢な英語を話すけれどね)
ただし、僕たちには漢字がある。これが大きな武器になる。適当に中国人を気取って漢字を当てはめれば、それなりに通じるから不思議である。
「僕は日本のレーシングドライバーです。中国でレースができて幸せです」
そんなメッセージを言葉にはできなくとも、漢字に当てればなんとか通じるのだから助かる。
「我是日本人的職業的競争自動車運転師成。我是歓喜中国的自動車競争試合参画」
これが面白いように通じるから気分がいい。いつしかスマホを片手に、筆談の嵐なのである。
ちなみに、Google翻訳するとこんなことになる。
「我是来自日本的木下隆之,能来中国赛车我很开心」
僕がこしらえたインチキ中国語とはちょっと違うような気もするけれど、通じちゃうのだから問題はない。萎縮してコミュニケーションをとらないよりも、手段を選ばず挑む姿勢を優先する主義である。
じつはさらに調子に乗って「Weibo」と「WeChat」を始めてしまった。「Weibo」は、いわゆるツイッターでありフェイスブックである。「WeChat」はLINEだと思っていい。電話回線とは別に、インターネット経由で通信ができるのである。報道規制と言論弾圧が厳しい社会主義の中国では、アメリカのSNSは公式的には活用できない。その代わり「Weibo」と「WeChat」が浸透しているというわけだ。
「これでファン倍増、人気爆発ですね」
無責任な関係者が耳元で囁く。耳元で囁かれるとからきし弱い僕は、ついついその気になって「Weibo」に熱心に投稿してしまうのである。
ファンの方々には呪文のように、「Weibo、Weibo」とフォローをせがむのだから恥も外聞もあったものじゃない。一人でも多くのファンを獲得しようと必死なのである。だっていまの僕、中国大好きなドライバーになってしまったのだからね。
-
-

-
漢字が心地いい。「2018年Mフェスティバル by上海F1国際サーキット」
-
-
-

-
上海国際サーキットの正門には巨大な看板がそびえる。「上汽集団国際競技場」である。
-
-
-

-
「熱く突き進め」とったところかな。
-
-
-

-
街のそこかしこがオリエンタルで中国らしい。
-
-
-

-
泊まったホテルはアメリカ資本の西洋式だったが、どこか中国の雰囲気が漂う。
-
-
-
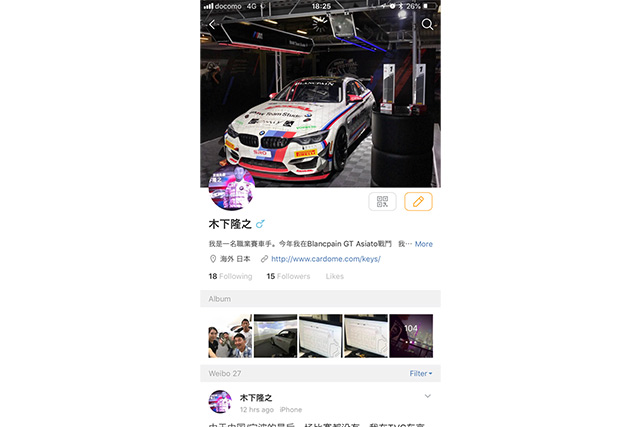
-
Weibo始めちゃいました。フォローをお願いします。こんなこと伝えるの、人生で初めて…。笑
-
筆談から会話へ
そこでやめておけば幸せな上海レースになったはずだ。筆談が通じることに気を良くした僕は、無謀な挑戦をした。悪い癖が出てしまったのである。
自己紹介に挑んだ。「僕は日本からやってきたレーシングドライバーです。中国でレースができて幸せです」をステージで叫ぶことにしたのである。
Google翻訳では「我是来自日本的木下隆之,能来中国赛车我很开心」であり、ネイティブなバイリンガル中国人のRYO君が直訳した正解文の「我是日本的赛车手,我很高兴能够在中国比赛」を、今度は筆談ではなくマイクを通じて叫ぼうと試みたのである。
邪道を承知でカタカナ発音するならば、「ウオツー、ムーシャ、ロンツゥ、ネンライ、ツォンコー、ビーサイ、ウオヘン、ガオシン」である。
さて、その時がやってきた。ネットでライブ配信されるそのステージは、1000万人の中国ファンが観ているという。こりゃ僕も、一夜にして中国のスターになれるのだと心が躍ったわけだ。
僕はMCが差し出すマイクを奪い取り、健康増進のために習った腹式呼吸で声高々に、カメラ向こうの1000万人に向かって自己紹介をした。
「ウオツー、ムーシャ、ロンツゥ、ネンライ、ツォンコー、ビーサイ、ウオヘン、ガオシン」「……」
会場は、割れんばかりの拍手に包まれた…。のではなく、あろうことか驚くほどの静寂に包まれた。スタンドに詰め掛けたファンの表情は、狐につままれたように、あるいはなにか悪いものでも見たかのようにまったく無反応だったのである。つまりは、まったく通じなかったのだ。
そしてはたと気が付いた。もともと言葉が通じないから筆談に頼ったのに、筆談が思いのほか成功したからといって、会話が成功する道理はない。
発音はネイティブなバイリンガル氏にカタカナ訳してもらったとはいえ、大事なことを忘れていた。中国語にはイントネーション、つまり四声の声調がある。発音の高低と上がり下がりが四つに分かれているのだ。
有名なところでは「母、叱る、馬、疑問」がすべてカタカナで表記するならば「マー」になってしまうことだ。中国語講座の初日に出される例題がこれだ。「マーママーマーマー?」。イントネーションを変えればすべてのマーが違う意味となるという話だ。
そんなだから、カタカナで覚えた自己紹介文を、四声などまったく無視して口にしたのでは、思いが通じるはずがない。幸いだったのは、下ネタや下品な間違いをしていなかったことだ。それに関しては、現地コーディネーターのRYO君が保証してくれてた。
「大丈夫です。みんな分かってくれていました。通じていました。何よりも、中国語で喋ってくれたこと、中国人、嬉しいと思います」。そういって慰めてくれた。
海外のレースは、思い通りにならないからこそ面白い。言葉の壁があるから刺激になるのだ。そんな珍道中レースを、10月14日に中国・寧波サーキットで迎える。ライブストリーミングの先の1000万人のために、ひとつかましてきます。
謝謝‼
キノシタの近況
ブランパンGTアジア上海戦は、両レースともポールを奪取。第一レースは2位、第二レースは優勝。ほぼ完勝だったから笑顔も弾ける。つづく最終戦に、チャンピオン争いは持ち越しとなった。10月13、14日に雌雄が決す。応援してくださいね。