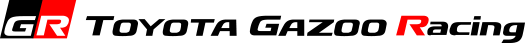320LAP2022.7.28
海外オーガナイザーならではの…
ファナテック・GTワールドチャレンジ・アジア「ジャパンカップ」が鈴鹿で開幕した。主催は海外の団体のSRO(SRO MotorSports Group)。数年前から「ブランパンGTワールドチャレンジ・アジア」として開催されており、それの名を変えた。同様に欧州でも展開。日本のオーガナイザーとは異なる、華やかなイベントが人気を呼んでいる。そのジャパンカップに参戦した木下隆之が、海外イベントの魅力を語る。
情報発信に寛容です
2018年と2019年、僕はBMW Team studieのドライバーとして「ブランパンGTワールドチャレンジ・アジア」に参戦した。GT3とGT4の混走であるそのシリーズに「BMW・M4 GT4」を駆って激走したのである。2年連続でシリーズチャンピオンを獲得している。
シリーズはインターナショナルだった。マレーシア・セパン、タイ・ブリーラム、日本・鈴鹿、日本・富士、韓国・ヨンナム、中国・上海の5カ国6カ所開催。1開催で2レースするから合計12レースで争われる。
特徴的なのは、エンターテインメント性に溢れていることだ。レースが激しく盛り上がるのは当然のことながら、そのプロモーションが先進的なのだ。SNSを駆使した情報発信には早くから取り組んでいる。最近ようやくYouTube配信を始めた団体も少なくないが、すでに4年前からYouTube動画を充実させているのだ。
レース中の映像や、サーキットが映り込む映像を使えないレースもある。チームのSNS内で、リザルトを口にすることすら禁止されることもある。主催団体の放映権料に影響するというのが理由だ。
その点でSROは寛容だ。それぞれの参加チームへの素材提供にも理解がある。個人的なSNSへの投稿を許可してくれるばかりか、オフィシャル映像を提供してくれる。世界的にまだメジャーではないという理由があるのかもしれないが、それぞれが発信することでチームの財政改善や、レースそのものの発展を期待しているのだ。目先の利益にこだわらない姿勢がいい。
写真映えするアイデアに溢れている
SNS効果を高めるために、「映(ば)える」施策に溢れている。表彰台は華やかなボードで囲われている。カメラ写りが華やかになるのだ。だがカメラを引くと、あたりは質素なこともある。日本の富士スピードウェイや鈴鹿サーキットのように、表彰台そのものが立派な設えであり、どこから撮影されても映(ば)える…とは限らない。アジア転戦だからこそのこだわりである。
今年の鈴鹿戦では、和服を纏ったシャンソン歌手の松城ゆきのさんの国歌斉唱が行われた。スタート前の静まり返ったサーキットに、透き通るような美声が響いた。大会スポンサーであるディクセルのアイデアだが、国際色豊かなイベントであることが浸透する。ブランパンGTワールドチャレンジ・アジアでは、ドライバーズミーティング中に、ご当地の民族舞踊が披露されることもあった。中国戦では、鮮やかな手さばきで仮面を変える「変面」が披露された。龍の舞が僕らをもてなすこともあった。世界転戦型としてのグレード感がある。
今回の鈴鹿戦では、レース前の晩にウェルカムパーティーが開催された。VIPルームには、大会スポンサーであるヨギボーの商品が置かれていた。巨大なクッションであり抱き枕のような商品が、そこかしこに並べられていた。
ウエルカムドリンクに酔い、ついついクッションに腰掛けてしまう。その背後には大会のパーティションが立てかけてあり、そこで個人が撮影した写メが世界に拡散されるという仕掛けだ。もちろんオフィシャルカメラマンが待機しており、決定的なシャッターチャンスは逃さない。世界のトップドライバーが商品でくつろぐ様子が、特に神経質な許可を得ることなく拡散されるのである。宣伝効果は高い。
パドックのコンテナさえも…
海外からの遠征組は、40フィートの巨大なコンテナでマシンやパーツを運んでくる。したがって、パドックにはチームの数だけの40フィートコンテナが並ぶ。さながら横浜埠頭のコンテナヤードの様相である。地元チームだけならば、華やかなトレーラーがずらりと並びパドックを彩るのだろうが、海外遠征組が多く、彼らの物資を詰め込んだ錆びたコンテナが積み重なる。
それだけでは味気ないと感じたSROは、そのコンテナをスッポリと包む袋をこしらえた。それはチームのロゴがプリントされており、つまりチームの数だけ存在する。一転、無機質なコンテナヤードが華やかなパドックに変身するのである。国際レースならではのアイデアであろう。
しかも、そのデコレートされたコンテナは、集合写真の背景として活用される。そればかりか、レースウィークが始まる前からパドックに留置される。つまり、レース関係者が揃う前の金曜日なり木曜日に、マシンを運ぶスタッフがその前でマシンと記念撮影する。ただそこにコンテナを置いておくだけなのに、簡易スタジオと化すのである。このアイデアも素晴らしい。
表彰台のシャンパンも、既製品ではなくオリジナルラベルでデコレートされている。ドライバーズミーティングでは、「シャンパンを派手に振り撒くように…」と指示される。写真映えのためである。
レースそのものも華やかさ優先だ
たとえば、緊急でレース規則が変更になったことがあった。韓国・ヨンナムの1〜2コーナーはタイトに連続している。コースオフエリアは広い。だから、ほとんどのドライバーが四輪脱輪をしてタイムを短縮させていた。硬い頭で判断するならば、ペナルティでタイム抹消である。だが、四輪脱輪したからといって、まったく危険ではなく、デメリットがないことを確認したのちに、その区間だけ四輪脱輪の対象からはずしたのである。
理由は明確で、胸のすくものだった。
「映像的にかっこいいから…」である。
ことほどさように、どこにもデメリットがなく、むしろ映像的なメリットがあるのならば、イベントのために柔軟な対応をするのが欧州流なのだ。
鈴鹿戦の終盤、クラッシュの発生に端を発してセーフティーカーオペレーションとなった。マシンは隊列を整えたまま、ペースカーを追走していた。周回数は無益に減っていく。すでに最終ラップになっていた。このままペースカーを先頭にチェッカーフラッグが振られレース終了なのか…。誰もがそう予想した。
だが僕は、最終ラップにセーフティーカー解除を予測した。というのも、SROの思想を理解していたからだ。案の定、最終ラップの最終コーナーでセーフティーカーがピットロードに飛び込んだ。レース再開である。そしてそのままチェッカーフラッグが振り下ろされた。レース終了だ。
セーフティー解除後は、ゴールラインを抜けるまで前車の追い越しが禁止される。つまり、レースを再開したからといっても順位の変動はない。抜かれもしなければ抜くことも不可能なのだ。だから、結果的にはセーフィーカー先導のままチェッカーフラッグをくぐっても結果には違いはない。
だが、セーフティーカーがピットに帰還し、レースが再開することで、少なくとも全車がスロットルを踏み込む。隊列を乱すことも可能だ。それにより、ゴールシーンが華やかになるのだ。セーフティーカーが先頭でトロトロ走行している画よりもはるかに躍動的であろう。結果が変わらないからセーフティーカー先導のままゴールさせるのではなく、結果が変わらないのだからレース再開なのである。この辺りのセンスは海外ならではである。
僕はこれまで、自動車メーカーのブランドアドバイザーとしてさまざまな施策に頭を悩ませてきた。そこで感じるのは、旧態依然の慣習から抜け出せない思考との戦いである。既得権益にしがみついていては進展はない。これまでがこうだったから…ということでは将来は暗い。
僕らは、この柔軟な発想と華やかな雰囲気を求めて「ファナテック・GTワールドチャレンジアジア・ジャパンカップ」に参戦した。次戦が楽しみである。
写真提供 田村弥
キノシタの近況
ニュルブルクリンク24時間レースから富士24時間レースへと続き、ファナテック・GTワールドチャレンジアジア鈴鹿戦と、全てBMW・M2CSレーシングでの参戦である。すっかりM2ドライバーになってしまったけれど、そろそろGT3で戦おうかな。