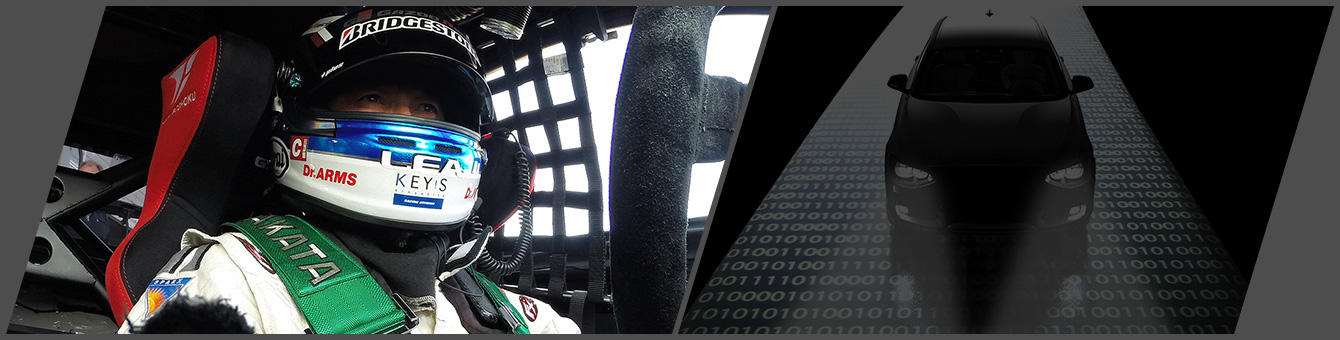「ロボレース開催」
今年の3月、「ロボレース」の開催が発表された。その情報を知った時に僕は、背筋に冷たい汗が流れるような不快感を感じた。皮膚の内側に虫が走るような、止めようもない感覚だった。危機感と言いかえてもいい。
その報道はこういったものだった。
AI搭載の無人レースカーが自立走行しながら勝敗を競うものとされていた。インディカーを近未来型にリデザインしたような、コンセプトカーの写真も添えられていた。
ロボレースは、同じ電動動力を持つ10台のレーシングカーで勝敗を競うとされている。マシンも同じだ。異なるのはAIだけ。つまり、AIの優劣を競うというわけだ。
マシンは、一般的なレーシングカーとほぼ同じサイズだ。レース前にプログラムを施し、ライバルの挙動や路面状態や、もちろんコースレイアウトなどを判断しながらバトルをする。サーキットを周回してバトルを展開するパターンと、障害物を避けながら単独でタイムを競うパターンで構成されるという。つまり、レースとジムカーナだ。
マシンの詳細は不明だが、写真を見るかぎりコクピットはない。それは当然。だってドライバーが乗ることはないのだから。前後のタイヤを覆うフェンダーが大きいのが特徴で、ウィングらしきものは見当たらない。実寸大ミニ4駆のようである。
- ロボレースについて詳しく知りたい方はこちら(AUTOSPORT web)
「もはやドライバーはなにもしなくていい?」
僕が危機感を感じたのは、ついにモータースポーツがスポーツから離れようとしているように先回りして感じたことだ。人間の頭脳より格段に処理能力の高いAIによって、ヒューマンスポーツであるモータースポーツが駆逐されるのではないかという危機感だ。
すでにAIが人間に勝った例がある。コンピューターがチェスの世界チャンピオンに勝利したのは、はるか昔の1997年のこと。さらに難しい将棋でも勝利している。もっとも困難だと考えられていた囲碁でも2015年には勝利。いまでは99%の確率でAIが人間に勝つという。ターミネーターの時代を予想した人も少なくないだろう。
「すでに感情までもコントロール可能なのだ」
AIは実は、作詞作曲も手掛ける。すでに作詞AI、作曲AIの楽曲が市販されている。悲しい曲、楽しい曲、それらには共通した言葉やリズムや、あるいは旋律があるという。「愛する」「ふたりだけの未来に…」「君が好きだ」「共に歩もう」…手垢のついた言い回しであっても、それを繰り返していれば人の感動をコントロールできるというのだ。もはや人間の感じようにもしたたかに浸透しているのである。
さらに恐怖なのは、小説すらもAIが上梓しているという。日経の「星新一賞にAIの作品が応募された。文学賞の1次選考を通過したというのだ。人間の感情の発露である文学すらも、AIが駆逐しようとしているのである。
であれば、鉄とカーボンとコンピュータの集合体であるレースが、いずれAIに席巻されるのも時間の問題なのかもしれない。
その危機感は実は十数年前に遡る。ホンダがF1を席巻している時代に、テレメトリーシステムがレースの主体になりつつあった。マシンとピットが相互通信されることにより、ピットからマシンをコントロールすることが可能になったのだ。それはさらにエスカレートした。遠く離れた極東のホンダ和光研究所のスタート担当者がコンピュータ上のスイッチを押せば、マシンはニュルブルクリンクであってもモナコであっても、もちろんシルバーストンであっても地球の裏側のインテルラゴスサーキットであっても、0.1秒の遅れもなく発進させることができたというのだ。もはや人間はコクピットに座って、ただその瞬間を待っていればいいという時代に、足を踏み込もうとしていたのだ。
「その先には自動運転レースが待っている」
僕はかつて、こう言って警鐘を鳴らしたことがある。「マシンの技術規制を進めないと。それはいずれドライバー不在の無人自動車のレースになる」と。
かつてレシングカーの技術が未成熟だった時代は、ドライバーの能力が勝敗の70%を締めるといわれていた。重たいハンドルと格闘し、ABSもトラクションコントロールもないマシンを速く走らせるには、ドライバーの繊細なテクニックが影響したからだ。だが、ABSの完成でプレーキングはただペダルを強く踏み込めばいいだけとなった。アクセルペダルさえも、コントロールする頻度は減った。つまり、ドライバーの作業量が低下した。ドライバーの勝敗への影響力は、50%になり、いまでは10%だと解く人もいる。
ABSやトラクションコントロールが進化したことで、ブレーキングの得手不得手や、アクセルワークの妙がタイム差を生まなくなった。ドライバーは、コンピュータが弾き出した理想のステアリング操作をすればいい時代である。BMWはすでに「自動運転でドリフト走行」を可能にした。
たしかに速いマシンに乗りさえすれば、いくらスキルに長けていても勝利することはできない。技術力に優れたマシンは、ドライバーのテクニックをカバーする。ワールドチャンピオンのF・アロンソですら、J・バトンすら、まだまだ熟成途上のホンダのマシンでは表彰台すら立てないのが証拠だ。
そのうちAIに僕らドライバーは駆逐されるのだろうか。彼らには恐怖心がない。高速コーナーを前に、右足が緩むこともない。もう太刀打ち不可能なのだ。
まっ、今回のロボレースは、いわばラジコンレースと同質だから、すぐにモータースポーツがAIに取って代わることはない。レースはまだまだドライバーという人間の運転能力と感情の戦いであるからだ。
だが、マシンの技術が、進化が、ドライバーの感情が表に表れないレースに向かっていることは確かなように気がする。ロボレースは現状のレースへの警鐘だと思う。

キノシタの近況

レクサスがサポートしている室屋義秀選手の妙技を見学に行った。
今後のイベントやCMの演出の参考にしようかと…。陸海空のコラボ、アイデアを温めています。
というか、飛びたくなったよ!
木下 隆之/レーシングドライバー

1983年レース活動開始。全日本ツーリングカー選手権(スカイラインGT-Rほか)、全日本F3選手権、スーパーGT(GT500スープラほか)で優勝多数。スーパー耐久では最多勝記録更新中。海外レースにも参戦経験が豊富で、スパフランコルシャン、シャモニー、1992年から参戦を開始したニュルブルクリンク24時間レースでは、日本人として最多出場、最高位(総合5位)を記録。 一方で、数々の雑誌に寄稿。連載コラムなど多数。ヒューマニズム溢れる独特の文体が好評だ。代表作に、短編小説「ジェイズな奴ら」、ビジネス書「豊田章男の人間力」。テレビや講演会出演も積極的に活動中。日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員。日本ボート・オブ・ザ・イヤー選考委員。「第一回ジュノンボーイグランプリ(ウソ)」
木下隆之オフィシャルサイト >