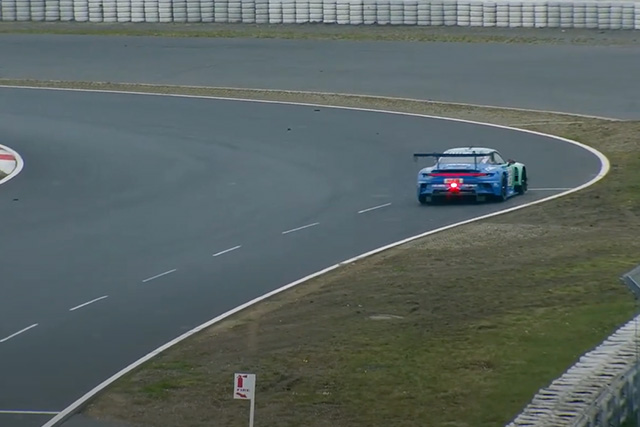339LAP2023.05.10
「ニュルブルクリンク独特のペナルティラインシステム」
レースの世界は残酷である。運不運でレースが大きく変化することは少なくない。何の落ち度もないのに、たまたま運が悪かっただけでレースが水泡に帰すこともある。ニュルブルクリンクに参戦している木下隆之が、それを回避するためのヒントをニュルブルクリンクで発見した。
セーフティカーの運不運
MC「おっと〜、激しいクラッシュが発生しました」
解説「これはセーフティが出るのではないでしょうか?」
MC「FCYが発令されましたので、全コース120km/h走行に制限されます」
レース中に激しい事故が発生すると、展開はにわかに慌ただしくなる。
ドライバー「このまま走行しますか?」
監督「いや、すぐにピットインだ‼」
無線を通じて、ピットクルーにも伝令が飛ぶ。ピットではタイヤが準備され、交代ドライバーがヘルメットをかぶる。給油マンも重装備だ。
レース中にタイヤ交換や給油、あるいはドライバー交代といったピットストップが科せられている場合には、その瞬間の采配次第で勝敗の行方が変わる。
コース上は、FCY発令によって速度が制限されている。緊急ピットインと判断し素早くピット作業を終えてしまえば、コース上を走るライバルの速度がレーシングスピードより遅いため、相対的に有利になる。タイミングを外せばその逆になる。
ただし、FCY介入中のピットストップを禁じるレースもある。FCYが宣言されるまでの間隙をついてピットインに成功すれば吉。失敗すれば厳しいペナルティの対象になる。
たとえば、スーパーGTで採用されているセーフティカー介入に関するルールは特殊だ。セーフティカーが導入された瞬間に全コース上が追い越し禁止になるのはこれまでと同様だが、一切のピットインが禁止される。セーフティカーを先頭とした隊列に並んで走行しなければならない。
セーフティカーがトップを走行するマシンをとらえ、隊列が出来上がるや否や、GT500とGT300それぞれをメインストレート上に整列させる。その後に素早く、GT500を先頭にセーフティカー走行が開始され、その隊列に後ろにGT300が追走する。つまり、クラスごとに、順位を整理するのである。
これは、ある意味で画期的なシステムだと思えた。
それまでのレースフォーマットでは、自身がどこを走行しているかによって、致命的に不利な状況に陥ることがあった。たとえばそれは、速さの異なるクラスが混走するレースの場合に、多くの場合速度で劣るクラスで発生した。
仮にGT300クラスだとしよう。テール・トゥー・ノーズでトップ争いを展開中、後方からGT500のトップ車両が二台の間に挟まったとしよう。その瞬間に甚大なクラッシュが発生、全コース追い越し禁止が発令され、同時にセーフティカーが導入されたとする。
セーフティカーはトップ車両の頭を抑えるのが基本だから、GT500の前で走行する。つまり、バトル中のGT300のトップ車両はセーフティカーの前に位置することから、遮られることなく1周先行し、隊列の最後尾につくことができる。
だが、バトル中のGT300の2位の車両はセーフティカーに頭を押さえられたGT500車両の背後であったために、その場に止まらざるを得ない。コンマ数秒のバトルをしていたにも関わらず、一瞬にしてほぼ周回遅れ寸前になってしまうのだ。
多くの場合、そのレースを放棄するに等しいハンディキャップを背負うことになる。たまたま、クラッシュのその瞬間にどこを走行していたかという運不運がレース結果を左右してしまうのである。これはあまりにも切ない。
というような不条理を解消するために、編み出されたセーフティカーオペレーションなのである。
だがそれとて、すべてを解決したわけではない。
クラッシュを確認した瞬間から、セーフティカー介入までの間隙を縫って緊急ピットインできたマシンは好都合だが、そうならなかったマシンは大きなロスを生む。ここにも運不運が生じてしまう。
運も実力のうちとはいうものの、それはあまりにも不条理だ。その結果次第では、レーシングドライバーとしての人生を左右する場面も少なくない。運が悪かったと片づけられるものではない。
ペナルティの功罪
レース中のペナルティに対する罰則規定に関しての議論もやまない。悪質なドライビング行為に対しては、最悪の場合には黒旗提示によるレース除外が言い渡される。そのドライバーは即刻ピットインして、レースを終えなければならない。
そこまでの悪質性が認められない場合は、○秒のペナルティストップ、もしくはドライブスルーペナルティが科せられる。
さらにそれよりも軽微な場合は…。
たとえばビデオ判定が必要となるようなクロスプレーの場合、レース後に○秒のペナルティタイム加算が言い渡される場合もある。
ただこれは、あくまでゴール後にタイムを加算して順位を確定するのであって、ライブ感覚に劣る。トップでチェッカーをくぐったドライバーが、実は優勝ではなかったというような場面も想定できる。エンターテインメントの点で魅力に欠けるのである。
走行ラインを規制する
今年のニュルブルクリンクで採用されているペナルティシステムは、実に画期的である。
1コーナーから2コーナーへのアプローチは、走行距離を短縮させるラインがベストとされている。多くのマシンが小さく旋回する。
だが、コース上のアウト側に白線が敷かれており、ペナルティの対象になったマシンは一度だけ、タイムロス覚悟で大外の白線内を走行しなければならないのである。
これには目から鱗が落ちた。ペナルティストップやドライブスルーペナルティのように大きく順位を下げるほどの悪質性がない場合、そしてさらにレース後にタイムペナルティを加算させるというライブ感を削ぐのでもなく、ほんの僅かだけタイムロスさせるのである。タイムにして2秒から3秒ほどのロスだ。
すでにMotoGPでは採用例がある。日本のモビリティリゾートもてぎの3コーナーから4コーナーにかけて、アウト側に特別な走行エリアが設けられた。「ロングラップペナルティ」と呼ぶ。走行距離が増えるだけではなく、コーナリング速度も抑えられるから、有効なペナルティになる。
ただ、功罪もあるようで、アウト側を走行させることはつまり、安全のためのエスケープエリアの減少を招くという意見も目についた。僕にはそれほど危険度が増したとは思えないのだが、だというのならば、ニュルブルクリンクのようにコース上にシンプルに、コースの一部にペナルティラインを設定すればいい。コスト的にも有利であろう。
これならば、たとえば1コーナーには「3秒ロスのペナルティライン」、2コーナーには「5秒ロスのペナルティライン」、3コーナーには「10秒ロスのペナルティライン」などと、反則の質によって様々なペナルティを設定することができる。画期的なアイデアだと思う。
フィールドスポーツにもさまざまな施策がある
アイスホッケーのペナルティシステムは合理的だ。その悪質度によって7種類のペナルティが課せられる。基本的には、反則を犯した選手はペナルティボックスでの、一定時間の退去が命じられるのだ。
マイナーペナルティは2分、ダブルマイナーペナルティは4分、メジャーペナルティは5分といったように、悪質度によってボックスで待機させる時間が変化する。この時間は、反則を犯したチームは数的に不利になる。フィールドでプレーできるのは6名だ。マイナーペナルティでは2分間、6対5で戦わなければならないのだ。
基本的にゲームは中断されない。そもそもアイスホッケーは体力を消耗するスポーツだから、連続でプレーできるのはせいぜい1分ほどだ。プレーは中断されず、タイミングを見てコロコロと選手が入れ替わる。
過去に何度もアイスホッケーを観戦したことがあるのだが、本当に目まぐるしく選手交代が行われている。サッカーや野球のように、選手交代のたびにプレーを中断することもない。ゲームを途切れさせないことは観客の興奮をキープさせることでもある。エンターテインメントとして完成されている。
ペナルティによって数的に有利になったチームを「パワープレー」と呼ぶ。パワープレー中は得点能力に優れた攻撃的な選手を送り込む。逆に数的に不利になったチームは、守備能力に長けたプレーヤーを投入して凌ぐ。その攻防すらも魅力のひとつなのだ。ペナルティによってゲームを興醒めさせないためのシステムが確立されているのである。
アイスホッケーのペナルティボックスに準じる制裁が、ラグビーのシンビンである。重度な反則に対して、10分間の一時退出が課せられるのだ。数的に不利な状況で戦わざるを得ず、ゲームが白熱する。不利になったチームは10分間を持ちこたえるために守備的な陣営で構える。時間稼ぎのプレーをすることもあり、スタジアムにブーイングが響くこともある。それもゲームの魅力のひとつだ。
アイスホッケーもサッカーも、プレーを中断させないための配慮が行き届いている。アイスホッケーの選手交代がプレー中に可能である点などは最たるものだが、ラグビーも同様に、プレーを続行させたままペナルティを科す「アドバンテージ」がある。
反則を受けたチームが有利に働いている場合、しばらくプレーを続行させるのだ。審判が「アドバンテージ」と宣言し、腕を横に伸ばして合図する。腕はアドバンテージで恩恵を受けるチームに向けられる。
これによってライバルは、敵のチャンスをつぶすためにわざと反則を犯しにくくなる。せっかくのいい流れを途切れさせないためのルールでもある。いちいちゲームが途切れないから、観客の興奮も持続するのだ。
さらに、副次的にアドバンテージ中にミスをしてしまったとしても、元々反則のあった場所まで戻ってプレーが再開される。しかもマイボールだ。
これによってアドバンテージを受けたチームは、ミスを恐れずに積極的なプレーに挑むことができる。より一層ゲームが白熱するというわけなのだ。
反則によってゲームがシラケることがなく、むしろ盛り上がる。
ちなみに、アドバンテージによって反則を犯したチームが十分に不利になったと判断されれば、アドバンテージは時効になりレフリーは「アドバンテージオーバー」を宣言する。ゲームは続行されるのだ。
ここでもゲームを途切れさせない施策が込められている。
改革してみてはいかがだろうか?
たとえば、富士スピードウエイの100Rの外側にペナルティラインを引いてみてはいかがだろうか?
ニュルブルクリンクのペナルティラインのようでもあり、アイスホッケーのペナルティボックスでもあり、ラグビーのシンビンでもありアドバンテージでもある。
レース中のコース上には、マシンの数だけチームがある。アイスホッケーやラグビーのように、1対1のさしの勝負ではない。そのアイデアをそのままレースに当てはめるのは性質上無理があるが、知恵を絞ればレースが運不運に左右されることなく、エンターテインメントとして昇華することができるのではないかと思う。
キノシタの近況
NLSニュルブルクリンク4時間耐久から帰国しています。今月15日からまたニュルブルクリンク24時間に向けて渡独しますが、体を休める間もありません。忙しいのは何よりですよね。