

2016年、日本とは全く異なる環境のフィンランドで、彼ら2人は4度も世界チャンピオンをとったラリー界のレジェンド、トミ・マキネン氏をはじめとする講師陣のもと、日々のトレーニングメニューをこなし、合計6回の実戦競技に参加する。
ラリーは簡単にいえば、山道や峠道などを舞台にして、タイムを競う競技。カーブの出口が見えない箇所や坂がどれだけ急激に下っているかさえも分からない道で、勇気を振り絞ってアクセルを開けていかなくてはならない。
SS(スペシャルステージ)と呼ばれるタイムを競う区間は合計すると最長250kmにも及び、次から次へと形状の異なるコーナーがやってくる。一つのミスを悔やんでいる暇などない。しかも、サーキットのレースとは違い、相手と並走する抜きつ抜かれつの戦いがない。ラリーは基本的に1台ずつ間隔を開けて走行するため、ライバルとの差を視認できないのだ。つまりは先の見えないコーナーとの戦い。姿の見えないライバルとの戦い。それは自分との戦い、姿が見えない敵との戦いとなる。
ただ、ラリードライバーには力強い仲間が居る。競技中、助手席に「コ・ドライバー」と呼ばれるパートナーが乗り、「ペースノート」と呼ばれる道の状態、カーブの形状を記したノートを読み上げ、ドライバーをナビゲートする。ラリーはサーキットと違い、同じコースを何度も周回するわけではない。例えば1月に参戦した「Arctic Lapland Rally」では、ギャラリーステージ(競技場内)を除く約223kmが全て違うコースで、事前に全てを覚えておくことは困難だ。
そのため、大会の本番前にコ・ドライバーを乗せてコースをゆっくり下見走行する時間(=レッキ)がある。ここで、コースの確認作業を行いながら、ドライバーとコ・ドライバーが相談をしながら、ペースノートを作成していく。新井のコ・ドライバーはフィル・ホール、勝田のコ・ドライバーはダニエル・バリット。2人共にイギリス人で、英語のコミュニケーションが必須なのはもちろん、異なる文化で育ったドライバーとコ・ドライバーがお互いを信頼し、息をぴったり合わせなくてはいけない。
人生の時間のほとんどを日本で過ごしてきた彼らにとって、これだ
けでも大きな試練だ。
トレーニングの後、すぐに本番がやってくる。慣れるまでプログラムは待ってはくれない。
2016年1月28日~30日に開催された「Arctic Lapland Rally」は雪の上を走るスノーラリー。
日本では絶対に使用しない釘のようなものがついた「スタッドタイヤ」(=スパイクタイヤ)を使用するラリーだ。彼らにとってスノーラリーは初体験。
勝田は残念ながらクラッシュしてリタイアしてしまったが、新井はクラス2位。総合でも3位に入る大健闘ぶりで地元のギャラリーから拍手喝采を浴びることとなった。

新井は、「海外で大会に出ることによって、自分のレベルがどこか、足りないところを実感できるというのはステップアップする上でも貴重な機会だと思います。
ラリーっていう競技はこれができるから勝てるってわけじゃないんですよね。
経験則もありますし、理論的に理解しなければいけない部分もありますから、本当に難しいです。
まだ成長できる部分は大いにあるので、そこをなるべく早く自分で理解するのが大事かなと」と好成績におごることなく冷静に今の自分を分析する。
勝田は、「サーキットの場合は同じところを走るのでレッキと呼ばれる作業がありません。
なので、ペースノートの練習を重点的に教えてもらっています。今年からWRCでやっていたコ・ドライバーのダニエルと組ませてもらっているんですが、本当に経験豊富で、ここはこうだよっていろいろ教えてもらっています。
実際に全開で走るとその通りだな
と思うことが結構あって、それを職業としているプロだなと思います。
ペースノートに関しては格段にレベルが上がったなと自分でも感じますね」と話す。
夜間の走行時にクラッシュしてリタイアに終わったが、新しくコ・ドライバーになったダニエル・バリットとのコンビネーションは良い効果を生んでいるようだ。

育ったフィールドこそ異なれど、スポーツマンらしい礼儀正しさと課題を追求し続ける気持ちの強さを随所に垣間見せる2人。
様々な課題を克服しながら日々、経験値を積み上げている。9月末の「Pirelli Ralli(ピレリラリー)」が終わる時、彼らがどんな結果を残し、どれだけ顔つきが変わっているだろうか。
7人のWRC世界チャンピオンを輩出したラリー競技の本場、フィンランドで新井と勝田は自分を信じて、腕を磨いている。世界で通用するラリードライバーになるために、自分の全てを捧げて。


19歳でラリーデビュー、全日本ラリー選手権、FIAアジア・パシフィックラリー選手権「ラリー北海道」に出場。2014年には全日本ラリー選手権JN6クラス、オーストリア国内ラリー選手権2戦にも参戦。
新井大輝選手が日本国民に広めたいラリー用語
<ペースノート> Pacenotes
助手席に座る相棒、コ・ドライバーが読み上げるコースの特徴を記したメモ。ラリー競技においては、数あるタイムアタック区間のコーナーの情報を全て覚えきれないため、ドライバーのドライビング技術と共にこのペースノートが勝敗のカギを握る。大会の前に決められた期間内でゆっくりとしたペースで試走、確認を行うことをレッキと呼び、レッキ中にペースノートを作成する。


12歳でカートデビューし、18歳でFCJチャンピオン獲得。20歳でF3シリーズ2位、2014年からはF3に参戦するとともに、全日本ラリーにも挑戦、第8戦でJN5クラス初優勝。
勝田貴元選手が日本国民に広めたいラリー用語
<コ・ドライバー> Co-driver
競技中にあらかじめ作成したペースノートを読み上げる助手席に座る人のこと。かつては「ナビゲーター」と呼ばれていたが、その役割は単なる助手以上の能力を求められる。的確な読み上げはもちろん、ドライビングの知識、ドライバーの癖を理解した上での臨機応変さも必要。選手権ではコ・ドライバーにもランキングがつく。


2016年、日本とは全く異なる環境のフィンランドで、彼ら2人は4度も世界チャンピオンをとったラリー界のレジェンド、トミ・マキネン氏をはじめとする講師陣のもと、日々のトレーニングメニューをこなし、合計6回の実戦競技に参加する。
ラリーは簡単にいえば、山道や峠道などを舞台にして、タイムを競う競技。カーブの出口が見えない箇所や坂がどれだけ急激に下っているかさえも分からない道で、勇気を振り絞ってアクセルを開けていかなくてはならない。
SS(スペシャルステージ)と呼ばれるタイムを競う区間は合計すると最長250kmにも及び、次から次へと形状の異なるコーナーがやってくる。一つのミスを悔やんでいる暇などない。しかも、サーキットのレースとは違い、相手と並走する抜きつ抜かれつの戦いがない。ラリーは基本的に1台ずつ間隔を開けて走行するため、ライバルとの差を視認できないのだ。つまりは先の見えないコーナーとの戦い。姿の見えないライバルとの戦い。それは自分との戦い、姿が見えない敵との戦いとなる。
ただ、ラリードライバーには力強い仲間が居る。競技中、助手席に「コ・ドライバー」と呼ばれるパートナーが乗り、「ペースノート」と呼ばれる道の状態、カーブの形状を記したノートを読み上げ、ドライバーをナビゲートする。ラリーはサーキットと違い、同じコースを何度も周回するわけではない。例えば1月に参戦した「Arctic Lapland Rally」では、ギャラリーステージ(競技場内)を除く約223kmが全て違うコースで、事前に全てを覚えておくことは困難だ。
そのため、大会の本番前にコ・ドライバーを乗せてコースをゆっくり下見走行する時間(=レッキ)がある。ここで、コースの確認作業を行いながら、ドライバーとコ・ドライバーが相談をしながら、ペースノートを作成していく。新井のコ・ドライバーはフィル・ホール、勝田のコ・ドライバーはダニエル・バリット。2人共にイギリス人で、英語のコミュニケーションが必須なのはもちろん、異なる文化で育ったドライバーとコ・ドライバーがお互いを信頼し、息をぴったり合わせなくてはいけない。
人生の時間のほとんどを日本で過ごしてきた彼らにとって、これだけでも大きな試練だ。
トレーニングの後、すぐに本番がやってくる。慣れるまでプログラムは待ってはくれない。
2016年1月28日~30日に開催された「Arctic Lapland Rally」は雪の上を走るスノーラリー。
日本では絶対に使用しない釘のようなものがついた「スタッドタイヤ」(=スパイクタイヤ)を使用するラリーだ。彼らにとってスノーラリーは初体験。
勝田は残念ながらクラッシュしてリタイアしてしまったが、新井はクラス2位。総合でも3位に入る大健闘ぶりで地元のギャラリーから拍手喝采を浴びることとなった。

新井は、「海外で大会に出ることによって、自分のレベルがどこか、足りないところを実感できるというのはステップアップする上でも貴重な機会だと思います。
ラリーっていう競技はこれができるから勝てるってわけじゃないんですよね。
経験則もありますし、理論的に理解しなければいけない部分もありますから、本当に難しいです。
まだ成長できる部分は大いにあるので、そこをなるべく早く自分で理解するのが大事かなと」と好成績におごることなく冷静に今の自分を分析する。

勝田は、「サーキットの場合は同じところを走るのでレッキと呼ばれる作業がありません。
なので、ペースノートの練習を重点的に教えてもらっています。今年からWRCでやっていたコ・ドライバーのダニエルと組ませてもらっているんですが、本当に経験豊富で、ここはこうだよっていろいろ教えてもらっています。
実際に全開で走るとその通りだなと思うことが結構あって、それを職業としているプロだなと思います。
ペースノートに関しては格段にレベルが上がったなと自分でも感じますね」と話す。
夜間の走行時にクラッシュしてリタイアに終わったが、新しくコ・ドライバーになったダニエル・バリットとのコンビネーションは良い効果を生んでいるようだ。
育ったフィールドこそ異なれど、スポーツマンらしい礼儀正しさと課題を追求し続ける気持ちの強さを随所に垣間見せる2人。
様々な課題を克服しながら日々、経験値を積み上げている。9月末の「Pirelli Ralli(ピレリラリー)」が終わる時、彼らがどんな結果を残し、どれだけ顔つきが変わっているだろうか。
7人のWRC世界チャンピオンを輩出したラリー競技の本場、フィンランドで新井と勝田は自分を信じて、腕を磨いている。世界で通用するラリードライバーになるために、自分の全てを捧げて。

19歳でラリーデビュー、全日本ラリー選手権、FIAアジア・パシフィックラリー選手権「ラリー北海道」に出場。2014年には全日本ラリー選手権JN6クラス、オーストリア国内ラリー選手権2戦にも参戦。
新井大輝選手が日本国民に広めたいラリー用語
<ペースノート> Pacenotes
助手席に座る相棒、コ・ドライバーが読み上げるコースの特徴を記したメモ。ラリー競技においては、数あるタイムアタック区間のコーナーの情報を全て覚えきれないため、ドライバーのドライビング技術と共にこのペースノートが勝敗のカギを握る。大会の前に決められた期間内でゆっくりとしたペースで試走、確認を行うことをレッキと呼び、レッキ中にペースノートを作成する。

12歳でカートデビューし、18歳でFCJチャンピオン獲得。20歳でF3シリーズ2位、2014年からはF3に参戦するとともに、全日本ラリーにも挑戦、第8戦でJN5クラス初優勝。
勝田貴元選手が日本国民に広めたいラリー用語
<コ・ドライバー> Co-driver
競技中にあらかじめ作成したペースノートを読み上げる助手席に座る人のこと。かつては「ナビゲーター」と呼ばれていたが、その役割は単なる助手以上の能力を求められる。的確な読み上げはもちろん、ドライビングの知識、ドライバーの癖を理解した上での臨機応変さも必要。選手権ではコ・ドライバーにもランキングがつく。

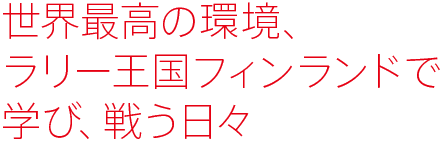






 ラリーチャレンジプログラム2016
ラリーチャレンジプログラム2016 日本車で4度世界を極めた男 トミ・マキネン
日本車で4度世界を極めた男 トミ・マキネン




