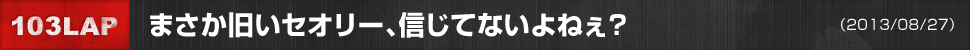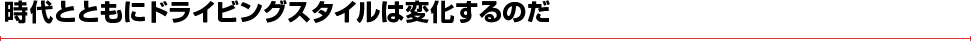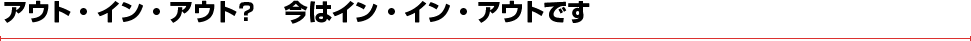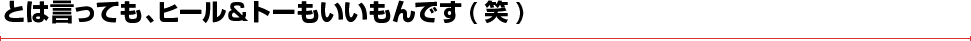タイヤが4本ある。ステアリングもある。ブレーキペダルもアクセルペダルもある。タイトなシートに括り付けられたドライバーがそれを器用に操作して走らせる。自動車レースが発祥してからそのスタイルは、未来永劫不変であるかのように変わり映えがしない。
だけど、ドライビングスタイルは日々刻々と変化している。端からは何も違いがないように見えても、コクピットの中にいると時代の変化を強く意識させられる。それは技術の進歩に違いないのだが、進化を追うようにドライビングをアジャストしているのだ。旧態依然のドライビングテクニックを信じて疑わず、凝り固まった脳でいると時代に取り残されるのだろう。
「アウト・イン・アウト」という基本テクニックがある。どんなドラテク本にも最初の1行目に紹介されているはずの、基本中の基本テクニックである。
コーナリングは、旋回Rを大きく取ると有利ですよという指南だ。コーナーにはアウトから進入し、中央で一旦イン側に寄り、そしてまたコーナー出口ではアウトにはらみましょうね…と懇切丁寧に教えているわけだ。
いわばゴルフでいえばアドレス、茶道でいえば正座の仕方、英語でいえば「This is a pen」。レースをする上で避けて通れない基本テクニックなのだ。
ただし、これにも微妙な変化がある。過去のサーキット映像と最近を比較してみると、些細な変化に気がつく。
ブレーキングを直前で終らせ、じっくりと速度が低下した頃合いを見計らっていざコーナリングを開始する。そこからコーナー仮想中心点を支点に、大きな弧を描き、その軌跡に添わせるように駆け抜ける。その走行軌跡が年々鋭角になっている。
大枠ではアウト・イン・アウトに違いはないのだが、アウトから早めに鋭くインに飛び込む…といったラインが目につくのである。弧を描くというより、入口かコーナー頂点までの2点を直線で結んだようなライン取りが主流のようなのだ。
 F1のタイヤは13インチと小径。しかも扁平率は低く肉厚である。大径かつ超低扁平タイヤこそスポーティなイメージがあるが、性能的にそれは誤解である。サイドフォールに厚みがあった方がトラクション性能に優れているのだ。
F1のタイヤは13インチと小径。しかも扁平率は低く肉厚である。大径かつ超低扁平タイヤこそスポーティなイメージがあるが、性能的にそれは誤解である。サイドフォールに厚みがあった方がトラクション性能に優れているのだ。
「スローイン・ファーストアウト」も、基本中の基本テクニックである。
コーナーを前に、十分に減速してからコーナリングを開始。コーナー脱出スピードを高めようというわけだ。
ただし、これにも変化がある。十分に減速しなければ曲がりきれないのは物理の法則がある以上道理である。だが、決して減速しすぎてはいない。いわば「ファーストイン・ファーストアウト」にも見えなくはない。
なぜか?それはとりもなおさず、タイヤの進化にある。
かつてタイヤの主流はバイアス構造のタイヤにあった。ゴムの塊の芯にあたる部分には金属のワイヤーが編み込まれている。それが進行方向に斜めにクロスしている。それがバイアス構造。一方のラジアル構造は、編み目が進行方向に正対している。
タイヤのラジアル化が30年ほど前に起った。「今度の新製品はラジアルです!」なんてタイヤメーカーがCMで自慢したほどだから、それは革命といっていいだろう。それがドライビングスタイルにとっての転機となった。
それまではブレーキング力とコーナリンググリップを同時に期待すると、タイヤは耐えられなかった。ゆえに、減速はあくまでステアリングを切り込むまでの直線で終らせ、コーナリングはすべてをそれに専念させよと。そう教えられた。
だがラジアル化によって、ブレーキングがまだ完全に終る前の段階からステアリングを切りはじめることが可能になった。軌跡と速度のリズムが変化しつつあるのはそれが理由だ。
そう、勘のいい読者ならピンときたかもしれないけれど、左足ブレーキの有効性はそれにも関連がある。左足でハードなブレーキングをしながら、アクセルペダルを踏みはじめる…といった芸当がラジアル化によって可能になった。だったらそれを使わない手はない。左足ブレーキの有効性はそれでも説明できるのである。
と言ってながら8月の週末、スーパー耐久2013「第4戦富士スーパー耐久7時間レース」にGAZOO Racing86で参戦。マシンが3ペダルだったということもあって、右足ブレーキで灼熱のサーキットを走り続け、頻繁に「ヒール&トー」なるブレーキングテクニックを駆使しながらひたすらゴールを目指したわけだ。時代の移り変わりの狭間に僕は生きているのだ。
ちなみに、「ヒール&トー」なる基本テクニックを知らない新人類がいないとも限らないので簡単に説明すると、それは一種の減速テクニック。右足でフルブレーキングしながらシフトダウンしたい場面に活用する。右足でブレーキング→左足でクラッチを踏む→ブレーキペダルを踏み込んだ右足をヒョィっとひねり、かかとでアクセルペダルを踏み込む。ブゥォンとエンジン回転を高めてシフトダウンをする…というテクニック。せっかく左足ブレーキテクニックをモノにしかけているのに右足ブレーキで戦わざるを得ない不条理を嘆きつつ、それでも爽快なレースを戦っていたのである。3ペダルも捨て難いぞ、なんて感じながら…。
-

-
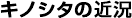
- 夏の風物詩「スーパーGT第5戦インターナショナルポッカサッポロ1000km」(鈴鹿サーキット)のテレビ解説を仰せつかった。「灼熱のレース」を「冷房完備の放送席」で観戦するのは最高。しかも、見応えのあるレースだったから、なおさら役得に感謝である。GAZOO Racingの可愛い後輩、井口と蒲生が揃って表彰台というのも嬉しい。コクピットで暑さと格闘するドライバーにはもうしわけないけどね…。
-

- スーパー耐久2013
- 市販量産車ベースのレーシングカーで参加できる国内最高峰の耐久レース「スーパー耐久」。第4戦 富士スピードウェイではアニキもGAZOO Racingから参戦!
-

- GAZOO Racing 86/BRZ Race
- ニュルでアニキもドライブした86とBRZオンリーのワンメイクレース。プロアマ不問・2メーカー激突のガチバトルを堪能!スーパーGTやスーパーフォーミュラ等と併催も。
-

- GAZOO Racing ワクドキ!サーキットを走ろう!
- ドラテクを磨きたいなら、まずここから。気軽にサーキット走行体験から現役レーサーが直接コーチするワンランク上の講座まで3種類のプログラムをご用意。日本全国で開催中。