かつてWRC世界ラリー選手権が「グループB」規定で行われている時代があった。
市販車で戦われることには違いないのだが、その中身はプロトタイプに近い。連続する12ヶ月に200台生産された車両がベース。グループAが同様に、連続する12ヶ月に5000台の生産がホモロゲーション取得の条件だったことを考えると、メーカーとしてかなりハードルが低い。売れてないマシンでも競技に投入できるからである。
その「200台」のハードルはやがて、エボリシューションモデルとしてならば20台でも認められることになったからサァ大変!メーカーにとってはそれこそ、まったく売れなくてもいいから20台だけ生産すればいいというわけで、戦闘力を高めやすい。その意味では、コスト的にも受け入れやすくなった。
大変なのは、それを操るドライバーである。たった20台生産のエボリシューションということはつまり、速く走るためならがむしゃらに改造していいことになる。市販車とは名ばかりで、中身はまんまモンスターマシンが溢れることになった。それが「グループB」時代である。
たとえば「ランチア・デルタS4」は、900kgにも満たないペラペラのボディに、1.8リッター直列4気筒ツインチャージエンジンを搭載。ターボとスーパーチャージャーを組み合わせて約500psを絞り出していたというからバケモノだ。
しかもシャシーは、コードネームすら市販車とは別物で、その強力無比なエンジンをミッドマウントしていた。市販車のデルタはファミリーセダンである。つまり、リアシートにエンジンを積んでしまうという暴挙に出たわけだ。
「フォードRS200」も同様。こっちはさらにハチャメチャで、バケモノエンジンをミッドシップに積んだことまでは許しても、さらに4WD化するという世界初の試みにトライしていた。
「プジョー205ターボ16」も同様。リアシートにエンジンが乗る。
「MGメトロ6R4」もそう。いまの感覚に置き換えれば、ヴィッツサイズにスーパーGT500のパワーユニットを押し込んでしまったかのようなのだ。
そんなバケモノの世界にトヨタも、「セリカツインカムターボ」を送り込んでいた。
グループBマシンの速さを証明する逸話が某サイトに乗っていたので紹介しよう。
0-100km/h加速は1.7秒だったという。1986年、F1モナコGPが開催されるモンテカルロ市街地コースをランチア・デルタS4がエキジビション走行をした時のタイムが、当時のF1の予選6番手に匹敵したというのだからまさにモンスターである。
そうそう、そしてここからが本題。
そんなモンスターマシンが華やかだったその時代は危険と隣り合わせ。その時代にトヨタラリーチームのエースとして活躍した男が「ビヨルン・ワルデガルド」である。
1943年生まれ。WRCのチャンピオンである。
当時から、ちょっとふくよかな顔つきであり、どこか温厚な雰囲気をたたえていた。だがその眼光は鋭く、さすがに勝負師の魂は隠しきれない。そりゃそうだ、あのモンスターマシンを捩じ伏せるのだから…。
そんなワルデガルド氏が、GAZOORacingの招聘によって新城ラリーに姿を現した。昨年に続いて2度目のデモランを日本の観客の前で披露したのだ。それはもう、会場は大いに盛り上がったという。
御歳70歳(このコラムが公開される11/12が誕生日!)。現役引退が1992年だというから、生ワルデガルドの勇姿を知る人は少ないはずだ。だが、その名は歴史に刻まれており、ラリーファンなら誰もが知る存在。老若男女が大歓声で出迎えたという。
 スティグ・ブロンクビスト氏の現役時代の写真(右の方)だけど、ややふっくらしているでしょ?何故だかこの時代のラリーストは、このタイプが多い。そして眼光が鋭い…!
スティグ・ブロンクビスト氏の現役時代の写真(右の方)だけど、ややふっくらしているでしょ?何故だかこの時代のラリーストは、このタイプが多い。そして眼光が鋭い…!
 新城ラリー2013では、日産の懐かしいマシンもデモランに登場!
新城ラリー2013では、日産の懐かしいマシンもデモランに登場!
実はキノシタも、英国で開催された「グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード」に招待された時に、氏と遭遇している。
学生時代にスピード競技を始め、ダートトライアルやラリーに没頭したキノシタからすれば、ワルデガルドといえば現存する神様のようなものだ。とても柔和な表情が印象的だった。かなり恰幅が良くなったけれど、現役時代さながら、鋭い目線に衰えはない。世界を制した人間というものは、その瞳の闘争心はいつまでたっても薄れないのだろうと思った。短い会話の間、まったく偉そうな素振りをみせずに優しく振る舞うその物腰とは対象的に、まるで瞳の奥に射るような鋭さを失わないことが印象的だった。
かつてキノシタが日産契約時代、WRCラリーマシンの開発をしていたことがある。マシンは「パルサーGTI-R」、2年間に及ぶダート生活をしていた。その時、実践で戦っていたのが「スティグ・ブロンクビスト」。僕はいわば黒子として彼が戦うマシンを開発していたわけである (その話はいずれ…) 。
という縁によって、何度か一緒に仕事をした。その時の彼も、ワルデガルド氏同様に、柔和な表情の中央に鋭く光る瞳を確認している。
さらに、シャモニー24時間氷上レース(スイス)に参戦した時には「アリ・バタネン」とニアミスしている。
前夜祭、こっちは遥々日本からやってきた新人として紹介されており、そこにスペシャルゲストとして登壇。ブルブル震えながら氏の横顔に見とれていた。するとチラリと笑みをよこして、言葉を投げかけてくれたことを記憶している。
あまりの緊張で、なんと言ったのか、何語だったのかすらもわからなかった。まさか「正々堂々と戦おうぜ」なんて謎の東洋人に言うわけもないし、その笑顔から想像するに「邪魔だからちょっとズレてくれる?」でもなかろう。「たぶん、ようこそ…」とか「初めまして…」とかだったのだろうと善意に解釈しているのだが、やはりその時の氏の瞳も、どこか鋭く光っていた。
総じて一世を風靡したラリードライバーには共通した独特のオーラがある。F1ドライバーのように、勝ち気を絵に描いたようなこれ見よがしの闘争心を溢れさせているのでもない。チャラチャラしている素振りはまったくない。むしろ、どこかの国で企業を経営するビジネスマンであるかのように紳士的で落ち着きがあるのだ。
だが、内に秘めた闘争心は隠しようもなく、それが瞳の奥に宿っている。それがラリーチャンピオン達に共通した姿だ。
はるか数1000キロ先のゴールを目指し、サーキットレースとは桁外れの人達によって支えられているのがWRCの特徴だ。
サービスエリアでは、傷ついたマシンを修復するメカニックがいて、ヘリコプターやトレーラーが野戦部隊を先回りして、1台のマシンを待つ。クローズドエリアを周回するレースよりももっとスタッフ間の信頼が欠かせない。そもそもナビゲーターにすべてを委ねてもいる。
人への気遣いを忘れない優しさと、消そうとしても消しきれない鋭い眼光というアンバランスは、そんな環境がそうさせているのかもしれない。
そんな風に思った。
来年こそ、ワルデガルドの勇姿と鋭い瞳を見に、新城ラリーに行こうと思う。
-

-
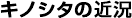
- 凄いドライバーと仕事しちゃった!アメリカで大成功したスコット・プリュエット氏だ。NASCAR、インディ、IMSA、アメリカン・ル・マン、ル・マン24時間…。その活躍を並べたらきりがない。特に印象的なのは、赤いボディに白抜きのターゲットカラーのインディでの活躍。チップ・ガナッシ・レーシングチームに乗っていたといえば、アメリカ音痴の人にもわかるかもしれない。F1で言えばマクラーレン?レッドブル?とにかく凄い経歴の持ち主である。最近、世界的に有名なベテランレーサーとの遭遇が多いな!あれ?もしかして…?
-

- 全日本ラリー選手権
- 北海道から九州まで日本各地で開催される日本最高峰のラリー。さまざまなメーカーのクルマが参戦。最終戦となる第9戦はこのコラムで紹介された「新城ラリー2013」。
-

- TRDラリーチャレンジ
- 初心者向けのラリー形式の草の根モータースポーツ。トヨタ車なら誰でも参加可能(Bライセンス必要)。最終戦のRd.5新城では60台のフル参戦台数となった。
-

- GAZOO Racing ワクドキ!ラリーアカデミー
- ラリーの楽しさをお客様のクルマで、舗装路でお気軽に模擬体験できるプログラム。コマ図の読み方など、ラリーの初歩から分かりやすく解説。ラリーを始めるならまずココから。


















