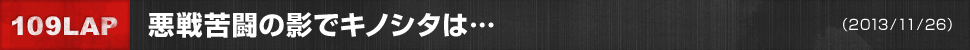グループA規定は、グループB規定より改造範囲が限定されていた。
連続する12ヶ月に5000台の生産がホモロゲーション取得の条件だった。しかも4座席が基本。エボリューションモデルであっても500台の生産を義務づけた。つまり、グループB規定の反省から、4座席に限定したことで世界のほとんどのメーカーに参戦の機会を与え、しかも5000台生産によって、市販車に近い形をうながしたのだ。「街中で見かけるクルマで…」がコンセプトである。
日産はそのグループA時代に、WRC世界ラリー選手権に「パルサーGTI-R」を投入した。実はキノシタ、その開発ドライバーを担当していたのだ。
それはもう過酷で過酷で…(汗)。
日産は伝統的に、世界ラリー選手権マシンの開発をレーシングドライバーに担当させていた。国内ラリーの速度域とは異なることから、よりハイスピード領域に慣れているレーシングドライバーのほうが適任との判断だったと聞いている。
かつては長谷見昌弘さんや星野一義さんが担当、その後、都平健二さんが請け負っていたのだが、ひとりでは体が持たないという理由で補充となった。そこで白羽の矢が立ったのがキノシタだったというわけだ。
学生時代はダートトライアルやラリーで全関東タイトルも持っている。ダート走行は得意中の得意だ。だが、キノシタの才能が期待されたわけではなさそうだった。当時の日産ドライバーの中から選考するとなると、鈴木亜久里はフォーミュラー系だったし、和田孝夫さんや高橋健二さんは、その過酷な労働を嫌がったとも噂されている。
なんといってもその労働時要件が過酷である。まだパルサーGTI-Rが未発表の時期からの開発だったから、走行は真夜中が中心。夜6時に集合し、終わるのは陽が登る直前である。テストコースに抜擢された「東北サファリパークの特設ダートコース」には照明らしいものは一切なく、まさに自衛隊の夜戦行軍のよう。
休憩場所は埃まみれのプレハブ小屋だけ。そこで豚汁や握り飯を頬張りながら、夜通し走るのである。
ゆったりと体を休めるソファーなんてあるわけもなく、もちろん水洗トイレなんて贅沢なものもない。おのずと闇夜に紛れ、草むらで用を足すことになるのだが、都合がいいぞと思う木の影はスタッフも同様の考えを抱く場所、抜き足差し足で忍び込んだ木立の根元には、先客の痕跡がある。靴の裏に妙な弾力性を感じて不快感MAX…なんてこともざら。
では意表をついて…と遠く離れた場所で尻を露にしていると、そこはサファリパーク。獰猛なクマやゾウが、いまにも尻を舐めそうな距離で遠吠えをあげる。その場で転げ回ることもあった。
どうりで高橋健二さんや和田孝夫さんが辞退したわけである。
コースは荒れ放題で、道幅はクルマ2台分もないから、ドリフトさせればテールとノーズが土手に擦れるというコース。それでいて世界狙いだからスピードレンジは高い。着地の強い入力も重要な検証項目。ジャンプスポットもある。電灯きらめく二本松の夜景に向かってジャンプを繰り返した。
1回の走行はたった3ラップ。それをふたりが交互に繰り返す。フルアタックを10分こなし、15分休憩。これが延々12時間続くのだ。
ぜいぜいと息を切らして、呼気も整わないというのに次の走行が指示される。若かったから許容できたのだろう。その繰り返しは壮絶を極める。
ちなみに、テスト走行は月に2週間。1週間のうち月曜日から金曜日までが走行。ウイークエンドはオフなのだが、だからといって東京に帰る気力も体力も残されていない。
定宿だった二本松の民宿で、ひたすら国内時差ボケと格闘する日々。肉体的にあまりに過酷だったから、日産が専属マッサージャーをあてがってくれたほどである。
開発テストといっても、開発初期はトラブルの洗い出しがメインの仕事だ。速く走らせるためのセッティングでもなんでもなく、ひたすらトラブルシューティングに明け暮れる。壊して、直す。その繰り返しなのだ。
「サファリは厳しいんだから…」
それが開発陣の合い言葉。想像を絶する入力を求めてひたすら走行が続くのだ。
 1000湖ラリーのスタートシーン。ラリーではおなじみのセレモニーである。
1000湖ラリーのスタートシーン。ラリーではおなじみのセレモニーである。
 これも1000湖ラリー。わだちの攻略がグラベルラリーでは鍵を握る。
これも1000湖ラリー。わだちの攻略がグラベルラリーでは鍵を握る。
 スカイラインGT-Rでデビューした「電子制御前後駆動力可変システム・アテーサET-S」を投入。
スカイラインGT-Rでデビューした「電子制御前後駆動力可変システム・アテーサET-S」を投入。
今だから話せるのだが、たった一度のジャンプでエンジンが傾いた…なんてことも珍しくはない。ストラットが曲がったなんてこともざら。ボディがひしゃげてしまい、ボディの一方を電柱に括り付け、もう一方をコース整備のために準備していたブルドーザーで引っ張って整える…なんて荒療治もいつものことだった。
とにかく壊すのが仕事だから、のんびり走っていては仕事にならない。体が壊れるか、マシンが悲鳴を上げるかの戦いでもある。
唯一まとまって休憩できるのは、マシンが壊れた時である。だから都平健二さんとこんな企みをしたことがある。
「なぁキノシタ君!」
「はい、なんでしょ?」
「ジャンプの先の路面に岩が飛び出してきたよね」
「はい、サッカーボール大の岩ですね」
走行を繰り返しているうちに路面が掘られていく。すると地中に埋もれていた岩がコース上にニョッキリと顔を出してくるのだ。
「あの岩に全開で突っ込んだらどうなると思う?」
「サスペンションが壊れますね」
「そう、壊れるよね」
「はい…」
「壊れるよねぇ…」
そう言って都平健二さんはにやりと笑った。
「えっ?」
「壊れるよねぇ」
「はい、確実に壊れると思います」
「壊れると…?」
「修理することに…」
「修理するということは…?」
「休憩時間が増える…えっ?」
そうして後輩のキノシタが岩めがけて突き進むのである。
2年間に及ぶそんな夜の仕事から解放され、昼間のテストになったのはサファリラリーに挑むことが正式に発表されてからである。エースドライバーだったS・ブロンクビストを交えてテスト走行を繰り返すようになってからは、なにやら晴れの舞台に立ったような気分になった。
実際に僕がステアリングを握ってWRCを戦うことにはならなかったが、自らが初期から開発したマシンが世界で戦うことには感慨がある。結果的にはチャンピオンを獲得する夢は叶わなかったが、ラリーの日産と言われていたチームのひとつの時代をサポートできたことは幸せだ。
何よりも、ドライビングスキルが磨かれた。成長期にあれほどの走行距離を稼いだドライバーも少ないだろう。照明のない深夜の走行であり、常にマシンはスライドしている。コースオフエリア等皆無。だって土手にマシンをヒットさせながら走るのだから…。
いま、ニュルブルクリンクにこだわり、深夜の走行が楽しく、そしてあのスリリングなステージで戦うことができているのは、あの頃の経験の産物だろうと感謝している。
-

-
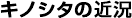
- 「NOLAモータースポーツパーク」は、米国ルイジアナ州ニューオリンズにある。そこで全米レクサスLFAオーナーを集めた走行イベントが開催されたのだ。華やかな前夜祭からサーキット走行!そこにはもちろんGAZOO Racing LFAも登場。アメリカだというのに、僕のことを多くの人が知っていた。さすがにLFAファンですね。それにしても驚きは、オーナー達の裕福ぶり。「もう1台欲しくなった。即金だけどある?」だって!あいにく完売です!(笑) 。
-

- 全日本ラリー選手権
- 北海道から九州まで日本各地で開催される日本最高峰のラリー。さまざまなメーカーのクルマが参戦。
-

- TRDラリーチャレンジ
- 初心者向けのラリー形式の草の根モータースポーツ。トヨタ車なら誰でも参加可能(Bライセンス必要)。
-

- GAZOO Racing ワクドキ!ラリーアカデミー
- ラリーの楽しさをお気軽に模擬体験できるプログラム。コマ図の読み方など、ラリーの初歩から分かりやすく解説。ラリーを始めるならまずココから。