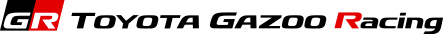スーパーフォーミュラ 2015年 第4戦 もてぎ
エンジニアレポート

ドライバビリティの改善で優位に
アドバンテージを保つため、開発に力を注いでいく
トヨタ自動車株式会社 東富士研究所
モータースポーツユニット開発部 関 貴光エンジニア
2015年のスーパーフォーミュラも、シーズンを折り返していよいよ後半戦に突入しました。8月22〜23日にツインリンクもてぎで行われた第4戦では、シーズン2基目となるバージョンアップしたエンジンが投入されましたが、石浦宏明選手が第2戦の岡山に続いて、見事なポール・トゥ・ウインを決めました。トヨタエンジンとしても、開幕戦からの連勝記録を4に伸ばすとともに、予選Q3に8台中6台、決勝もトップ4まで独占。シリーズ後半戦を素晴らしい結果で始めることができました。これを受け、トヨタエンジンの開発・メンテナンスを通じてTOYOTA GAZOO Racingの各ドライバー、チームを支える東富士研究所の関貴光エンジニアに、第4戦もてぎを振り返っていただき、次戦への抱負をお話ししていただきます。
パワーアップとドライバビリティを改善
今季2基目のエンジン初戦も好結果を得る

トヨタ自動車株式会社 東富士研究所
モータースポーツユニット開発部 関 貴光エンジニア
スーパーフォーミュラでは、トヨタエンジンを搭載するドライバー、チームを応援していただき、ありがとうございます。トヨタのスーパーフォーミュラ用エンジン"RI4A"を担当する東富士研究所の関です。ツインリンクもてぎで行われた第4戦を振り返りながら、今回投入した今シーズン2基目のエンジンについてお話ししたいと思います。
レースでは石浦宏明選手が、ポールポジションから見事な走りで2勝目を飾ることになりました。もちろん我々が用意した新エンジンのパフォーマンスも効果があったと思いますが、何よりも石浦選手のがんばりと、チームの完璧な車体のセットアップとピットワーク、これに尽きると思います。あと決勝レースでは直前に降った雨の影響で奇数列のグリッドがスタートで有利となり、それが結果に影響した、ということも見逃せません。今回のレースはスタートでほぼ決まった部分が大きかったと思います。
新エンジンに関して言うなら、他のドライバーたちも力強いレース展開で、我々が狙っている開発の方向性が間違っていないことが実感できました。それは、これまで以上にパワーアップを追求することに加えてドライバビリティの改善(※1)を図って行く、というものです。特に今回の舞台となったもてぎはストップ&ゴーのレイアウトで知られていますが、ストレートがあまり長くないのでトップスピードはあまり関係なくて立ち上がりのピックアップが重要(※2)なんです。だから車体(シャシー)も、コーナーからの立ち上がりで効率的にトラクションが掛けられるようにセットアップして行きます。その車体のセットアップに、新エンジンの開発で力を注いでいた部分が役に立ったと思っています。純然たるパワーよりもむしろ、そのパワーの伝え方が重要で、絞り出したパワーを活かすも殺すもドライバビリティだと思っています。
※1 「ドライバビリティの改善」 ドライバビリティとは、ドライバーの意思であるアクセルペダルの操作量に、エンジンがどれだけ忠実に反応するか、という特性。一般的に、ターボエンジンではその構造上、NA(過給をしない自然吸気)エンジンに比べてドライバビリティが劣っていると言われます。だが、RI4AではNAにかなり近いと各ドライバーが言うほど改善が進んでいます。
※2 「ピックアップが重要」 アクセルペダルを踏んだ時、エンジンが素早く吹き上がる(回転数が上昇する)のをピックアップが良いと言います。特に走行中にアクセルペダルを踏み込んだ時のレスポンス(ピックアップレスポンス)が重要とされています。
ドライバーのリクエストに応えて
何種類かの制御パターンを用意

表彰台を独占したTOYOTA GAZOO Racing勢
ドライバーの皆さんが「パワーはこれで十分!」と言ってくれることは、当然ありません(苦笑)。でも、最近はパワー以上にドライバビリティの改善に対する要望が多いのです。それはパワーアップよりもドライバビリティの改善の方が、ラップタイムを押し上げる効果があることを分かっているからでしょうね。そしてその要望も、ドライバーによってまちまちです。それはドライバーの好みの問題だけではなく、サーキットのキャラクター(※3)や(各チームの)車体のセットアップに関連しているようです。我々としても、その要望に応えることが大切だと考えています。
レギュレーションによってマップは1種類(※4)しか用意できませんが、制御のパターンでいくつかのバリエーションを用意しています。サーキットの現場でアジャストできる部分は限られているので、基本はサーキットに来る前に用意します。車体の"持ち込みセット"と同じですね。それでサーキットでは朝のセッション(土曜、日曜のフリー走行)で、各ドライバーに幾つかのパターンを使ってもらって、本番(公式予選や決勝)で、どのパターンを使用するかを決めてもらっています。また、路面状況の変化などに対応するため、レース中にもドライバーが選択したパターンを変更できるようになっています。これは開幕戦から継続しているスタイルで、もちろん、いくつかの制御パターンも毎戦毎戦、改善を進めて進化させてきました。スーパーフォーミュラでは、エンジンに関してハードウェアの進化は厳しく制約されていて、新エンジンの投入に合わせて用意するしかないのですが、ソフトウェアの方は少し制約が緩く、制御などは毎戦毎戦、進化させることが可能になっています。
※3 「サーキットのキャラクター」 サーキットのコースレイアウトからくる性格、特性。簡単に言えば「高速コース」「テクニカルコース」といった表現です。エンジニアの面からは、ストレートがどれだけタイムに影響するのか? 重視するコーナーは低速系か高速系なのか? と、もっと詳細な分析がされます。この特性によって車体やエンジンも、セットアップの方向性が決まってきます。
※4 「マップは1種類」 現代のエンジンは回転数や負荷の状況など各種データを車載コンピュータに送り、"運転状態"に応じて燃料の噴射量や点火時期などをプログラムによって制御しています。そのプログラムが基準にする"指示書"がマップです。他のレースでは複数のマップをレース中に使い分けることもありますが、スーパーフォーミュラではレギュレーションで、1種類のマップしか認められていません。
この後のオートポリスとSUGOは
エンジンの要求項目が似たサーキット

レース終盤、驚異の追い上げをみせた中嶋一貴選手
今回のもてぎ戦で投入した新エンジンはこの後、第5戦のオートポリス、第6戦のSUGO、そして最終戦の鈴鹿、と都合4レースで使用することになっています。これはレギュレーションで決まっていて当然、十分なマイレージ(ここでは性能を保証する距離の意味)も確保しています。前回の富士と同様、今回のもてぎも、サーキットのキャラクターは他のコースとは大きく違っていますが、次のオートポリスとSUGOは、比較的似たキャラクターとなっていて、エンジンへの要求項目も似ています。燃料流量リストリクターの規制値に関しても、最終戦の鈴鹿では95kg/h(※5)となりますが、オートポリスとSUGOは、今回のもてぎと同様90kg/hに制限されています。
今回、(エンジン開発の)方向性が間違っていなかったことが分かったので、引き続き、ドライバビリティの改善を進めていきます。今回間に合わなかったアイテム(※6)もありますから、まずはそう言ったものから順次投入して行くつもりです。
結果的には圧勝というイメージもありますが、"ライバルと比べて最高出力ではあまり差はない"というのが我々の分析です。理論的にも、絶対的なパワーで大きく差をつけることは難しいと思うので、やはりドライバビリティをどのようにして、どこまで改善していくか、が重要になってくるでしょう。このままアドバンテージを保って、勝ち続けていきたいと思っています。これからもTOYOTA GAZOO Racingのドライバーたちが全力を尽くせるようがんばりますので、彼らへの応援をよろしくお願いします。
※5 「鈴鹿では95kg/h」 RI4AなどNRE(ニッポン・レース・エンジン)では、使用する燃料の流量をリストリクターによって制限して、安全性や経済性を無視した開発競争に陥らないようにしています。昨年は100kg/h(1時間当たり100kgが流れる)を基準にしていましたが、エンジン開発が進んだ今季は鈴鹿と富士の95kg/hを基準に、それ以外のサーキットでは90kg/hとなりました。この流量による制限は、少ない燃料でより効率の良い出力を得る技術を追求するもので、市販車の環境技術にも反映されています。
※6 「アイテム」 ここでは技術アイテムのことで、性能向上のために使われる新技術や新しいパーツのことを指します。アイデアを具現化し、設計・開発からテストを経て実戦に投入されます。「新しい"タマ"を入れる」のように使われる"タマ"も同義語です。