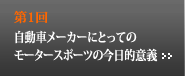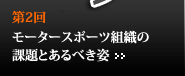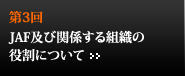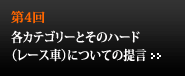![]()
未曾有の経済危機の影響を真っ先に受け、日本のモータースポーツは今瀕死の状態にある。しかし、こうなったのはこの経済危機のせいだけではない。1990年代初めのバブル崩壊の後から既にジリ貧状態にあり、その間もただ手を拱いていたわけではないが浮揚させられなかった。これは時代の変化に対応すべき今までの改革が中途半端であったという証にもなる。
今回の不況は自動車産業を今までになく痛撃しており、それも化石燃料の枯渇、地球温暖化ガスの排出問題というモータースポーツにもアゲインストとなる風を伴っている。従って本気で手を打たないと今度こそ生き残れないことになる。
そういう中、日産系の筆者がトヨタのHP上で「メーカーの枠を超えてモノ申す」機会を頂いたので、厳しい現実を改革の好機と捉え、日頃から考えていることを4回にわたり述べてみたい。
改革案であるから当然痛みを伴うし、関係者の一部には不快に感じる方もいると思うがご理解を頂きたい。

最初に、自動車メーカーにとってのモータースポーツの今日的意義を論じる。
クルマが発明されたのは1886年で、1894年にはパリ-ルーアン間で初めてのレースが行われている。1908年にはT型フォードの量産化が始まり、ルマン24時間レースは1923年から開催されているように、100年位前のクルマの黎明期からモータースポーツは常にクルマと共にあった。
そして自動車メーカーは、“技術開発促進”、“ブランド及び特定車種の知名度やイメージ向上”、“競争を通じた人材育成”などに意義を見出し、積極的にモータースポーツに関与してきた。結果としてそれぞれに成果も上がり、多くの著名なブランドも生まれた。
しかし、今奇しくも100年に一度と言われる危機が訪れ、自動車の存在価値に根本的見直しを迫っている。となるとモータースポーツの価値にも当然仕切り直しが必要になる。

市場がハイブリッド車や電気自動車、或いは小型車へとシフトが進む一方で、若者は携帯電話に代表される手軽な娯楽に関心が向き、クルマ離れが著しい。ある調査によると今の大学生は団塊世代に比べ興味を持つ事柄の数が2倍あり、またクルマを危険で環境に悪いとネガティブに捉える傾向が強いそうである。原因はいろいろあるがこれを放置しておくとクルマは単なる移動手段の道具と化し、環境にやさしく、安全で、安価な必要最小限の機能を備えたもので充分となってしまう。例を挙げれば電気冷蔵庫や電気洗濯機、或いは掃除機のような白物家電と同じ扱いである。
ところがクルマには白物家電と違って、“持つ喜びや誇り”及び“走る楽しさ”などの人格がある。これは人々に夢や希望を与え、情熱や感動という心を揺さぶることになる。
自動車産業には世界の就業人口の約10%が従事しているので、世界をリードする産業として成長し続けることが社会的正義でもあるが、その為には便利な道具を提供する一方で、このようなクルマの魅力を付加価値として高め、成長に生かしていく必要がある。
クルマの本来持つ魅力や価値を、若者をはじめ多くの人に知らしめ、又共感、共有して貰うには、人の持つ競走本能に訴えかけるモータースポーツが最も効果的である。
自動車メーカーは今までもモータースポーツを通じてブランド構築やクルマ文化の醸成、憧れのヘリテージつくりなどで貢献してきたが、これからは産業としての存続、発展を賭けてモータースポーツの底辺を支え、自らも参戦していくことがもっと大事な時代になっている。
次回はモータースポーツ組織の現状と課題及びあるべき姿について述べる。
【編集部より】
本コラムの記事について、みなさまからの声をお聞かせください。
GAZOO編集部“ジミーブログ”にてみなさまのご意見をコメント欄にご自由に書き込みください。


-
1945年鹿児島に生まれ 現在63歳。
鹿児島大学工学部卒業後、日産自動車に入社、モータースポーツ業務に携わる。
スポーツ車両開発センター部長を経て、1996年ニッサンモータースポーツインターナショナル(通称ニスモ)に転籍。 常務取締役を退任後、2008年より東海大学工学部教授。
ニスモではスーパーバイザーとして日産系スーパーGT500チームの総監督を務める。
「レーシング・オン」にコラムを連載中。