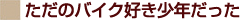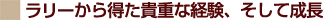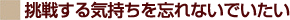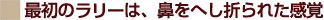トヨタ車体の自社ラリーチーム、「チームランドクルーザートヨタオートボデー(TLC)。」主要メンバーが同社の社員で構成されているそのチームで、社員の期待を一身に背負うのが、1号車のステアリングを握るプロのラリースト三橋淳選手だ。最初はバイクでパリダカに挑戦して好成績を挙げ、その後4輪に転向。2011年1月に行われるダカール2011では、自身にとっての3連覇を目指すとともに、チーム6連覇の記録を狙う。森達人監督にとって、頼れる長男坊にあたる三橋選手だが、かつては競技とは無縁の、ただのバイク好き少年だったという。
「もともとバイク好き、旅好きで、路面を選ばないで走れる方がいいから、オフロードバイクを買った。どこにでもいるごく普通の高校生ライダーでした。そこからバイク雑誌などを読み始めて、パリダカのことも知るようになったんですけど、ラリーの映像を見たのは、たまたまTVでファラオラリーを見たのが初めて。そもそもは競技嫌いというか、人と争うのも好きではないし、興味もなかったので、ラリーに出るつもりなどなかったんですよ。ただ、海外に行ってみたいという憧れはありましたけどね。」
そんな三橋選手に、競技参加のきっかけを与えたのは、行きつけのバイクショップ。間もなく競技の魅力、楽しさに気づいた三橋選手は、そこから10年ほど国内の競技に参加したが、本格的に活動するようになったのは、20代後半になってから。初めてパリダカに行ったのも、30歳の時。そこには新鮮な驚きが待っていたという。
「とにかく大会の規模が大きくて、圧倒されました。日本であれほど大きなモータースポーツイベントが見られるのはF1ぐらいだと思いますけど、そんな規模の大会に自分が出ていること自体に圧倒されました。大変だったコースですか? アフリカ最深部のコースを走ったとき、かな。肉体への負担が大きくて、ライダーの中には、ゴールしてナイフもフォークも持てないぐらいやつれているやつもいました。あ、でも僕はそんなことなかったかな。その時もいつものように、ラリーが終わったあと、原稿とか写真をインターネットで日本に送っていましたから。10年間、日本で色々なラリーに出て鍛えられたのかもしれません。」
さすがケイン・コスギに似ていると言われるタフガイ。実際に見る三橋選手も、背が高く、とてもガッチリしているのが印象的だった。そんな三橋選手は、2004年に4輪に転向。日産のファクトリーチームからパリダカに参戦する。だが、バイク時代と違い、4輪チームは現場だけでも60人という大所帯の"組織"。そこでの人間関係は2輪時代には経験しなかったもので、頭を悩ませることもあったという。しかしそこでの経験も、三橋選手の人間としてのスケールを大きくした一つの栄養となったのではないだろうか。
その後、2007年にTLCに加入。次第にチームが1つにまとまっていく過程をつぶさに見てきた。
「最初に入った時は、まだアラコからトヨタ車体になったばかりで、会社とチームは別という雰囲気でした。でも、去年ぐらいから、会社の上層部の人たちも含め、みんながチームの一員という意識を持ち始めたというか。一体感が生まれた感じですね。そこでの僕の仕事は成績を出すだけ。すごくシンプルですし、やることは鮮明です。そういう環境で仕事をできるようになったのは、今の森監督のおかげです。」
選手として、結果を残す。それだけを考えて走るという三橋選手は、競技中に景色を楽しむことはない。現地の食事に触れることもないという。ただテストの時だけは、「ああ、いいなぁ、アフリカは」という風に、風景に心を打たれることもあるらしいそのあたりは、私たち一般人と変わらないようだ。ダカールは想像もつかないところと思いがちだが、もともと旅好きの三橋選手に言わせると、けっして特別の場所ではないらしい。
「確かに、ダカールは皆さんの思う非日常の世界かもしれません。でも、それは休暇でどこか知らない場所に行ってみたいなとか、どこかで思い切りアクセルを踏んでみたいっていう欲望の延長線上にある世界。例えば、東京から長野に行こうと思ったら、途中でいくつかの山を越えて行きますよね。そのような旅を、タイムを計りながらやっている。そんな感じの競技です。」三橋選手にとっては、山や砂丘、泥の中で遊ぶ道具が、足から自転車、バイク、そして4輪へと変わっていっただけ、なのだという。
「今、日本人が全く世界で通用しないっていうイメージを持っている人が多いじゃないですか。でも、こういう時代だからこそ、世界の舞台で戦う日本人、日本企業があるということを知ってもらいたい。"できないよ"と考えるのではなくて、見て、好奇心を持ってもらいたいと思います。イマジネーションの源は、好奇心。行ってみたい、やってみたいという気持ちが、モータースポーツにも、他の分野にも必要なんだと思います。」
キラキラした瞳で、このように話してくれた三橋選手。トヨタ車体の社員だけでなく、すべての人を勇気づけてくれそうなメッセージだ。
![]()
トヨタ車体の自社ラリーチーム、トヨタランドクルーザートヨタオートボデー(TLC)は、ここ数年、2台体制でダカールラリーに参戦している。2011年1月に出場する大会も、体制は同じ。1号車はエースカーとして、そして2号車はサポート役として、2台でチームの6連覇を狙っていく。その2号車のステアリングを握るのは、今年チームに加入した寺田昌弘選手。ドライバーとして以上に、ナビゲーターとしての経験が豊富で、同じマシンに乗ることになる新人の社員ナビ・田中幸佑選手の教育係も務めることになるという。そんな寺田選手は、子供の頃からの冒険好き。パリダカにも、中学時代から憧れた。
「最初はTVで見て。競技内容も何も分からなかったんです。でも、砂丘を越えてくるバイクの人の目に、カメラが寄った時、その目にインスパイアされて、"あそこに行きたい"と思いました。それがパリダカだったと後で分かりました。そもそも冒険好きだったので、創始者のティエリー・サビーヌの考え方に影響を受けましたね。」
中学3年生の時に、"お年玉"をはたいてオフロードバイクを購入し、クローズドコースで走りの練習をしたという寺田選手。大学4年の時には、オーストラリアン・サファリという大会にも出場した。大学を出ると一般企業に就職。5年で退職すると、NPOの医療支援で、年のうち約1カ月をモーリタニアで過ごし、通信インフラの整備などを行っていたという。そして1997年、初めてのパリダカにドライバーとして「ランドクルーザー70」で挑戦。この時は、残念ながらリタイヤに終わったが、1998年にはナビゲーターとしてクラス優勝を果たしている。が、ここまではまさに趣味。借金をして仲間内で参加し、専属のメカニックもアシスタントもいない状態だった。それでも、随所に感動があったと寺田選手は振り返る。
「最初に出てリタイヤした時は、マリという国だったんですが、そこから1週間ぐらいかけて、自力でセネガルまでたどり着かなければならなかったんです。先輩方にも、"パリダカはリタイヤしてからが本当の冒険だ"と聞いていましたが、その通りでした。その最初の出場で思ったのは、出ている人たちが想像していた以上にカッコいいということ。完走する人たちは、自己責任ということに対する意識がすごく強くて、鼻をへし折られたような感じでした。自分ではそういう部分にある程度の自信があったつもりだったんですが、まだまだでしたね。その後、2回目にクラス優勝した時は、続けていればいいことあるなって思いました。ゴール後のパーティでは、僕らが参戦していたような小さなクラスまで表彰されるとは思っていなかったので、名前を呼ばれた時は感激でした。最初はみんな"誰だ、誰だ?"っていう感じだったんですけど、僕らのことだとわかると、『おお、アイツら、生き残っていたんだ』って、みんながワーッと拍手してくれて。うれしかったですね。その大会では、初めてナビゲーターをやって、最初は脳みそがかゆくなる感じだったんですけど、徐々に慣れていき、意外と自分の感性に合っていると感じました。前夜に渡されるルートを自分の仮説の中でロケハンして、未来の予測を立てる。翌日には、その予測した未来と現実を刷り合わせてドライバーに伝える。そのような作業が、ミスなくどんどんやっていけたんです。」
この2回の大会出場後、寺田選手は10年ほど選手としてはダカールに挑んでいない。さまざまな冒険をしながら、フリーのライターとして記事を執筆したり、取材者としてダカールに同行したりという日々が続いた。しかし、縁あって2008年に片山右京選手のナビゲーターとしてダカールに復帰することが決まった。あいにくその年の大会はテロにより中止となったが、2009年には再び片山選手と競技に挑んだ。
そして2011年、TLCのドライバーとしてダカールに挑む。南米大会は2度目の出場となるが、"4700メートルも高低差があるコースだし、アンデス越えや世界一乾いているアタカマ砂漠に行けるのが楽しみ"と声を弾ませる。アフリカでも周囲360度にディンプルが広がる砂漠の光景に驚いたというが、今回もダカールそのものを楽しみたいそうだ。このあたりのとらえ方は三橋選手と違うところだ。では、新人・社員ナビゲーターの田中幸佑選手を教育するという役目についてはどのように考えているのか。
「今、田中ナビは28歳なんですけど、僕が初めてパリダカに行った時と、同じ年代なんですね。だから、自分を投影する部分があります。色々なことを教えていく中で、彼が悩んだりすることもありますが、それが鏡となって自分に跳ね返ってくることもある。でも、着実にステップアップしていますし、初めてではあるもののスキルは高いですよ。今はお互いに半人前かもしれませんが、大会中にそれぞれが1人前以上になって、ゴールに戻ってきたいですね。」
自身も、三橋選手からさまざまなドライビングスキルを学んでいるという寺田選手は、チームの中では社交的な次男坊的存在。三橋選手をサポートしつつ、同時に末っ子の面倒を見るという大役も、寺田選手にならできそうな気がする。