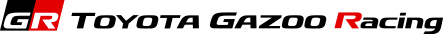レースで鍛えられるハイブリッド技術
THS-Rと市販ハイブリッド車の密接な関連性(2/3)

モータースポーツも環境性能を追う時代に
 量産乗用車のハイブリッドシステムを進化させる一方、トヨタはハイブリッドシステムをサーキットにも送り込んだ。言うまでもなく、ハイブリッドカーの"走る楽しさ"をさらに追求し可能性を探るためだ。限界の走行性能が求められるモータースポーツの世界でハイブリッドシステムを鍛え上げれば、その技術は量産乗用車のハイブリッドシステムをさらに進化させるに違いない。
量産乗用車のハイブリッドシステムを進化させる一方、トヨタはハイブリッドシステムをサーキットにも送り込んだ。言うまでもなく、ハイブリッドカーの"走る楽しさ"をさらに追求し可能性を探るためだ。限界の走行性能が求められるモータースポーツの世界でハイブリッドシステムを鍛え上げれば、その技術は量産乗用車のハイブリッドシステムをさらに進化させるに違いない。
またモータースポーツといえども環境技術と切り離しては成立しない時代がやってくると判断、そのときに活躍できるレーシングカーを開発しようという希望もあった。トヨタは2006年、レーシング・ハイブリッドシステムに初めて取り組むことになった。
量産ハイブリッド車はストップ&ゴーの多い市街地での走行を得意とするが、高速走行時は相対的に効率が落ち、燃費向上のメリットを得にくい側面があった。レースに出場してサーキットを走れば、高速域からの急減速を繰り返すことになる。その際発生する大きなエネルギーを瞬時に回収できる技術を確立するのが、レーシング・ハイブリッドシステムにとって大きな課題のひとつであった。そのレース活動で得た技術を量産ハイブリッドシステムにフィードバックすれば、低速域から高速域まで効率の高いハイブリッド車ができあがる。そこに、レースでハイブリッド技術を鍛える意味があった。
2006年にハイブリッドレーシングカーが初登場

2006年、開発陣は当時最新の量産ハイブリッド車の1台、レクサスGS450hをベース車両に選び、量産ハイブリッドシステムのうちニッケル水素バッテリーをキャパシタに換装し、十勝24時間レースに出場する決意を下した。これには、エネルギー貯蔵装置としてのキャパシタの素性を確認するという、先行試験の意味合いがあった。
当時のGS450hは、3.5リッターV型6気筒エンジンを搭載したFR車であり、FF車ベースのプリウスからハイブリッドシステムが移植された「世界初のFR量産ハイブリッドカー」であった。しかもハイブリッドシステムを燃費より出力重視で使用する"走る楽しさ"を追求したハイブリッドカーとしても注目されていた。レース用ベース車両にはうってつけの素性を持っていた。
 その後、TS040 HYBRIDに至るトヨタのレーシング・ハイブリッドカー開発を指揮することになる村田久武プロジェクトリーダー率いる開発陣は、「夏の北海道、十勝スピードウェイで開催された24時間耐久レースにハイブリッドシステムを持ち込むと何が起きるか?」に的を絞ってレースを闘った。レクサスGS450hは、大きなトラブルを起こすことなく24時間を走りきり総合17位でレースを終えた。この過程で種々のデータが収集された。
その後、TS040 HYBRIDに至るトヨタのレーシング・ハイブリッドカー開発を指揮することになる村田久武プロジェクトリーダー率いる開発陣は、「夏の北海道、十勝スピードウェイで開催された24時間耐久レースにハイブリッドシステムを持ち込むと何が起きるか?」に的を絞ってレースを闘った。レクサスGS450hは、大きなトラブルを起こすことなく24時間を走りきり総合17位でレースを終えた。この過程で種々のデータが収集された。
そのデータを基に翌2007年、開発陣は改めてレース専用のハイブリッドシステムを開発し、再び十勝24時間レースに出場した。このときベース車両に選ばれたのは、国内最高峰ツーリングカーカテゴリーのSUPER GTのGT500クラスに参戦していたスープラであった。
ハイブリッドのスープラが十勝24時間で優勝
 2007年当時、SUPER GTのGT500クラスで覇権を争っていたトヨタ・スープラは、480PS以上を発生するレース専用V型8気筒4.5リッター自然吸気エンジンを搭載、トランスアクスル方式の駆動系を持っていた。開発陣は、基本レイアウトをそのままに、モーター/ジェネレーターユニット(MGU)をリヤアクスルに組み込み、エネルギー蓄積装置としてキャパシタを搭載した。また、フロントにインホイールMGUを搭載し、高効率の4輪回生を実現した。その後4輪回生システムは、2014年のTS040 HYBRIDでル・マン24時間レースの実戦を戦うことになる。
2007年当時、SUPER GTのGT500クラスで覇権を争っていたトヨタ・スープラは、480PS以上を発生するレース専用V型8気筒4.5リッター自然吸気エンジンを搭載、トランスアクスル方式の駆動系を持っていた。開発陣は、基本レイアウトをそのままに、モーター/ジェネレーターユニット(MGU)をリヤアクスルに組み込み、エネルギー蓄積装置としてキャパシタを搭載した。また、フロントにインホイールMGUを搭載し、高効率の4輪回生を実現した。その後4輪回生システムは、2014年のTS040 HYBRIDでル・マン24時間レースの実戦を戦うことになる。
 2007年の十勝24時間レースに出走したハイブリッドレーシングカー、スープラHV-Rは、3136kmを走って総合優勝を果たした。この結果、ハイブリッドシステム非搭載の場合と比較して約10%の燃費向上が確認された。国内レースとはいえ、24時間レースに優勝したことで、レーシング・ハイブリッドシステムの方向性は明確になっていった。
2007年の十勝24時間レースに出走したハイブリッドレーシングカー、スープラHV-Rは、3136kmを走って総合優勝を果たした。この結果、ハイブリッドシステム非搭載の場合と比較して約10%の燃費向上が確認された。国内レースとはいえ、24時間レースに優勝したことで、レーシング・ハイブリッドシステムの方向性は明確になっていった。