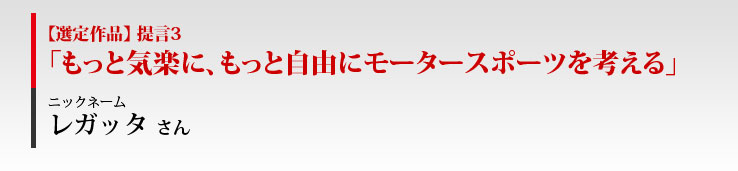モータースポーツを盛り上げるといっても、簡単に効果を上げられる秘策が存在するのだろうか?オリンピックやサッカーのワールドカップなどの様子をみると、モータースポーツも同じようにならないものかと感じる人も多いのかもしれない。だからといって、国別対抗のイベントを企画したり、日本人選手が好成績をあげたとしても盛り上がるとは限らない。それはモータースポーツに限らず、他のスポーツでも同様である。なぜならば、国別対抗イベント、ヒーローの誕生、メディア露出の増加というのは、「盛り上がる」という現象における起点ではなく最終局面でしかないからである。そして、イベント規模や選手の活躍以上に重要なのは、そのスポーツ自体の魅力である。国別対抗戦であれば何でも良いのではなく、サッカーだからこそワールドカップが盛り上がったのであり、ワールドベースボールクラシック(WBC)も野球だったから注目されたのである。当たり前すぎて見逃されているが、対象のスポーツに対する理解がベースにあってはじめて盛り上がるのである。もちろんこのようなビッグイベントでは、いわゆる「にわかファン」も多いのだが、逆にいえば簡単に理解できる要素があるとも言える。結局モータースポーツを盛り上げるためには、モータースポーツを多くの人に理解してもらうこと以外にないのである。
モータースポーツといっても様々な側面から捉えることができるが、ここでは少しおおらかに考えてみたい。どうしてもモータースポーツが持つ「凄さ」を強調したくなってしまうのだが、これではモータースポーツの原点がわかりにくいように思われる。最高峰の競技であれば凄くて当たり前なのだが、逆に日常のクルマの利用とモータースポーツがかけ離れてしまう。たとえばサッカーや野球であれば、最高峰のイベントであっても、凄さだけでなく無意識に身近さも感じているはずである。なぜなら子供のころからボールを蹴ったりキャッチボールをした経験、少なくとも他人が遊んでいるのを見たことがあるからである。一方、モータースポーツでは凄さは感じるかもしれないが、ほとんどの人は自分がモータースポーツをするとは考えてはいないのではないのだろうか。つまり、最高峰の競技とくにF1だけをモータースポーツであると認識しているのである。
ところが、モータースポーツという「くくり」は、サッカーとか野球とか相撲などのような競技種目を示しているのではなく、もっと大きな枠組みである。何よりもF1にせよSUPER GTにせよモータースポーツの競技は、非常に不安定である。60年続いているF1(formula one)規定ですら内容は数年ごとに変わっていて、過去と比べると全く別物であることがわかる。それどころか競技自体が数年で廃止されたり、また新しく創設されたりもする。他のスポーツ競技と違って、常に変わり続けているのである。そして世の中には、いわゆるスポーツカーあるいはスポーツバイクと呼ばれる乗り物がある。これらは競技専用ではないし、サーキットなど限られた場所だけで使われるものでもなく、あくまでも一般の人が公道で使う乗り物である。このようなスポーツカーなどの存在は、競技でなくてもモータースポーツが成立することを証明している。要は乗り物に乗って楽しむことができれば、それで充分なのである。そのように考えると、別に高性能なスポーツカーである必要もない。オートマであろうがミニバンであろうが走りさえすればよく、決して凄くなくてもモータースポーツはできる。モータースポーツは特殊ではなく、むしろ日常に近いスポーツに感じられるのである。
どのようなスポーツであっても、その原点は「楽しむ」ことにある。サッカーのワールドカップで優勝することは非常に凄いことに間違いはないが、ボールを蹴りあって楽しむ行為に変わりはない。モータースポーツの理解にとって必要なことは、「乗り物で楽しむ」という原点を再確認することなのである。
「乗り物で楽しむ」という観点に立てば、モータースポーツをもっと自由にとらえる事ができる。たとえば、モータースポーツはスピードを出すことの代名詞のように扱われている。しかし、乗り物で楽しむのであれば、極端に速いスピードでなくてもよい。クラシックカーレースのように、交通法規を遵守して法定速度内でも競技は成立する。それだけでなく、速さを競うことつまりレースである必要もない。エンジンが付いていれば、そのスピードは魅力であるが、乗り物の魅力はそれだけではない。ドリフトさせたり、モトクロスバイクでトリックを決めたり、トライアルのように障害物を走破することも乗り物で楽しむことになる。決して速さを競うことがモータースポーツの絶対条件ではないのである。たまに記録映像で見かけるようなボロ車を動けなくなるまでぶつけあうことも、乗り物で楽しむ、つまりモータースポーツなのである。
さらにいえば、運転だけが乗り物で楽しむことではない。乗り物にはモノとしての魅力があるので、分解、組み立て、改造、製作、設計という「乗り物いじり」だけでも楽しむことができる。つまり、ドライバーやライダーだけでなく、ピットクルーやメカニックやそれを指揮するクルーチーフやエンジニア、さらにはデザイナーやマシン製作者もモータースポーツにおけるプレイヤー(楽しむ人)である。スポーツに対して身体的な活動をイメージしている人には馴染みにくいのかもしれないが、それだけモータースポーツには幅広く楽しめる要素があるのである。
また乗り物で楽しむ点においては、その動力が何であろうと共通する部分は多い。脚の力で動かす自転車や風の力で動かすヨット、あるいは木箱に車輪をつけて坂道を下るだけのソープボックスダービーでも、乗りこなす楽しみや乗り物をいじる楽しみは何ら変わりない。だから、モータースポーツの入り口はレーシングカートやポケットバイクだけではなく、三輪車でも雪ぞりでもかまわない。乗り物で楽しむこととして考えれば、モータースポーツのおもしろさや魅力が身近なものとして感じられるのである。
このように乗り物はモータースポーツにおける中核である。にもかかわらず、その乗り物が充分に評価されているとは言い難い。しばしばモータースポーツがスポーツとして扱われないのは、乗り物を使っているからである。この乗り物が否定されるキーワードは、「機械」である。同じ乗り物を使っていても、人間の筋力で動かしている自転車競技やボート競技がスポーツであることを疑われることはない。一方モータースポーツでは機械の動力であるモーター(エンジン)を使っていて、その乗り物はまさに機械の塊である。スポーツに機械を使うことによって、人間の能力を阻害することだと決めつけられているのである。このようなイメージに根拠があるわけではなく、実は単なるレトリックの問題にすぎない。たとえば「機械のように働く」とは、自分の感情や意思をなくして働くことを表現している。つまり機械とはメカニカルな装置だけを意味するのではなく、人間でないことや人間と対極的な存在として扱われている。確かにスポーツには、身体的、肉体的活動であるイメージが強い。しかし、機械で楽しむことが人間性をスポイルするとは思えない。そもそも機械を使うことは、決して人間であることを否定することではない。人間の知恵と技術を結集したものが機械であり、逆に人間の存在の証(あかし)なのである。
むしろモータースポーツは、非常に人間的なスポーツである。なぜなら人間の能力は、筋力などの身体能力だけではないからである。乗り物を使うことによって、テクノロジー、ビジネス、政治などの能力も必要になる。だからこそ様々なおもしろさを感じることができる。また男女の区別なく、あるいは身体にハンデを負っていても同じ条件で楽しむことができるスポーツでもある。いわゆるスポーツマンやアスリートだけでなく、多くの人が楽しむことができるのである。乗り物を使うことは、決して人間の存在を台無しにしてロボットのようになることではない。逆に人間の能力や可能性を高めたり、喜びを感じさせるのである。
モータースポーツは乗り物を単なる移動手段ではなく、楽しむために使うからこそ乗り物に魅力を感じるのである。乗り物に対して魅力を感じられれば、なんらかのきっかけによってモータースポーツが盛り上がるようになるはずである。