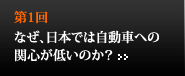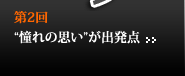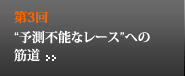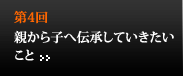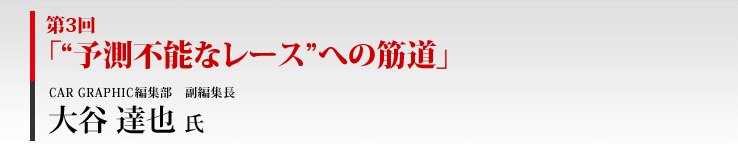![]()
 今回は、私の個人的な視点から「今後のモータースポーツに望まれること」を論じてみたい。
今回は、私の個人的な視点から「今後のモータースポーツに望まれること」を論じてみたい。
前回、私は「競技が終わるまで結果を予想できず、ハラハラドキドキの連続となることを観客は期待している」と書いた。また、どんなに強い競技者であっても、ファンの関心をつなぎとめるためには「3~4割の勝率が上限」とも指摘した。同様のことを考えるのは私ひとりではなく、「予想がつきにくいレースにする」ことや「ひとりの競技者が勝ち続けないようにする」ことを目指し、レースの現場ではすでに様々な試みが行なわれている。F1の予選が手を変え品を変えながら3セッションに分けて実施されるのは、スターティンググリッドを少しでも意外なものにするのが目的であり、レース中の給油を認めているのは戦略に幅を持たせてレースに意外性を織り込むことを狙ったものといえる(筆者註:F1では2010年からレース中の給油が禁じられる)。日本のスーパーGTやドイツのDTMでウェイトハンディキャップ制度が導入されているのも、特定の競技者が勝ち続けるのを防ぐのが目的だろう。いずれも一定の効果を生み出してはいるが、私には全面的に賛成することができない。以下に、その理由を述べたい。
もしも多くのファンを獲得したいのなら、ルールはできるだけシンプルなほうが好ましい。反対に、ルールが複雑なスポーツは、競技者も観戦者も数が限られるというのが私の持論だ。サッカーほどシンプルなルールのスポーツは他にない。分かりにくいのはオフサイドくらいのもので、あとはルールを知らなくてもゲームを楽しめる。これこそ、サッカーが世界中の地域で高い人気を誇っている最大の理由だろう。では、クリケットはどうか?イギリス、オーストラリア、インドなどの、いわゆる英連邦出身者を除けば、そのルールに馴染みのある人の数はごくごく限られている。クリケットが世界的にメジャーなスポーツになりきれない理由の一端はここにあると推測される。また、クリケットを祖先とする野球は日本やアメリカでこそ人気が高いが、世界的に見れば国民的スポーツとして受け入れられている国のほうがずっと少ない。これもルールが複雑なことに原因があると見ていい。
自動車レースも、理想は「速いものが勝つ」というシンプルな構造であるはずだ。けれども、現状のままでは、何らかの操作を加えないとレース展開が単調なものに陥りやすく、特定の競技者が勝ち続ける恐れが高い。しかし、だからといってルールを複雑怪奇なものとすれば、門外漢にとってわかりにくいものになり、元も子もなくなる。では、どうすればいいか?
現代のモータースポーツと、サッカーに代表される球技とを比べると、競技の再現性や不確実性に大きな違いがあることに気づく。この、球技における再現性の低さや不確実性の高さが、予想もできない試合展開を生み出す大きな要因となっている。サッカーでは、精妙な動きを再現することが本質的に難しい人間の“脚”を使い、球形のボールを蹴る。当たり所によってボールがどこに飛んでいくかわからないのは当然のことだが、にもかかわらず、得点を挙げるには数m~数10m先のゴールをセンチメートル単位の精度で狙わなくてはならない。どんなに一流の選手でも、毎回毎回同じ結果を得るのは不可能だろう。しかも、1チーム11名、つまり合計22名の選手がそれぞれの意思を持って動いているのだから、同じフォーメーションになるのは偶然以外に考えられない。再現性が低いのは当たり前のことだ。
野球やゴルフでは、比較的小さなボールをバットやクラブなどの道具で叩いて飛距離やコースを競う。道具と、丸いボールがどんな位置関係でぶつかるかによって飛び方に大きな違いが生まれるのは当然である。
 サーキットレースでは、ライバルとの競り合いによって意外な展開が生まれる余地も残されているが、トップドライバーがひとりで走っている限り、延々と一定のペースを保つのはそう難しくない。プロ野球の選手であれば、何度でも同じようにバットをスイングできるのと同じことだ。しかし、実際の野球では、ピッチャーが投げるボールを打たなければならない。したがって、打球がどこに飛んでいくかは、バッターのスイングという要素と、ピッチャーが投げるボールの球種という要素の組み合わせによって決まることになる。程度の差はあれ、同様の傾向は他の球技にも見られる。例外はゴルフだろうが、あれだけ小さなボールを数100mも飛ばすのだから、不確実性が高いことは論を待たない。これとは対照的に、モータースポーツではドライバーの操作だけでほぼ一義的に結果が決まる。極論すれば、似たような試合展開を繰り返して観客を飽きさせる危険性をモータースポーツは本質的にはらんでいるのだ。
サーキットレースでは、ライバルとの競り合いによって意外な展開が生まれる余地も残されているが、トップドライバーがひとりで走っている限り、延々と一定のペースを保つのはそう難しくない。プロ野球の選手であれば、何度でも同じようにバットをスイングできるのと同じことだ。しかし、実際の野球では、ピッチャーが投げるボールを打たなければならない。したがって、打球がどこに飛んでいくかは、バッターのスイングという要素と、ピッチャーが投げるボールの球種という要素の組み合わせによって決まることになる。程度の差はあれ、同様の傾向は他の球技にも見られる。例外はゴルフだろうが、あれだけ小さなボールを数100mも飛ばすのだから、不確実性が高いことは論を待たない。これとは対照的に、モータースポーツではドライバーの操作だけでほぼ一義的に結果が決まる。極論すれば、似たような試合展開を繰り返して観客を飽きさせる危険性をモータースポーツは本質的にはらんでいるのだ。
 ボールを脚で蹴るような、もしくはバットでボールを打ち返すような、本質的な意味での偶発性をモータースポーツに持ち込むことはできないだろうか?それも人為的にではなく、ごく自然な形で実現するには?
ボールを脚で蹴るような、もしくはバットでボールを打ち返すような、本質的な意味での偶発性をモータースポーツに持ち込むことはできないだろうか?それも人為的にではなく、ごく自然な形で実現するには?
いろいろな意見もあるだろうが、私はダウンフォースの削減がいちばんの近道だと考えている。それも、ダウンフォースを現状から20%削減するなどといった手ぬるい方法ではなく、ほぼ完全に排除することが望ましい。理由は簡単で、そうすればコーナリング時の挙動が不安定になるからだ。挙動が不安定になれば技量の差がよりはっきりと出てしまうかもしれないが、どんなに優れた腕前の持ち主でもミスを犯すことはある。ダウンフォースの削減は、そのミスを自然な形で誘発することを可能とするだろう。また、現代のレースで接近戦が難しいのは、前を走る競技車に近づきすぎるとフロントのダウンフォースが減少するためといわれる。こうした弊害も、ダウンフォースを実質的に禁止することで解消が望める。
これを聞いて「せっかくここまで進歩してきたエアロダイナミクスを否定するとは何事か?」と憤る人もいるだろう。ただし、私はエアロダイナミクスを切り捨てろと言っているわけではない。ダウンフォースを削減するかわりにドラッグ(空気抵抗)を徹底的に削るレーシングカー作りをしたらどうかと提案しているのだ。それも立派なエアロダイナミクスの活用であると信じる。「それではストレートスピードが伸びすぎて危険」という指摘には、「だったらエンジンを小排気量にすればいい」と答えたい。ドラッグを削ってエンジンを小排気量化することは、現在の市販車が歩む道と同じである。もちろん、これらはレースを面白くするために考えたことだが、環境問題を声高に唱える向きにとっても受け入れやすい変革であるはず。だったら一石二鳥というものではないか?
ダウンフォースを削減させる方法にも、ひとつ提案がある。従来であればウィングの面積を制限したり、ディフューザーの長さや傾斜に上限を定めるなどしてダウンフォースの量を減らしてきたが、これを続けていくと車両規定がどんどん複雑になり、結果的にレーシングカーの形が似たり寄ったりになりかねない(現代のF1はその好例)。これを防ぐひとつの方策として、サスペンションにかかる荷重でダウンフォースの量を判断・監督することはできないだろうか?具体的には、サスペンションのプッシュロッドに取り付けられているストレインゲージ(ひずみ計)の出力をテレメトリーシステム経由で検出する方法がある。こうすれば走行中のサスペンションにかかる荷重、すなわち車重とダウンフォースの合計を計測できる。F1で実施されているようにECUを共通化すればテレメトリーデータの抽出もより容易になるだろう。
テレメトリーデータでダウンフォースを監視するメリットのひとつは、ボディ形状を規制しなくて済む点にある。実質的にダウンフォースの量を直接、計測するのと同じため、ウィングの面積を規定したり、ボディワークを事細かに定める必要はなくなるからだ。その分、デザイナーにとっては腕のふるい甲斐があると同時に、より多彩なスタイリングが登場する余地が生まれる。
以上の提案は私が個人的に考えたものであり、専門家のアドバイスを受けたわけでもなければ実証が済んでいるわけでもない。ひょっとすると、とんだ勘違いが含まれていて、実現できない可能性もある。けれども、ダウンフォースをばっさり切ると同時に、それに付随する効果(この場合はデザイン上の自由度が増すこと)も狙うくらい大胆な改革でなければ、現状打破は難しいかもしれない。それくらいの危機感を持ったうえでの提案であることをご理解いただければ幸いである。
最終回となる次回は、モータースポーツの振興策をソフト面から考えていくつもりだ。
【編集部より】
本コラムの記事について、みなさまからの声をお聞かせください。
GAZOO編集部“ジミーブログ”にてみなさまのご意見をコメント欄にご自由に書き込みください。

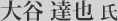
- 1961(昭和36)年9月2日生まれ、48歳。
神奈川県平塚市出身。川崎市在住。
大学卒業後はエンジニアとして電気メーカーの研究所に勤務していたが、29歳にして、かねてより憧れていたCAR GRAPHIC編集部への潜入に成功する。現在は同誌副編集長兼モータースポーツエディター。日本モータースポーツ記者会の会員でもあり、2009年末まで会長を務めていた。