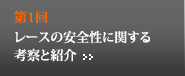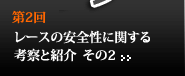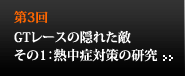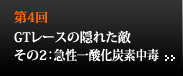![]()
<日本のレース・レスキュー> 日本国内のサーキットのレスキュー体制はほとんど全てがF-1に代表されるフォーミュラー・カーを前提にその体制が考えられており、F-1を手本としたレスキュー体制が日本のサーキットのレスキューの基本となっている。F-1のレスキュー・トレーニングや実戦での出動をみると、フォーミュラー・カーにとっては、ほぼ完璧なレスキュー体制であると思う。しかし、箱型のレース・カーの場合はロールケージに囲まれてドライバーの救出がしにくい事に加えて、まず心配される事は火災の発生である。特に我々が関わっているS-GTでは2007年には全9戦のうち8戦で車両火災の発生を見ている。2008年ではやや少なくなったが、2009年では1レースで3件の火災発生があった事もある。S-GTカーはその構造上、エンジンルームのカプセル化、チューンの程度が高い=高熱化などから出火し易く、また極端に空力を追及されたボディシェルの形状が

初期消火作業という火災発生時の一番大切な作業の妨げになる事もあり、火災発生時、何らかの理由(クラッシュの衝撃や煙を吸った事でドライバーが意識消失、あるいはベルトが外れない、脱出側ドアーの故障あるいは障害物の存在など)で脱出チャンスを失った場合などには深刻な結果を招く事は容易に想像できる。また、負傷者の救出作業中に出火する可能性も高くその対応を考慮する必要がある。また「隠れた敵=熱中症」も大きな問題である。時速200㎞以上で走行する約40台のGT車両のうち1台でも「熱中症」で意識不明になったドライバーが発生したら?その危険性はだれでも容易に想像できることである。本稿では我々が関与しているS-GTのレース・メディカルとレスキュー・システムに関してお話をする。
<サーキットにおける初期救急医療>
自動車レースでのクラッシュによる外傷は「高速度・高エネルギー外傷」である事を常に念頭に置く必要がある。事故現場での救急医療活動及び初期救急医療のポイントは、少ない医療器具、劣悪な負傷者環境の中(例えば、狭いレース車両の中)で、的確な診断と、正確な初期治療=救命処置を素早く行うことである。
現状、あるいはこれまでの方法は、レスキューが到着して、救出、そして負傷したドライバーをとにかくメディカルセンターに運ぼうとする事であった。その基本的発想は「治療はメディカルセンターで」と言う事であり、担当ドクター達もメディカルセンターで「患者が運ばれてくるのを待つ」というスタンスがほとんどであった。これでは、救出から本格的救命治療までに大きなタイムラグが生じてしまう。呼吸停止、あるいは心停止という生命兆候が消えかかっている場合、我々は最初の3分が蘇生のゴールデンタイムと考える。我々が考える初期救急医療の基本は、現場で救命医療を開始すると言う事である。「待つ」のではなく「行く」のである。これは現在のドクター・ヘリの基本概念にも共通するものであるが、ドクター・ヘリのタイムラグが20分~30分程であるのに対してサーキットではそのタイムラグは数十秒から1分である。
次にレース時のクラッシュという場面で、初期救急医療を実践する場合の一般診療との相違点を少し述べる。
現在、一般の救急病院、救命センターに勤務するドクター達は発症、あるいは受傷後メディカル・センターに運び込まれるまで、ある程度時間が経過している(早くても20~30分)状態で患者を診察することがほとんどであるが、災害現場、すなわちサーキットでは初期救急医療に携わるドクター達は全くフレッシュな受傷患者を診察する事になる。
例えば、骨折ならば、まだ患部が腫れ上がっていない状態。あるいは臓器損傷があっても、まだショックに陥っていない状態のごく初期に(ドライバーは場合によってはこんな時でも緊張とクラッシュのショックの為「大丈夫」と言うこともある)少ない医療器材で診察をする事になる、つまり重大な損傷を見逃す可能性は否定できない。我々が常々言っている「ドライバーの[大丈夫]という言葉は信用しないで、しばらく眼を離さないでください」という理由の一つである。
現場に到着し、ドライバーとコンタクトした、しかしドライバーは意識不明、呼吸停止の状態、かすかに脈は触れる、といったような生命兆候が徐々に弱くなっていく時(このような患者はセンターに運びこまれた時には心肺停止状態の状態になっている事が多い)、つまり一刻を争う状況では、聴診器は役立たず(騒音のため)、視診、触診、医師の五感、そして車両の壊れ方、あるいはヘルメットの傷などあらゆる現場の状況を把握して瞬時に大まかな診断を下さなくてはならない。そして直ちに気道確保、輸液ライン確保、あるいは止血といった処置に取り掛かるわけであるが、場合によっては(例えば、ロールバーが変形してドライバーを救出するまでに時間がかかりそうな場合)、車の中でシートに座らせたまま気管挿管、あるいは気管穿刺といった気道確保の処置を行う必要もある。勿論、これらの気道確保、輸液ライン確保、あるいは止血処置と言った処置はほぼ同時に行われなくてはならない事である。
この様な重症例は稀な例であるが、FROドクターはこのような症例にも確実に対応できるスキルが求められる。そして、観客動員数が多いレースでは、これらの現場での救急処置が必ずカメラのレンズに狙われている事も忘れてはならない。
最近、「車が良くなったから重症事故や死亡事故は起きない」という説や思考があるが、本当にそうであろうか?毎年、確実にレース・スピードは上がっている。そして、現在、S-GTをはじめとして世界各国の箱型レース・カーではタイヤのグリップの増大や走行性能アップに対処する為にボディーの剛性はどんどん上がっている。ベース車両に対して、ロールケージやカーボン・コンポジット材での強固な補強、あるいは頑丈なサブフレームなどへの交換、というような大改造を施されているGTカーにおいては、クラッシュ時のドライバーの負傷程度は予想がつかない事もある。
剛性を上げるために、場合によっては、生産車にあるクラッシャブル・ストラクチャー(衝撃吸収ゾーン)部分は追加された「剛性を高める」為の補強材が入っていたり、頑丈なパイプ・フレームに置き換えられたりしている例も見受けられる。したがって、時にはクラッシュしたレース・カーの外見には大した問題は無さそうなのに(その剛性の高さゆえ)ドライバーは逆に強いダメージを負っているというようなこともあり得る。FIAでもS-GTでも「クラッシュ・テスト」は実施されているが、一度クラッシュ・テストに合格すれば、その後、同一車種に対しては行われる事はなく、その後の追加補強に関しては「野放し」では無かろうか(?)と危惧する。残念ながら、我々レース・メディカルにはそのデーターは回っては来ないのが現状である。
車は大丈夫、でもドライバーは脳震盪や脊椎損傷、あるいは「肋骨骨折」に拠る「緊張性血気胸(直ちに胸腔穿刺が必要)」、更に重症になると「心タンポナーデ(心臓を包む膜に血液がたまり、心臓が空回りをする状態=直ちに心嚢穿刺が必要)」などを容易に発症する可能性が高くなる。当然、これらの外傷は素早く、的確な処置が必要なものばかりである。
これまで、数多くあったクラッシュにおいて、ドライバーが死亡するような事故が起こらなかったのは、ただ単に「運が良かった」という事に過ぎなかったのだと思われる。
<レース初期救急医療の実践と問題点>
レース・レスキューに限ったことでなく、救命救急の基本はスピード(時間)、マンパワー(人数ではなく優秀な人材)そしてチームワークである。この行動原理は設備の整ったメディカルセンターにおける医師、パラメディカル達の救命処置の行動原理とレース事故現場での救命救急処置の行動原理に共通するものである。しかしながら、過去日本のレース界ではこれらの対応は各サーキットで対応がまちまちであったことも事実である。
レース・レスキューの場面を考えて見ると、多くのサーキットでは、ドクターカー、ETカー(救出チーム)、ファイヤー・カー等、それぞれ別の車で出動するが、S-GTでは常に火災が背中あわせということを考えると、(1)一流レース・ドライバーが運転するフットワークの良い車に (2)スキルの高いレース・ドクター、 (3)レース・レスキュー、 (4)ファイヤーアタッカーのプロ各1名((3)(4)は兼務でも良い)がチームを組んで乗り込み(良好なチームワークとマンパワー)、それぞれが初期医療、初期消火を担当、しかも数十秒以内に事故現場に駆けつける(スピード)ことが必要と思われる。その為には、レース続行中でもレース・カーに割って入る様なレース・コントロールも必要であり、コース上の安全を前提に走行スピードの遅い不要な車両をできるだけ排除し必要最低限の車両がレースに介入すべきである。また4~5㎞というサーキットのレイアウトでは事故現場への到着時間を可及的に短くするためには最低2台の同様な機能を持つチームの配置が望ましい。また、このチームは、レース中にもかかわらず、レースカーに割って入るいわゆる「特攻」チームであり、レース・ドライバーの次に危険率が高いと言う事も申し上げておかねばならない。それゆえ、これらのレスキュー・チームはエリート集団であり、否、エリート集団でなくてはならないのだ。
この理念は1999年、GTA専属ドクターが誕生した時からあったが(当時はドクターがドライビングとドクターと火消しを担当)それが正式にFRO (First Rescue Operation)Teamとして誕生したのは2002年夏の事である。
<S-GT FROに関して> 我々S-GTでは、FRO-Carを2台用意し、FRO-1の専属ドライバーもドクターも常にS-GTと共に転戦し、約40台の車両の構造や約80人のドライバーの病歴や性格まで熟知、突発事故に対してスタンバイを行っている。またFRO-2に関しては開催サーキットとの良好なコラボレーションを得るべく、車両はGTAからサーキットに提供、ドライバーもドクターもファイヤーも現地スタッフが乗り込み、迅速な対応ができるようにスタンバイしている。

<モータースポーツ・セーフティ>
・Gセンサーに関して:
・DELPHIイヤープラグ内蔵Gセンサー:
INDYシリーズやNASCAR、F-1などではドライバーの頭部が受けた衝撃を直接感知するイヤーピース内蔵のGセンサー(衝撃加速度計)を採用している。これらの衝撃は常にデーターロガーに記録されているが、一定以上の「G」が検知されると無線でレース・コントロールに送信するようになっているものもある。ただし、非常に高価であり、S-GTでは2005年にその導入を諦めた経緯があるが、近未来の導入が望まれる。
これに代わるものとして(もっと安価で)、以下の衝撃センサーを2004年から検証を始め、2006年度から全てのGT車両に取り付けることとした。ただし、これはドライバーの受けた衝撃では無く、あくまで車両の受けた衝撃を感知するものである。
クラッシュ車両の衝撃度の判定は各サーキットのそれぞれのマーシャルレスキュー要員によって、マチマチであり、「医療介入」のポイントさえもばらばらであった。それを解消すべく、各車両のダッシュボード上に衝撃センサーを取り着け、どこのサーキットのマーシャルレスキュー要員にも「医療介入の臨界点」に対して共通した判定ができるようにした。
右の写真は衝撃を感知した状態であるが、赤丸のインジケーターが表示されている。このインジケーターは通常はセンター部に隠れているが、設定された衝撃(S-GTでは17Gを設定=何故17Gのかは別の機会にお話しする)を感知するとその方向に飛び出し、固定される。事故現場で現場マーシャルレスキュー要員がこの赤いインジケターを確認したら、「17G以上の衝撃が車輌に加わった事」、「最大衝撃方向はセンターからインジケーター方向(時計時刻で表現=進行方向正面が12時)であること」を容易に判断、「医療介入」ポイントであると認識し、速やかにタワーに報告させる事とした。
この場合は当然、”Rock’n’ Roll ! = 無線用語で出動!” FROが現場に急行する。
以下次号
【編集部より】
本コラムの記事について、みなさまからの声をお聞かせください。
GAZOO編集部“ジミーブログ”にてみなさまのご意見をコメント欄にご自由に書き込みください。

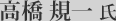
- 1950年3月生まれ 西台整形外科理事長。専門は救急・外傷外科。
1998年までS-GT(当時はJTTC)GT300クラスに参戦。参戦中から「GT専属レース・ドクター」の必要性を訴え続け、1998年シーズン終了とともにGTA専属ドクター。以来GTレースやテストに常に帯同し、GTドライバーの安全対策とレース・メディカルやレース・レスキューシステムなどの統一性の構築などをアピールしてきた。本人はレースから引退したつもりは全く無く、S-GTのシーズンオフには現在でもチームからお誘いがあればDaytona24時間などの長距離レースには時々参戦している。