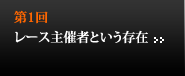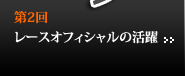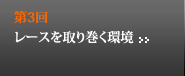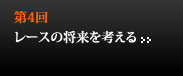![]()
 今回はレースを取り巻く環境についてご紹介します。
今回はレースを取り巻く環境についてご紹介します。
レースを取り巻く環境を大きく分類すると、(1)経済環境、(2)自然環境、
(3)社会環境などが考えられます。
経済環境は、昨年の米国経済破綻に端を発した企業経済の悪化に始まる一連のニュース、及び関連するレース業界への影響で、内容は既に皆様がご承知のとおりです。最近は、レースに参戦していた企業の撤退ばかりがクローズアップされ悪者にされがちですが、ここに至るまで資金を投入し、新技術の開発・供給とドライバー育成でレースを支えてきてくれた事を忘れてはならないと思います。そして私達モータースポーツに関わる人間が最も避けなければならないのは、レースの存在そのものを否定される事です。
自動車による競争=レースの誕生以来100年以上の歴史を経た現在もレースは存在しており、この間に生み出された様々な技術は人々の生活に貢献してきました。
どの時代でも変わらない人間の欲求、即ち、少しでも良い暮らしをしたい、他人より少しでも格好よく見られたい、少しでも良い道具を手に入れたい、という本能は不変です。これをレースに置き換えれば、競争するライバルより性能の良いマシンを作りたい、速く走らせたい、チームは速いドライバーと契約して好成績を残したい…結果、これらを実現する為に資金を必用とし、支援してくれる企業やお金持ちの財布に頼ってきました。いま、スポンサーが自身の経済状況の悪化から意思とは反して撤退を余儀なくされている時に、その財布の中身を当てにして文句を言う訳にはいかないのではないでしょうか。
国内の歴史を振り返ってみると、自動車やタイヤメーカー及び関連する企業がその時代を反映したマシンでレースを牽引してきました。1970年代の石油危機・排気ガス浄化に代表される環境対策を優先するためにメーカーが撤退したあと、主役は誕生して間もないコンストラクターやプライベーターに移りましたが、関係者の努力でレースは形を変えながら消滅する事も無く、その時代に後押しされてヒーローになったエンジニアやドライバーも誕生して現在に至っています。いつの時代も、他人より速く走りたい・走らせたいという欲求が無くなる事はありません。
クルマが単なる生活の道具でしかない存在なら、世界中の全ての自動車と部品メーカーがひとつの図面で同一の製品を作れば驚くほど安価に供給できるかもしれません。しかし、そんな夢や憧れを抱けないクルマなど誰も欲していないのです。
いま、レース関係者の間で交わされる会話は暗い話題ばかりで、ファンの皆様もこの先モータースポーツがどのような道を辿るのか心配されていると思います。私共サーキットは主催者という立場でレースを開催し続ける事でモータースポーツのお役に立ちたいと考えています。
 いま一番関心が高まっている自然環境への配慮ですが、エコという観点からは、排出ガス浄化や低燃費技術がレースを通して磨き上げられてきた事実を改めて主張すべき時が来ています。先日も新聞で「いまやガソリンを無駄遣いするレースは…」との報道が為されるほど、メーカーやチームが如何に少ない燃料(軽量マシン)で走る事が勝利に結びつくかを重要視してマシンを開発し作戦を練っている事すら認知されていません。
いま一番関心が高まっている自然環境への配慮ですが、エコという観点からは、排出ガス浄化や低燃費技術がレースを通して磨き上げられてきた事実を改めて主張すべき時が来ています。先日も新聞で「いまやガソリンを無駄遣いするレースは…」との報道が為されるほど、メーカーやチームが如何に少ない燃料(軽量マシン)で走る事が勝利に結びつくかを重要視してマシンを開発し作戦を練っている事すら認知されていません。
私達のようにレースの世界にどっぷり浸かってしまっていると当たり前すぎて忘れてしまいがちですが、もっと社会にアピールしていかなくてはとの自覚を新たにしています。
社会環境という面では、残念ながらまだまだモータースポーツ自体が社会に認知されていません。いまだに暴走族の集まりだと言う人もいるくらいで、主要メディアもメーカーの撤退や事故の報道の大きさに比べ、前日のレース結果すら探し出すことは困難な状況です。
今こそ社会から離れたところで愛好家だけがレースの面白さに酔いしれていた時代から決別する時です。「こんなに凄いレースを遣っているのに、どうして観に来ないのだろう。」とか、「このままでは先が見えない。」と互いに慰めあっている暇に、自分達でこの世界の未来を切り開かなくてはなりません。レース関係者もファンの皆様ももっと周りの人にモータースポーツの魅力を正しく伝え、サーキットに来られる時にお友達を一人だけでも誘って頂けば、少なくとも現在の倍の人達にレースを観戦して頂くことが出来ます。
 Jリーグが発足した当時、100年構想と銘打って施策を展開し始めたのを横で見ながら、随分と大げさで遠大な計画だなと受け止めていましたが、彼らは地元やメディアの理解を深め、スポンサー企業やサポーター作りからスタートして、彼らより長い歴史を誇るレースはアッと言う間に経済面でもファンの数でも抜き去られてしまいました。
Jリーグが発足した当時、100年構想と銘打って施策を展開し始めたのを横で見ながら、随分と大げさで遠大な計画だなと受け止めていましたが、彼らは地元やメディアの理解を深め、スポンサー企業やサポーター作りからスタートして、彼らより長い歴史を誇るレースはアッと言う間に経済面でもファンの数でも抜き去られてしまいました。
いつまでもそれまでの慣習や規則や組織に縛られる事なく、時代に即したカタチで前進するには、この経済不況もひとつのチャンスかもしれません。いま、モータースポーツに求められている「改革」は、一部の人達で出来る事ではありません。また、大きな痛みも伴うはずです。今まで支えて下さったファンの皆様と関係者がモータースポーツの明るい未来を実現するために何をすべきか、何が出来るか…真剣に議論する時が来ています。
次回はレースの将来について考えます。
【編集部より】
本コラムの記事について、みなさまからの声をお聞かせください。
GAZOO編集部“ジミーブログ”にてみなさまのご意見をコメント欄にご自由に書き込みください。

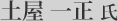
- (株)モビリティランド 取締役 モータースポーツ担当
1950年7月9日、愛知県生まれ。中学生当時65年のホンダF1メキシコGP優勝以来ホンダに憧れ71年にホンダに就職、2輪の営業・宣伝・技術研究所・ワークスチーム、本社モータースポーツ・広報を経験し、98年ツインリンクもてぎに出向。4輪のJOY耐、KARTのK-TAI、2輪のもて耐など参加型イベントを企画推進。
その後、鈴鹿サーキットとの合併を経て現職。
仕事を離れたプライベートでは71年から94年まで休日に鈴鹿サーキットのコースオフィシャルに参画。87年の第1回目から94年までF1でチェッカーフラッグを振った他、81年のシビックワンメイクレース初年度ではドライバーとして参戦。
現在、本職の他にGTA取締役・スーパー耐久運営機構委員長・LSO運営委員長。