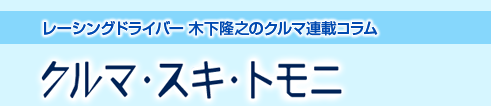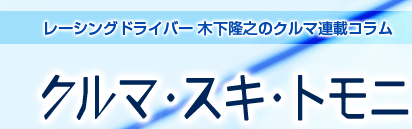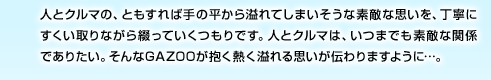


どことなくヘルメットを重たそうにして、佐藤駿介(13)は、買ってもらったばかりの新車のレーシングカートから飛び降りた。
父、佐藤大介(48)がそっと手を伸ばして、小さな体を支えた。
「まだダメ、ちょっと悔しいよ」
幼い顔に、たっぷりの汗が浮かんでいた。走行時間の30分を、一度も休まずに走りつづけたばかりだ。
「ねだるおもちゃはかならずクルマだったし、レースのビデオを擦り切れるほど観ては喜ぶような子供でした。そんな駿介がレーシングドライバーを目指すと言いはじめたのは、はじめてレースに連れて行ったその帰り道のことでしたね」
まだ自転車すら転がせない時から、F1マシンとインディーカーの違いを言当てられるような子供だったし、学校での読書時間では、「野口英雄物語」や「宮沢賢治集」を読む友達の横で、「ドリフト入門」や「セナの写真集」を眺めては、担任を困らせた。
粘土細工時間、みんなが怪獣やロボットを造るそばで、「運転中のレーサー」を丁寧にこしらえていた。
題名は“3速から2速にシフトダウンするお父ちゃん” そのオブジェはいまでも大切に、リビングに飾ってある。
「お気に入りのクルマは?」
「ハチロク」
そう即答するような、ピカピカのクルマ少年なのである。そんな駿介が、元クルマ少年だった父とふたりでカート場に通うようになるのに、そう時間がかかるはずもなかった。いまでは、なんだか仲のいい同級生のようなふたりだ。
カート場には、父に連れられてやってくる子供たちが多い。たいがい息子は将来のF1ドライバーを夢見、父親がそれを支える。
走る息子のために、慣れぬスパナを不器用に捻ってはネジを締めたり、爪をオイルまみれにしてエンジン調整をしたりする。そんな父親は、子供たち以上に嬉しそうだ。
「素人だから、たいしたことはできないんです。だけど、息子にできるかぎりのことはしてやりたい。こんなにクルマ好きに育ってくれたんですからね」
父はそう言って、母親が持たせたおにぎりを美味しそうに頬張る息子を、愛おしく眺めた。
「さあ、これが今日最後の走行時間だぞ。しっかり走ってこい!」
大介がそっと、将来のレーシングドライバーの背を押した。
「ねぇ、来週も走っていい?」
「だーめっ、期末テストだろ?」
ピカピカのヘルメットを小突く。
「じゃ、その次の週ね!」
「成績が上がったら考えるよ」
「下がったら?」
「かあちゃんが、許さないよ」
「じゃ、内緒でこっそり」
「いいから、さっさと走ってこい!」
そう言って、けしかけるようにお尻を叩いた。
駿介がハンドルに手を添えながら、マシンの傍らに立つ。父は、後ろから押し掛ける体制になる。
「せーのっ!」
ふたりが力を合わせ強い力で押すと、エンジンは勢い良く吹け上がり、小さな体を乗せたカートは勢いよくコースに吸い込まれていった。あとには、2サイクル特有のハイピートのサウンドと、甘いオイルの焼ける匂いが残った・・・。

「子供よりも、私の方が楽しんでいるのかもしれないですね」
元気に走りはじめた息子の姿を目で追いながら、父親はそう言って笑った。
大きな夢を抱えた子供たちの、小さなレーシングチームがそこにはあった。クルマ好きの父と息子が抱くその夢は、子供の成長のその先に、まっすぐに力強く延びている・・・。
連載エッセイをはじめます。
街の片隅に転がっているちょっといい話、間抜けな笑える話、GAZOOレーシングの熱く激しい挑戦・・。時には怒ってみたりしながら、人とクルマの、ともすれば手のひらから溢れてしまいそうな思いを丁寧にすくい取りながら、つたない文章で綴っていくつもりです。
「所有する」「走らせる」「語り合う」そんなGAZOOに込められた思いが、人々の心に届くことを祈って・・・。
自分でもどう展開していくのかわかりませんが、それもクルマの魅力のひとつだし、楽しみですよね。
このページに目を通してくれた人達の話題のひとつになれば、幸いです。応援よろしく・・・!