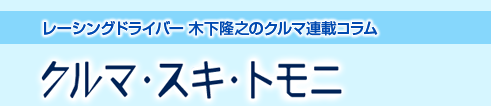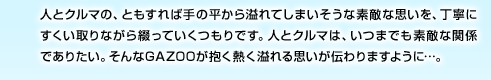


サッカーボールを追いかける子供達。空振りしたり転んだりしながらハシャイでいる。微笑ましく見守る父と母。転がるボールをそっと手渡した。
芝生の上では、デッキチェアに身を沈ませた老夫婦が静かに読書をしていた。
一方で、盛大にバーべキューに盛り上がる若者達。厚切りの牛肉がジュージューと音をたて、アルコールの匂いが漂う。持ち込んだDVDレコーダーのスピーカーから、激しいロックサウンドが轟いている。
小さな女の子が、補助輪をはずした自転車をフラフラと、か細い足でこいでいる。中腰であとを追う父親は、もう汗びっしょりだ。
金曜日の午後7時。サマータイムのドイツの空はまだ明るい。それぞれがそれぞれの楽しみ方で、週末のひとときをエンジョイしていた。
そう、ここは・・・。
公共の公園でもなく、波が打ち寄せる浜辺でもない。人々に解放された歩行者天国でもない。そこは国際格式のレースが開催されるサーキット。 ニュルブルクリンク24時間レースを翌日に控えたサーキットの、”コース上”の一コマなのである。

毎年初夏に開催されるニュルブルクリンク24時間レースには、20万人以上の観客が集まる。一周25kmものコースは森や林で囲まれており、それぞれが仲間や家族、恋人を誘い合いコースサイドに集う。大小さまざまなテントを設営し、アウトドア生活を堪能するのがニュルの伝統的な過ごし方だ。
公開練習や予選といった時間帯はもちろんコースはレーシングマシン専用道となる。爆音を轟かせながら500馬力オーバーのスーパースポーツが疾走する。そこは戦場だ。その時だけは彼らはフェンスの外に引き下がり、ハイスピードで激走するマシンに声援を送る。だが走行が終わればそこはがらりと趣を変える。フェンスの切れ目からコースに踏み入ってきた人達によって、それまでの激しくスリリングな光景がまるで夢か幻であったかのように穏やかな遊び場に変わるのである。サーキットが解放されるというより、それが彼らの庭であるかのように自然に憩いの場となるのだ。
フェンスに腰掛け、若い男女が抱き合っている。恋真っ盛りだ。
本来ならスリックタイヤがかすめる縁石を枕代わりに寝転んで、まどろむ男女もいる。
コース上の夥しい数のペイントは、誰かが描いたものだ。
僕は金曜日のその晩、そこを訪れた。そしてひとりの老紳士に話しかけた。静かに小説に目を落としていた白髪の男性に、だ。
「いつもこうして過ごしているんですか?」
「孫がクルマ好きになってから毎年来ているんだ。息子夫婦と孫達とね。だから20年くらいになるのかな?」
老紳士の回りを、孫達が駆け回っていた。
「いつもここで?」
「この場所が定位置さ。ここではみんなが減速するだろ。クルマがじっくりと観察できるんだよ。」
「どのクルマがごひいきですか?」
「そりゃ、ポルシェだよ。ドイツ最強のスポーツカーだからね」
「僕は#14番のマシンで明日走ります。レクサスも応援してくださいね」
「あのクルマは速い。サウンドもいいね。では応援させてもらうことにする。ただし、ポルシェの次だけどね・・・」
老紳士はそう言って笑った。
僕は手にしていたGAZOORacingオリジナルタオルをプレゼントした。そして握手を交わしてその場を離れた。
「いいレースになるように祈っているよ」
手を振りながら僕を見送る笑顔とその言葉が、強く印象に残った。

僕は翌日、スタートドライバーの大役を仰せつかった。フォーメンションラップの最中、7.7km地点の”メルゲッツフェルツ”のコーナーに差し掛かった時、フェンスの外側に目をやった。昨晩、老紳士と言葉を交わした場所だ。アデナウの森を抜けたあとの左高速コーナーの先に、そのキャンプエリアはある。ドライバーの目線からは正面に拝むことになる。
何かを期待していた。20万人以上の観客のひとり、そう、あの老紳士との小さな再会を望んでいたのだ。
彼は、いた。
目が合った。微笑みながら手を振ってくれていた。GAZOORacingのロゴが鮮やかなタオルを振りかざしてくれていた。僕は小さく、手を挙げた。
僕がどんなデザインのヘルメットで挑んでいるかを彼は知らないはずだ。だがその時は、お互いを確認し合うとするように、視線を重ねたのだ。そして、あきらかにコクピットの中には僕がいるのだと確信したようで、皺だらけの手を精一杯に振ってくれたのだ。僕はパッシングで再会を確認した。
それ以降の周回で僕は、そのコーナーに来るのが楽しみのひとつになっていった。僕らは4名のドライバーで編成されており、ひとりが約7周回を連続して担当する。約4時間ごとに、1スティントで7回、メルゲツッツフェルツにやってくることになるのだ。
スタート直後の興奮がひとまず収まった頃、もう陽は沈みかけていた。フェンスの外に目をやった。ひとりでボーッと見てくれていた。夕食の最中なのだろう。家族は薪を囲み、肉を頬張っているようにみえた。
陽がすっかりと落ち、あたりは真っ暗な深夜になった。薪の火も消えかかろうとしていた。孫達はもうテントの中でスヤスヤと心地いい寝息を立てているのだろうと想像した。
夜が開けた。朝食の時間だ。爽やかな朝の冷気がキャンプサイトを包んでいた。人々が活動を開始しようとしているのがわかった。その時も老紳士はコーヒーカップを手に、僕を見てくれていた。微笑んでいた。
僕はその老紳士がどこからやってきて、どんな人生を歩んできたのかは知らない。名前も知らないのだ。わかっているのは、息子夫婦と孫とのニュル観戦がもう20年になることと、ポルシェが好きだということだけだ。だけど、もう何年もわかり合った間柄のように、心が通じているように思う。

レースが始まると本来ならレーシングコースは、コース上と観戦エリアという鉄のフェンスに隔てられた、交わることのない空間になる。だがニュルにはその常識はあてはまらない。ニュルブルクリンクという空間に集った仲間なのだ。
レース終盤に我々のマシンはトラブルに見舞われ、リタイヤの危機を迎えた。だがメカニックの懸命な作業により見事にコース上に返り咲くことができた。修復を終えたマシンが息を吹き返し、ピット内はメカニックの働きをねぎらう拍手に包まれた。僕も涙した。そこで最初に思ったのは、メカニックの思いがレクサスLF-Aを蘇られたことの感動と、7.7km地点の老紳士に、懸命に走り続ける姿を見ていただくことができるという喜びだったのだ。
「調子良さそうじゃないか・・」
「おかげさまで・・」
「頑張りなさい」
「あなたの好きなポルシェを追っています」
「マシンの調子は大丈夫なのか?」
「快調ですよ。このままの勢いで進めばいいんですが・・・」
「しばらく止まっていたようだね?」
「でも懸命の修復作業で復帰することができました」
「いいサウンドだよ。ここまではっきりと響いていますよ」
「ね、ポルシェより響くでしょ?」
勝手な想像を働かせていただければ、そんな会話が成立していたように思う。
最後のスティントでは、こう語りかけられたのだろうと想像した。
「ニュルは甘くはないだろ? だけど、いい走りだったよ・・」
もし叶うことなら来年またそこで、21年目の観戦となる老紳士との再会を果たしたいと思う。
そこでこう言おうと思う。
「確かに去年のポルシェは速かった。だけど今年のレクサスLF-Aは、そうとうに手強いと思うよ・・」