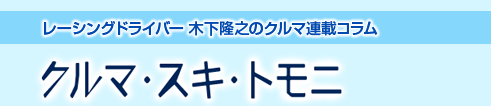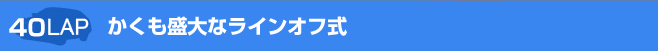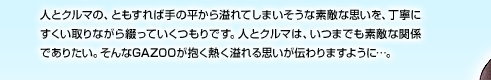

本来は身内だけでとりおこなわれる、ささやかな “誕生を祝う会”である。だが、この日は、完成までに携わった多くの関係者が招待され、ことさら華やかに行われたのだ。
レクサスLFAの『ラインオフ式』のことだ。「ラインオフ」とは、クルマなどの工業品がベルトコンベアの流れから降りることを意味する。転じて、車両が商品として完成すること。
そのモデルが最初にラインオフする瞬間を祝うことを「ラインオフ式」と言う。
もっともそのセレモニーは通常、自らの手でネジを締めたり、緩めたり、ガラスをはめ込んだり、電気の配線をしたり、実際に生産の現場で汗を流した人達だけによって、しめやかに行われる。ラインに向かって作業をしてくれた工員達の労をねぎらうという意味合いが強い。最後は、完成車を取り囲んで記念撮影を“バチリ”。それがいつものパターン。
だが、レクサスLFAの場合は例外のようで、開発総責任者の棚橋晴彦CE(チーフ・エンジニア)はもちろんのこと、豊田章男社長やサプライヤー会社の社長達、あるいは開発の陣頭指揮をとった故成瀬弘氏の奥様、そして末席にはLFAでニュルブルクリンク24時間に参戦した歴代のレーシングドライバーまでが招集され、誕生の瞬間を祝ったのである。
僕にとって、おそらくこれが最初で最後のラインオフ式になるのだろう。
セレモニーは、通常どおり車両組み立てラインのエンドで行われた。
といってもLFAは、まるで工芸品のような手作業で造り込まれる。いわゆる、ロボット溶接がビチビチと電光を瞬かせることもなく、鉄板を打ち叩く金属音が耳をつんざくようなこともない。量産ラインとは趣が異なるのだ。
そこは「LFA工房」と呼ばれる専用のエリアであり、小さな体育館ほどの空間だ。各セクションから運び込まれた夥しい数のパーツが整理棚に整えられ、それをひとつひとつ手で運び、ひとつひとつを手で組みつけていく。70年前のトヨタがそうしていた手法そのままに、レクサスLFAは命を吹き込まれていくのだ。
だから、ベルトコンベアに乗って流れてはこない。見るかぎり、ロボットは1台もなかった。本体は車輪の付いた台車に乗せられ、次々と丁寧に次の行程に手押しされていく。だから普段から、吹きこぼれたオイルの匂いや、塗料の香りはしない。
生産量は1日1台である。
だから、世界500台限定のすべてがラインオフされるまでには、2年近くの日々が必要というから、ラインオフとはいえ、この日が始まりなのである。
手作業であるがゆえに、無機質な金属や樹脂の集合体が次第に形になって行く様子は、工員達が丁寧に魂を植え付けていく作業のように思えた。パーツの1つ1つの組付けは、工員の気持ちと思いと、皮膚の暖かみに委ねられているのだ。それが「LFA工房」。
会の冒頭は、豊田章男社長が真紅に彩られた“シリアルナンバー14”に乗って登場することから始まった。工員達が作る人の列の間を、栄えある完成車が、例の官能的なV10サウンドを響かせてやってくる。そのサウンドでさえかき消されるような拍手に包まれて、だ。
静々と進む完成車のあとを、携わった工員達が見守るように続く。
メインステージに導き終えた社長はまずはマイクを握り、開発に携わった多くの人達に感謝の気持ちを伝えた。
「まるで娘を嫁に出すような心境です。あるいは、子供の誕生に立ち合ったような感動を覚えています。」
工員達にとっても、手を離れる娘を送り出す心境だっただろう。
セレモニー当日には、2009年にともにレースカーのステアリングを握ったH・キュロス氏も遥々コスタリカからやってきており、彼が購入したレクサスLFAが“14号車”。セレモニーを“シリアルナンバー14”に委ねたのは、ゼッケン“14”をちなんでのこと。トヨタの粋なはからいである。
「アリガトウ、トヨタノ、ミナサマ。カンドウシテイマス…」
通訳を通さずに、自らの口で感動を伝えていた。たどたどしい日本語だったけれど、それが彼の思いの強さを語っていた。
彼はコスタリカでトヨタ系販売会社を営んでおり、これから中米での販売サポートを担当する。
「もしこれが世に出なかったら、僕らの努力は空白の12年間になるところでした。だから、支えてくれた人達には本当に感謝します。」
カーボンボディを担当した石川良一グループ長は、ホッとした胸の内をそう言い表してくれた。
企画されたのは12年前。当初はごくささやかな集まりの中で、ほとんど表になることなく粛々と進められていたという。そして開発中断の危機を何度もくぐり抜け、ようやく誕生の日を迎えたのだ。
そんな難産だったLFAの誕生は、彼にとっても喜びなのだろう。
「僕はLFA工房の配属を希望しました。技術と誠意が認められ、ようやくLFAの組み立てラインを担当することになったのです。だから嬉しい。だって僕がこのパーツを組みつけたんですよ。涙ものですよ…」
LFA工房を支える一人の工員は、そう言って喜びを噛み締めた。
そんな思いは、僕も同様だった。開発を進めてきた人達と愛情の熱さが同じだと言ったら彼らに失礼だろう。だが、2007年の暮からLFAのレーシング仕様のステアリングを握り、3度のニュルブルクリンク実践テストをドライバーとして携わってきた僕にとっても、病院の待合室で娘の産声を耳にした時に感じた同様の“感動”と“責任”のような、もしくは嫁ぐ娘を送り出す父親の震えるような“喜び”の心境なのである。
![]()
レーシングドライバーである僕たちは、いまストーブリーグの真っただ中。来年の活動計画をすすめている最中なのである。ちなみに「ストーブリーグ」とは、シーズンオフの冬に、ストーブで暖まりながらファンが噂話をすることからそう呼ばれはじめたという。そんなストーブリーグが終えたあとも、暖かいシーズンを迎えられますように…。祈っていてください!
www.cardome.com/keys/
【編集部より】
本コラムについてのみなさまからの声をお聞かせください。
“ジミーブログ”にてみなさまのご意見、ご感想をコメント欄にご自由に書き込みください。また、今まで寄せられたご意見もご覧ください!