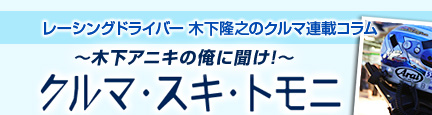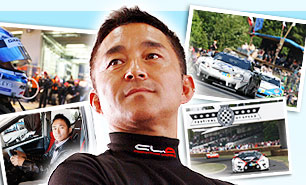
昨年末のことなのだが、ウインターテストのために北海道を訪れて驚いたことがある。さぞかし寒かろうと、厚手のダウンジャケットにスノーブーツ、さらにはミトンのグローブをひとそろい加えた安全防寒で武装していったにもかかわらず、とても暖かいのだ。陽射しは強く、空は青々と晴れわたっていたこともあって、Tシャツにダウンでもしっとりと汗をかくほどのぽかぽか。
だから、雪も少ない。街を貫く幹線道路のところどころには、アスファルトが顔を出していた。スノータイヤでなくてもなんとか目的地にたどり着けそうな、そんな“雪のない雪国”だったのである。
「いやぁ、温暖化っていうやつの仕業でしょうね。これで3月頃になりゃ、もう雪融けなんだから、嬉しいやら寂しいやらで…」
空港から乗ったタクシーの運転手さんは、そう嘆いていた。雪がなければ走りやすい。けれども、雪が観光資源の北海道には雪がないとねぇ…というわけだ。
そんなとき、フッとこんな疑問が浮かんだ。
『スノータイヤはいつ開発しているの?』
サマータイヤなら、春夏秋冬ほとんどの季節で走行テストが可能だ。だが、スノータイヤが雪道を走れる期間は限られている。そこに疑問が芽生えたのだ。

スノータイヤの進化は驚くほどだ。もう雪道など怖くないもんね。チェーン不要。
スパイクタイヤ不要。とてもいい時代になったものです。だからこのところ、4WDの必要性も薄らいだ。雪道だからこそ、FRでドリドリ楽しんじゃいます。
疑問を抱えたら即刻解明しなければ気のすまない性分ゆえ、たまたま携帯にアドレスの残っていたTOYOに迷わず連絡をとった。昨年のこと『GARIT G5』の試乗テストでお世話になった、開発担当者の朝山佳則さんに疑問解明を迫ったのだ。
「たしかにおっしゃるとおりですよ。我々がテストできるのは、1月から3月に限ります。昔は12月からもテストになったんですけれどねぇ…」
なるほどタクシーの運転手さんがいうように、昨今の雪の季節は短いのである。
「じゃ、4月から12月までは暇?」
「いえいえ…、3月までのおよその仕様を決めてからは、その性能解析や生産の準備があります。休んでいるわけじゃないんですよ。『夏、休んでるんとちゃうか?』ってチャカされますけどね(笑)。」
実は、稲穂が色づく2009年秋に発表された『GARIT G5』をボクは、そこから遡ること8ヶ月前の1月、一面白銀に覆われた北海道で試乗テストをしている。それはほぼ完成型とされた。つまり、朝山さんがいうように、その後の8ヶ月間は発売の準備に追われていたのだ。TOYOだけでなく、ほとんどのタイヤメーカーがそんなサイクルで開発をしているらしい。
「スノータイヤの開発は楽だなんて、とんでもない。北海道テストは、夜中なんですよ」
「なぜ夜中?」
「昼間は天候次第で路面コンディションがコロコロと変化します。するとテストしづらい。ですので、路面が安定している夜中に実験をするのです」
スノータイヤ開発の苦労はそこにもある。圧雪路のテストをしようとしても、実験車両が走れば走るほど、路面は変わっていく。ワダチができたり、雪が融けたり…。ドライ路面のように安定しないのだ。だが夜中ならば、それほど変化は敏感ではない。だからテストは夜中なのだ…。
「みなさんと正反対の生活です(汗)」
「日本が夏のときに、雪を求めて南半球のニュージーランドに行くことがあるんですよ」
「真夏に?」
「日本とは逆に、ニュージーランドは真冬のスキーシーズンです。そこで実験テストをするのです」
「スキー、する?」
「仕事ですから…」
Tシャツにタンクトップでにぎあう空港で、防寒具を抱えて飛び立つ気持ちは察して余りある。スキー板も持たずに…。
「みなさんと正反対の生活です(笑)」

もう圧雪路やシャーベット路で苦労することはなくなった。ただ唯一、ピキピキに凍ったアイスバーンだけは気になるもの。タイヤ各メーカーはこのところ、「氷盤性能」に躍起になってますね。だってそれさえ克服すれば、ほとんど無敵なんだから…。

TOYOのスノータイヤをしげしげ眺めると、小さな白いツブツブが確認できます。それが「クルミ」。ひっかき効果というらしいです。なるほどイメージしやすいなぁ。
「ところで、TOYOのスノータイヤには、“クルミ”が配合されてますよねぇ。なんでクルミなの?」
ずっと抱えてきたもうひとつの疑問である。
「クルミの殻を砕いて混ぜることで、氷上グリップが高まるんですよ。それがエッジとなってザイルのように氷をひっかくわけです」
「釘ではダメ?」
「路面を傷めます。ですので我々は“硬いけれど路面よりは柔らかいもの”を探してきました。しかも環境への配慮もあって、削れても害にならない“天然もの”の中でチョイスした結果です」
「クルミでなければダメ?」
「“白熊”も研究しました。氷の上をスタスタと歩きますが…」
「爪と肉球にヒントがありそう…」
「“タコの吸盤”も研究しました」
「吸い付くから?でも生きているからだと…」
「“あめんぼう”も分析しました」
「ありゃ、水の上を滑るんだけど…」
「“ヤモリ”も飼育したそうです」
「壁でもずり落ちない…」
「愛着が沸いたそうですよ」
「でも開発には関係ないし…」
とまあ、長々と話を伺ったのだが、そこで感じたのは、スノータイヤの開発は、大変そうでもあり、楽しそうだということだ。
厳寒の北海道の真夜中に作業を進めたり、真夏に防寒具で旅立ったり、“ヤモリ”をナデナデしたり…。そうしてあのスノーグリップは進化していくのだ。
こんど機会があったら、TOYOスノータイヤをしげしげと見つめてみて欲しい。黒いゴムに混じって、1mm大の小さなツブツブが確認できるはずだ。それが“クルミ”である。そしてこう思うことだろう。“ヤモリ”でなくて良かったと…。
![]()

東日本を襲った未曾有の大地震によって、日本は壊滅的な損害をかぶった。ただし、今回の地震が人類に突き付けた課題は大きく重い。これは天災だったのか?人災ではなかったか?自宅のある横浜市は、毎晩停電になります。電気のない暗闇で思うことがたくさんあります。行方不明の人のこと、被災者のこと、近代文明社会のこと、資本主義のこと・・・。一刻も早い復興を祈っております。(これからの計画停電に備えて、自宅にある懐中電灯とロウソクをかき集めてみました)
www.cardome.com/keys/
【編集部より】
今回から、木下アニキに聞きたいことを大募集いたします。
本コラムの内容に関することはもちろんですが、クルマ・モータースポーツ・カーライフ…等のクルマ情報全般で木下アニキに聞いてみたいことを大募集いたします。“ジミーブログ”にてみなさまのご意見、ご感想をコメント欄にご自由に書き込みください。