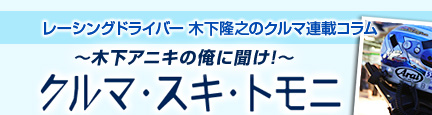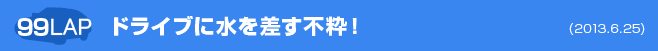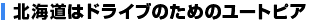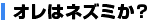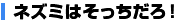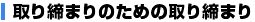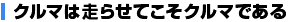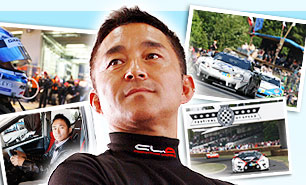
新緑の北海道を走った。
梅雨が明けきらぬ関東から逃れるように足をおろした北の大地は、肌にまとわりつくような湿度とは無縁で心地良い。緑濃い青葉と、乾いた透明の空気が見事にミックスしていた。
広大な大地は北海道でしか味わえない。地平線を拝めるなんて、少なくとも日本では、北海道を訪れたものだけの特権だろう。
その意味では、ドライブ好きにとって日本に残された最後の桃源郷である。本土からやってきたと思われるライダーやドライバーに頻繁にすれ違うのだ。
ただ、そんな爽快感に水を差すような光景を何度も見た。北海道を走ってしばらくは、いかにこの地がドライブに適しているかをこのコラムで熱く語ろうと思っていたのだが、何度もそのイヤな光景を目にしているうちに気が変わった。憤りを覚え、気分は暗く落ち込み、よってこんな刺々しい話題になってしまうことをお許しくだされ。
そう、せっかくの北海道なのに、いまだに私には「不合理と思えるようなネズミ取り(よくこんな言い方をしますが…)」が頻繁に行われているのである。交通安全週間という特殊な事情もある。それはそれで、分かるのだが…。
あまりに不自然だからネズミ取りの一部始終を観察していて驚いた。
前方には小さな村がある。そこでは徐行をうながしたい。だが、村を抜け、民家が消え、その先に伸びやかな直線が開けたその場所で、いきなりの「ネズミ取り」である。
路肩の薮にこっそりと隠れ、ついうっかり速度超過をした餌食を捕獲する。いっそのこと村の入り口に堂々と仁王立ちし、「ネズミ取りだぞ!」と宣言してみてはどうだろうか。
現地の人に聞いたら、こんな答え。
「取り締まりはいつもですか?」
「このところ多いねぇ~。だから地元の人は捕まらないよ」
「観光客がターゲットなんですか?」
「冬場はやらないからねぇ~」
「夏だけ?」
「オマワリも寒がりだからね」
「納得いかないですね」
「雪道で速度出すほうが危険なのにねぇ~」
暖かい陽に誘われたライダーやドライバーがターゲットなのだ。
そもそも、この広大な大地を50km/h規制にすることの意味がわからない。事務所がある横浜のとある商店街は40km/h規制である。とても40km/hで走るのは危険だと思われる道路が40km/h規制なのに、キツネかタヌキさえ気をつければいい北海道の直線路が50km/hであることの矛盾…。
こんなことは、日本では珍しいことではない。
ドイツかぶれを承知で言えば、ドイツにもオービス系の自動速度取り締まり装置がなくはないのだが、たいがいが村の入り口である。そう「ここからは民家がありますので速度超過に注意しましょうね」という案内をも含んでいる。「それを無視するならば危険だから取り締まりますよ」というわけだ。
だが日本は、反則金を徴収しやすい場所に設置する。安全のためではなく収入のためだとの疑念はこんなところから芽生えるのだ。
速度規制のあり方も、ドイツには納得することが多い。民家のない郊外路は、110km/h規制だという。そう、日本の高速道路よりも緩いのだ。
だが一転、村落での速度規制は厳しい。入り口にはオービスもある。村を抜けた直後の直線で取り締まるなんて不粋はしないのである。
横浜の商店街と北海道の大地の速度規制に10km/hしか差がないことをドイツ人が知ったら腰を抜かすに違いない。
ドイツの信号は、「赤→黄→青」もしくは「青→黄→赤」と流れる。常に黄色が挟まる。
日本は、青から赤になる時、つまり停止する場合のみ黄色が挟まり、発進の時にはいきなり赤から青になる。
これは、交通の考え方を明確にあらわしている。ドイツはクルマを走らせようという意識が根底にあり、日本は停めようとする考え方なのだ。それで安全か?かえって流れが悪くなり、危険が増すように感じるのは僕だけだろうか?
日本は自動車産業において先進国だけど、交通の後進国と評されるのはこんな理由もあるのだ。国土は狭いといっても、たとえばドイツなどよりも広い。旧東西ドイツを合算しても、日本の方が広いのだ。
島国の日本には山脈が多く、生活圏は限られている。平野の多いドイツとは事情は異なるものの、そんな日本からクルマを気持ち良く走る場を奪っているのは、行政の責任でもあろう。
このコラムも99Lapsとなった。次号は記念すべき100Lapsである。だというのに、いきなりギスギスした話題になってしまった。
読んで爽快になるコラムを目指していながらこのていたらく、重ね重ね、お許しくだされ。
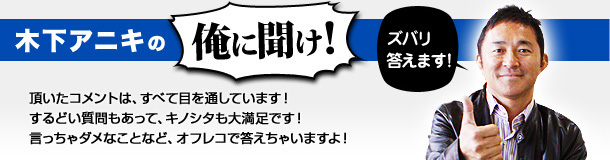

念願の86を購入し、ちょうど納車を待っているので、ぜひご意見をお聞きしたいです。
いまでも慣らし運転は大切だと思う。生産精度が上がり、工場出荷すぐに性能が確保される時代になったとはいえ、機械は機械だから、じっくりと慣らしをした方がいいだろう。
だって、やはり金属と金属が擦れ合うわけで、接点を馴染ませるのに越したことはない。
購入して数百キロまでは、エンジン回転を抑え、ドリフトは控えるほうがいいだろうね。
メーカーによっては慣らし運転不要と公言しているところもあるけれど、たとえばレクサスLFAなどは、購入後数百キロはエンジン回転リミッターが作動するように細工されている。それが慣らし運転の必要性を証明している。あのV10は高精度だという事情もあるけどね。
肝心なのは、しっかりオイル交換をすることだ。細かい金属片が混入しているオイルを入れ替えるまでは、走りは穏やかにするべきだろう。
ただし、慣らしが終ったら、元気に走ってやるべきだ。エンジンを回さないで過ごしていると、回らないエンジンになってしまう…という話もある。走り込んでやると、クルマも元気になるものだ。
ともあれ、慣らし運転は、新車を手にした人のみの特権である。86に愛情を注いで、大切に育ててくださいね。羨ましい!

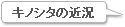
【編集部より】
木下アニキに聞きたいことを大募集いたします。
本コラムの内容に関することはもちろんですが、クルマ・モータースポーツ・カーライフ…等のクルマ情報全般で木下アニキに聞いてみたいことを大募集いたします。“ジミーブログ”にてみなさまのご意見、ご感想をコメント欄にご自由に書き込みください。