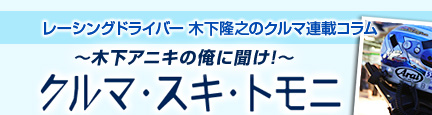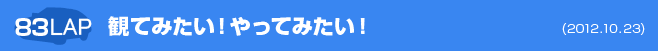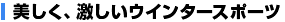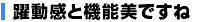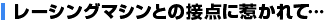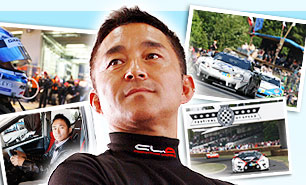
その躍動感は、とても美しかったというべきだろう。
ただ、最初にそれを観た時の印象は、美しさとは別のものだった。そんな美的感覚はしばらくして静かにやってきたものであって、初見ではただただ、強引なまでの迫力や爆発的な力感に気圧されたのだ。
陽光がキラキラと光りの粒を描く雪面を、まるで山々を破壊するような力強さで駆け下りるそれに、思わず体がブルブルと震えたことを思い出す。
僕が初めて「チェアスキー」を観た時のことだ。冬季長野パラリンピックでその競技を実際に目にしたときの感情である。
長野で開催された1998年、どうしても見たかったのがチェアスキーだった。
八方手をつくして入手したこともあり、とてもいい思い出になっている。
それ以来、僕は、ウインタースポーツのひとつであるチェアスキーが気になってしかたがなくなっていった。観客として楽しみたいという素朴な気持ちを超えて、自らチャレンジしてみたいという体験型の思いに変わっていった。まだ経験はしていないけれど…。
チェアスキーの正式名称は「Sit Ski(シットスキー)」というらしい。
その名から想像できるように、体を固定する椅子に、一本のスキー板がつながっている。下肢に障害を持つ選手のため開発された。いわば、車椅子スキー版といった面持ちである。
選手はそのチェアに体を固定し、「アウトリガー」と呼ばれる、小さなスキー板のついたストックでバランスをとりながら滑降する。
滑降といっても、ただ雪の斜面を滑り落ちるという次元などではまったくない。選手はエッジで斜面を刻みながら、絶妙なバランス感覚で駆け下りる。ガシッガシッっと、アイスバーンを切り裂く音がさらに迫力を際立たせる。通常のスキーよりも固まり感があるから力強さは凄まじい。
恐ろしく速い。転倒したら大怪我するぞ、と身を縮めたくなるほどスリリングなのだ。
チェアスキーというマシンと一体になって斜面に挑む様子に惹かれたのは、レーシングドライバーとして、ごくあたりまえの趣向だったかもしれない。
駆け下りる姿だけでなく、僕にとってはその「道具」が興味深く見えたのだ。アルペン選手はドライバーであり、チェアスキーはレーシングマシンとイメージが重なって見えたからなのだろう。
用具は特徴的である。椅子はただ単に体を固定するだけの「椅子」という次元を超え、レーシングカートのバケットシートのような形状をしている。その下部に、数本ものアームが固定され、それが複雑に稼動する。いわばサスペンションアームである。
そしてそのセンターに、モノチューブのショックアブソーバとスプリングがセットされる。
ジャパンパラリンピックのアルペン競技は3種類。回転、大回転、スーパー大回転である。それぞれ、競技の性格によってマシンには違いがある。ラリーマシンとジムカーナマシンの仕様が異なるように、障害の種類によって、体の固定の方法も異なるのである。
競技を離れていえば、2枚板の「バイスキー」や、4枚の板にステアリングがついた「スキーカート」まである。
まさにマシンなのだ。
ここまで機能美を得るまでには、紆余曲折があったという。
古く昔の映像を入手した。すると、ショックアブソーバはなく、ほんとうにただの車椅子にスキーを括り付けたかのようなお粗末なもので、チェアスキーというより、恐る恐る斜面を下るだけの道具だった。
少なからずショックアブソーバの機能に関してはプロである僕にすれば、「もっと減衰力を…」だとか「もっとサスペンションアームを伸ばして…」
なんてツッコミを入れたくなるレベルだった。
さらに振り返って過去の映像をみると、チェアスキーの進化の道筋が見える。かつてこの競技ではドイツ勢が圧倒していた。というのも、あきらかにマシンレベルに差があった。素人が観てもわかるほど、彼らのマシンは安定していた。
一方の、ドイツ以外の選手は、小さなギャップでさえ大きく跳ね飛ばされ、速く滑ることよりも、転倒しないことで精一杯の様子だったのだ。
だが、長野オリンピックを継起に、その道具が目覚ましい進化を遂げた。そこには2輪メーカーやショックアブソーバのサプライヤーの技術が注がれたようだ。ダンパーで有名なカヤバは特に障害者スポーツに貢献しているようで、チェアスキーの足回りを支えている。とても嬉しい話だ。
チェアスキーの技術では、ドイツと日本が世界をリードしている。それも当然のこと、経済的にも恵まれている上に、ともにクルマ先進国としての高度な技術がある。モトクロスの技術などは、そのまま生かされるに違いない。
できればもっと、レースとチェアスキーの技術交流があっていいと思う。世界一のチェアスキー大国になったらもっと嬉しい。
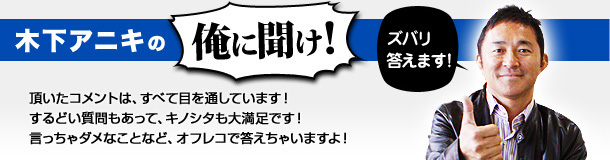

この前、トヨタからEQという電気自動車が発表されました。
今後ハイブリットとEVどちらが増えていくと思いますか?
一度はEVを運転してみたいと思うのですが、木下アニキは電気自動車を運転したことはありますか?
ハイブリットと比べてみるとどんな感じなのでしょうか?ぜひとも教えてほしいです♪
よろしくお願いしま~す♪
近未来でいえば、ハイブリッド隆盛の時代が続くことは間違いない。まだまだハイブリッドは進化の過程にある。環境性能はもっと高まるだろうし、スポーツ性能にも磨きがかかるはずだ。
ただし、EVがジワジワと浸透していくことも間違いない。航続距離や充電時間、あるいはその電気の源が原発であることの嫌悪感が払拭されれば、一気に普及する可能性がある。(その課題克服は困難なのだが…)
日産リーフはもちろんのこと、三菱i-MEiVにもたくさん乗った。リーフのレーシングカーを走らせたこともある。(クルマスキトモニの59LAP参照)
特にリーフのレーシングカーは独特のフィーリングだった。やっぱり内燃機関のほうがレース向きだよね、とは思うけれど、可能性はある。ともあれ、当分、ハイブリッドと内燃機関、そして電気の併用の時代が続くんだろうね。
そのどれが優れているかという議論より、こんなに選択肢があることを喜びたいね。
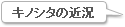
先月、TMG(トヨタモータースポーツGmbH)を訪問した。いまWEC(世界耐久選手権)を戦う総本山である。
もっとも最新マシンのメンテナンス風景を観ることはできなかったが、エントランスにはカーボン剥き出しのF1が展示してあった。これこそが「幻のトヨタF1」である。F1撤退をしなかったら翌年これが走っていたわけだ。
いいもの見ちゃった!
www.cardome.com/keys/
【編集部より】
木下アニキに聞きたいことを大募集いたします。
本コラムの内容に関することはもちろんですが、クルマ・モータースポーツ・カーライフ…等のクルマ情報全般で木下アニキに聞いてみたいことを大募集いたします。“ジミーブログ”にてみなさまのご意見、ご感想をコメント欄にご自由に書き込みください。