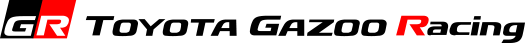324LAP2022.9.22
華麗なる群像劇
F1では、レース中に交わされるリアルなチーム間の交信が、ライブ公開されている。クラッシュやトラブルでの緊迫感が伝わってくる…と。競い合うライバルチームへの抗議や苦言はもちろんのこと、ドライバーと担当エンジニアとの激しい口論も生々しい。F1は完璧なるエンターテインメントである。勝敗を伝えるという報道姿勢を超えて、その裏側に潜む人間模様をも露にするのだ。F1への造詣が深い木下隆之が、その魅力を語る。
スポーツの真相をより深く…
F1のテレビ放送を欠かさず観ることにしている。レースが開催されるウィークエンドは、ソワソワと気持ちが落ち着かない。フリープラクティスが始まる金曜日から、決勝が終わる日曜日まで流れる国際映像が、僕の時間を奪うのだ。
そこまで僕を惹きつけているのは、F1が華麗なる群像劇であるという点だ。生身の人間が抱く感情をはっきりと伝えてくれる。
レースだから、デジタルにマシンの性能やドライバーの力量、あるいは過去の戦績に基づいた歴史や伝説なども興味の対象であることに違いはない、だが、マシンを操っている生きた人間の心の乱れ、チームスタッフの感情の起伏。そんなサーキットで繰り広げられている人間模様を伝えてくれているから面白いのである。
F1ほど冷血非道なカテゴリーも少ないだろう。世界には多くのレーシンクドライバーが存在しているというのに、頂点であるF1ドライバーはほんの一握りである。チーム数を10に制限しているから、世界の中で勝ち上がってきた20名にしか、F1パイロットを名乗る資格は得られないのだ。
努力や実力だけではなく、運と金と、そして政治力が欠かせない。そのあたりのゴダゴダやグジャグシャを、国際映像は遠慮なく報道してしまうから面白い。
スポーツ配信コンテンツ、DAZN(ダゾーン)が放映しているF1インサイドストーリーが刺激的である。
テールエンダーだった「ハースF1チーム」には昨年、潤沢なロシアマネーが注がれていた。ロシアの肥料メーカーである「ウラルカリ」がメインスポンサーにつき、マシンのカラーリングやロゴで圧倒的な支配権を得た。人事にも口を出した。ドライバーにはロシア人のマゼピンを起用させたのだ。
ただ、スポンサーがドライバー人事を契約条件にすることは珍しくはない。ホンダはパワーユニット供給の条件に、日本人ドライバーのシートを確保する。スポンサーは自国民ドライバーの起用を提案する。営利団体である企業はF1を商業的な理由でサポートしているわけで、つまり、宣伝効果を最大限にするには真っ当な手法なのだ。
だが、ハースF1チームが特異だったのは、ウラルカリが指名したマゼピンは、オーナーの実の息子だったのだ。自分の息子のF1の夢を、巨額の札束で購入したのである。全く贅沢な話だが、F1という世界はそういうものである。世界クラスの富裕層の財布で成り立っているのだ。
だからこそ、野次馬的に面白い混乱が起こった。あくまで報道で知る限りの情報に基づいた推察なので、誤りがあるかもしれないことをお許し願いたい。
マゼピンは、けしてF1で通用するほど優秀なドライバーには思えなかった。しかも性格的にはワガママに思えた。チームも彼の態度や言動に苛立ちを感じているようだった。だが父親が持ち込む大金のおかげでチーム運営ができている関係もあり、直接的に彼を責めることができないでいたようだった。
だが、あるレースでの出来事をきっかけに、マグマのように溜め込んでいたマゼピンに対する怒りが爆発。マゼピンもあからさまにチームを批判した。互いに激しい舌戦を展開した。その様子が幼稚だから滑稽なのだ。
あるレースで、最後尾を走るマゼピンがクラッシュした。
「体は大丈夫か?」
チームから負傷を心配する無線が飛ぶ。
そこまでは正常な交信だ。だが、サインガードに陣取る幹部たちはオフマイクでこう口にする。
「ヘタクソ‼︎」
エンジニアたちはうなづきあい、陰口をあびせかける。
「遅っせーくせに、文句ばかり言いやがる」
「本当だよ。とっとと首にしちゃいたいよね」
マゼピンも不満を無線で口にした。
「こんなクソッタレなマシンじゃ走れない」
「いや、シューマッハは君と同じマシンでタイムを出しているんだよ」
チームエンジニアはコンビを組むドライバーと比較した。
「こんなクソッタレマシンしかつくれないんだったら、パパに言ってスポンサーを降りてもらうよ」
駄々をこねる子供のように、あからさまなのである。買ったおもちゃが壊れていたとしても、子供がお店の主人にこうは言えまい…ということを、ロシアの富豪のおぼっちゃまはF1の世界で言っちゃうのである。
「わかった、あとで冷静になって話し合おう」
チームはその場を宥めた。
ピットに戻ってきたマゼピンは、チームクルーと会話をすることもなく、父親に駆け寄った。そして、耳元に口を寄せて小声でこう言ったのだ。
「パパ、このチームダメだよ。お金、取り上げちゃおうよ」
幼稚園児並みである。
実は、こういった会話のやり取りが音声になって放映されている。レース中の無線を通じての会話はオンマイクだが、チームクルーの陰口や親子の会話がオンマイクのはずがない。おそらく高性能な集音マイクか何かで盗聴しているに違いない。
感心するのは、その盗聴かもしれない行為を含めて、F1界で起こったチーム内の確執を晒してしまうことだ。当然、F1のオーガナイザーも公認であろう。
結局のところ、ロシアによるウクライナ侵攻を理由に、ウラルカリのロゴとロシアの国旗をマシンからはがし、ウラルカリとマゼピンとの契約を破棄した。喧嘩別れである。
というような顛末が、ドキュメンタリー構成で編集されている。それが許されているのが、僕がF1群像劇と呼ぶ理由である。
人間にスポットを当てる
レース後、3位までに入賞したドライバーは、ピットロード上でインタビューを受けるのが決まりだ。まだ汗も引いていない。乾いた喉を潤しながら質問に答える場面もある。だからこそのライブ感が興奮を誘う。
トップ3のドライバーは、表彰台裏の控え室で待機する。そこにもカメラが入っている。その場の彼らのやりとりも音声に乗るのである。
「タイヤは何を履いたんだい?」
「ミディアムだったけど、ノーグリップさ」
「そうそう、俺もだよ」
そんなたわいも無い会話からも、ドライバーの人間関係が推察できる。チームメイトなのに目を合わさない。あるいはライバルチームなのに、ドリンクやタオルを手渡すドライバーもいる。数分前まで命をかけてバトルをしていたはずなのに、声を上げて談笑することもある。F1がドライバーの戦いであり、そのドライバーも人間であることが伝わってくる。
日本のマスコミ報道は、そこまで踏み込まない。踏み込めない。チームやドライバーに拒否権があるようで、都合の悪い会話や映像はカットされるからだ。忖度も含まれる。会話はあたりさわりのない平凡なものになる。短期的にはそれは平和に思えるけれど、長期的にはモータースポーツ発展への可能性を狭めることになりかねないと思う。画面の前にいる世界中のモータースポーツファンのハートに響いているとは思えないからだ。
プロスポーツ選手である限り、競技中は公人だと思う。だとしたら、日本のモータースポーツももう少しはオープンであってほしいと願う。
エンターテインメントとして高度に成長したF1にはもはや、ドライバーにも私人としての立場は存在しないのかもしれない。
キノシタの近況
トレーニング代わりにサッカーボールを蹴ることにしている。跳ねるボールへの反応は動体視力の鍛錬になるかもしれないし、走りながら蹴るという複雑な動作は、筋肉の柔軟性を高め、体幹が鍛えられそうだからだ。というのは名目で、緑の人工芝があまりにも鮮やかだったので、ついつい…。