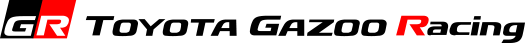354LAP2023.12.20
「ドリフトの芸術性」
東京・台場でD1グランプリ最終戦が開催された。都会のど真ん中というアクセスの良さもあり、多くの観客が熾烈な戦いに酔いしれた。過激なドリフトアングルでコーナーに飛び込むマシンは、派手な白煙をあげながら、常人では不可能な妙技を披露する。心身ともにドリフト好きな木下隆之が想いを語る。
クラシックバレエはスポーツなのか芸術なのか
こう見えても、芸術観劇には並々ならぬ興味がある。
Bunkamuraオーチャードホールで、熊川哲也率いるK-BALLET主催のクラシックバレエを鑑賞したのは一度や二度ではないし、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏を、東京オペラシティコンサートホールで堪能したのだから、実態はぜ〜んぜんなのだが、それだけ聞くと高尚なご趣味の持ち主のようである。
もちろんクラシック系の楽団やバレエスタジオの作品だけではなく、ポップスも観る。DEENの武道館ライブはコロナ禍を例外とすればレギュラーで聴いているし、2024年初頭の中島みゆきコンサートのチケットを応募、抽選結果を心待ちにしているのである。
とはいうものの、芸術を理解しているわけではない。カラオケで熱唱することもあるし、酔った勢いで踊ることもある。つまり、舞台鑑賞をするにはするのだが、酔った勢いの絶叫歌と、足元がおぼつかない千鳥足ダンスである。その程度の芸術センスであり、Bunkamuraだオペラシティだと気取ってみても、目や耳が肥えているわけではない。わかっちゃいないのである。
それでも、クラシックバレエやオーケストラを鑑賞する理由は明快だ。演者や奏者から叱られそうではあるが、そのスポーツ的な要素に興味があるからなのだ。
熊川哲也のダンスはとても躍動的である。およそ重力から解き放たれたように宙を舞う。ジャンプの高さが際立っているのはもちろんのこと、飛んでから着地するまでの滞空時間が長い。0.5倍速で観る動画のようにスローテンポなのだ。
若田光一さんや毛利衛さんたち宇宙飛行士が無重力空間からメッセージを送る時の、宙返りやジャンプに似ている。熊川哲也の浮遊感は、アイザック・ニュートンでさえも説明できないに違いない。
片足を軸にした高速回転は感動的である。和独楽だってこれほど高回転では回るまい、というほどに鮮やかで、かつ中心が1ミリもブレない。
バレエ用語では「フェッテ」という。脳天から足先に、あたかも一本の金属棒が貫いているような状態を表現しているのだ。これを5回転も10回転も途切れることなく続けるのだから、観客席から割れんばかりの拍手が巻き起こるのもうなづける。熊川哲也がフィギュアスケーターだったら、5回転ジャンプも7回転ジャンプもこなしていたであろうと想像させる。
そう、僕がクラシックバレエを鑑賞するのは芸術性を味わうのではなく、熊川哲也のジャンプやターン。つまり、身体的な才能があるからこそ可能な跳躍力や回転力を堪能するためなのだ。つまり、陸上競技を観戦するのと同様のスポーツ性をクラシックバレエに求めているのである。
楽器の演奏に感じるスポーツ性
楽器の演奏は、身体スポーツだと思っている。実はこう見えても中学生3年間は、スポーツ部とブラスバンド部を掛け持ちしており、スポーツ部では主将、ブラスバンド部では部長を務めた。
ブラスバンドだから管楽器が主体なのだが、フルートやクラリネットのような優しい楽器ではなく、弾ける系のユーフォニウムとトランペットを担当していた。
念のために伝えておくと、フルートやクラリネットを演奏するのが簡単で優しい、という意味ではなく、音色がまろやかで優しいという意味。ユーフォニウムはバスなどに比較してまろやかな音色だが、トランペットは進軍ラッパのように勇ましい。
僕がオーケストラのスポーツ性を期待している理由を薄々勘づいてしまったのかもしれないが、つまり、管楽器を吹くにはただならぬ肺活量が必要不可欠であり、それはスポーツ選手のレベルを超えている。
その証拠になるのかわからないが、ブラスバンド部と掛け持ちしていたスポーツ部とは水泳部である。スイミングといえば肺活量が勝負であることに疑いはない。潜水艦のようにバサロ泳法で潜り続けなくとも、息を吸って、息を止めて、息を吐いての繰り返しであるスイミングでも肺活量が試される。つまり僕は、プールで息苦しさに耐え、音楽室でも潜水呼吸をしていたのである。
しかも妙なことに、唇の筋肉が鍛えられる。トランペットにはマウスピースから空気を送り込む。だが、風船を膨らますようにフーッと息を吹き込むのでは音はならない。唇を尖らせつつ、オナラの真似をするようにブーっと振動させる。その振動を楽器に伝えることであのサウンドが響くのだ。
夜空に染み入るような濁りのないノートを響かせていても、奏者の唇はオナラのブーなのである。フーじゃなくてブー。
そうそう、何を伝えたかったのかというと、フーじゃなくてブーっとやっているうちに唇が痺れてくる。そもそも唇には口輪筋という筋肉があり、すぼめたり閉じるときに活用する。これが痺れてくるとブーができなくなる。つまり、音が鳴らない。夜空に染み入るような濁りのないノートどころか、スカースカーっと呼吸が漏れるだけなのだ。
ちなみにその筋肉は加齢と共に衰える。口角が下がってくるのはそのせいだ。その点からも、管楽器演奏はスポーツ性が高いと思える。
日本一のジャズトランペッター日野皓正の、あの頬の膨らみや唇がそれを証明している。
かくかくしかじかの理由により、僕はクラシックバレエ観劇もオーケストラ鑑賞も趣味としているのだが、つまりは、バレエや音楽からスポーツ性を感じているのである。
先日、東京・台場で開催されたD1グランプリ最終戦を観戦した。全10戦で行われるシリーズ戦の締めくくりである。チャンピオン争いは混迷を極めており、上位8名に王者の資格があった。
結果からいえば、チーム・トーヨータイヤ・ドリフトの藤野秀之が第9戦(土曜日)に勝利、第10戦(日曜日)では2位を死守。逆転チャンピオンを獲得したのである。単走でもシリーズチャンピオンに輝いた。チーム・トーヨータイヤ・ドリフトのチームメイト松山北斗は、第10戦に勝利。トーヨータイヤにとっては、史上初めてではないかと思えるほどの完全勝利だった。
ドリフトもモータースポーツの一つである。JAFの規定によると、ジムカーナやダートトライアルと同様スピード競技に分類される。D1の採点要素はスライドアングルと安定性が中心だ。追走で速さが武器にはなるものの、タイム計測はない。
だというのにタイム競技とされているジムカーナやダートトライアルと同じ括りなのは意外だが、その速さを目の当たりにすると確かにスピード競技とされていることも理解できる。その速さには痺れるのである。
だが不思議なことに僕は、ドリフト競技からは芸術性を感じてしまうのだ。車内に搭載したGセンサーから得られるスライドアングルや挙動の安定感が勝敗を左右する審査対象となるが、ビッグパワーの華麗な走り味に酔いしれてしまう。
たとえば、ハイパワーエンジンが奏でる咆哮も僕には欠くべからざる感動の審査対象なのだ。激しくスロットルをオンオフするよりも、ある一定の高回転ノートが抑揚なく響く瞬間に、体の芯がゾワゾワとしてしまう。
ドリフトは瞬間芸の世界である。サーキットレースとは違って、わずか10数秒で演舞が終わる。それでも予選ともいえる単走から追走まで駒を進め、よしんば決勝戦まで勝ち上がると、合計で13回もトライしなければならない。競技としては一日を費やすから、ドライバーの肉体的ストレスはただならぬものがあるのだろうが、トライは瞬間で決まる。その一瞬にかける姿に感動してしまう。
とはいうものの、ドリフト競技はスポーツなのか芸術なのか、深く考察したくなった。
ややかけ足でD1の歴史を振り返ると、「スポーツか芸術か論」の葛藤が理解できる。
かつては完璧な採点競技だった。審査員が感覚で採点、順位を決定していた。それがある種の不協和音を響かせた。審査員の個人的な好き嫌いが点数に影響することから、スポーツ性が著しく欠如してしまったのだ。
その反省から、デジタルに走りを評価する方法に移行していく。いまでは車載したセンサーが、速度やドリフトアングル、あるいはそのドリフトが安定して維持されているかなどの5ポイントを監視している。それをDOSS(D1オリジナルスコアリングシステム)と呼ぶ。主観ではなくデジタルに走りを評価しようというわけだ。
とはいえ、コースを逸脱しているかいないか、チェックポイントを通過しているかいないかは、上空から撮影したドローン映像を審査員が目視で確認する。極端ではないもののそこには、審査員の微妙なサジ加減が介在するように見える。採点競技からデジタル競技への移行期間のように感じるのも事実。
今回のD1最終戦の決勝戦でくつわを並べた藤野秀之と松山北斗は、最後の最後で素晴らしい演技をした。デジタルで評価されるスライドアングルや安定性の評価では、ほぼ満点に近い98点前後を並べたのだ。最終的には202ポイント対200ポイントで決着した。最後の最後で、それぞれがほぼ最高点を叩き出した。得点の内訳にも感動させられたのである。
採点されないクラシックバレエやオーケストラにスポーツ性を感じ、勝負の世界であるD1に芸術性を意識してしまうのは、感覚としてどうかと思うけれど、実際にそうなのだから仕方がない。
ともあれ、どちらも人間の才能なのだ。舞台上でフェッテを舞い続けるバレエダンサーも、最後までむせびなくような高音を奏でるトランペッターも、そして台場で舞った藤野秀之も松山北斗も、身体能力の美しさという点で共通している。
はて、僕はサーキットレースで芸術的な走りができているのだろうか。これからちょっと意識してみることにする。
キノシタの近況
今年最後のサーキットイベントはトーヨータイヤ・ドライビングプレジャー鈴鹿で初めて「プロクセスR888Rドリフト」を履いた。そう、ドリフト用に開発したスペシャルでサーキットを攻めたのである。走行会でトップタイムを叩き出したければ、このタイヤ以外は考えられませんね。