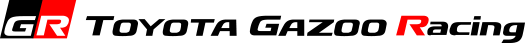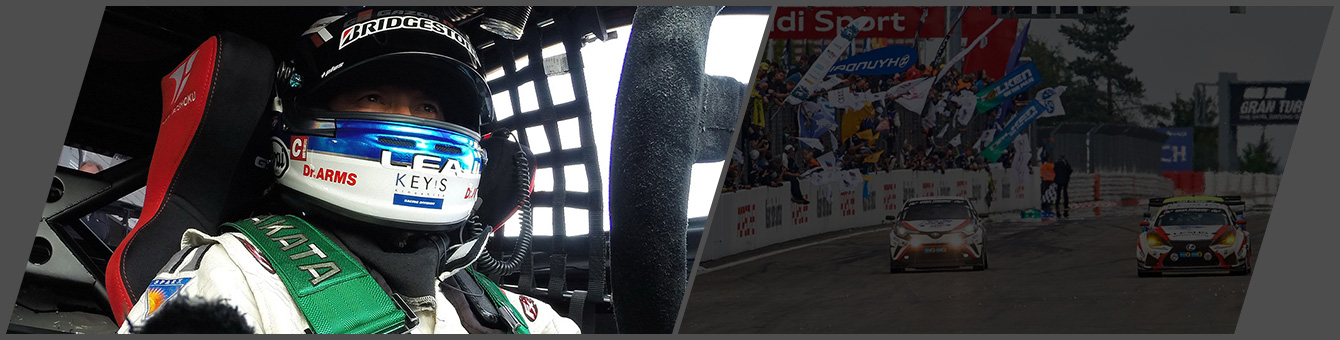「ニュルブルクリンクでの不思議な出逢い」
十数年前のこと、当時僕はBMWで全日本ツーリングカー選手権を戦っていたこともあり、ひょんな誘いによってニュルブルクリンクの市販車開発テストの場に呼ばれていた。
「初めまして、デザイナーの◯◯です」
ずいぶん時が経っているから名前を失念してしまったけれど、優しげな笑みを絶やさぬ背の高い男だった彼との会話の内容は強く記憶している。
「サスペンションデザインを担当ですか?」
「いえ、担当はボディの造形ですよ」
「ボディの造形デザイナーがなぜここに?」
「不自然ですか?」
「日本では、造形デザイナーがサーキットに来ることなどないもので…」
「そうですか、インテリア担当のデザイナーも来てますよ。紹介しましょうか」
その日は市販車開発のサーキットテストの日だったというのに、その場でデザイン担当者と名刺交換をするなど思いもよらなかった。
傍らには数名のテストドライバーがレーシングスーツ姿でミーティングをしていた。大勢のメカニックによって開発車両は走行前のチェックを受けていた。テスト用のタイヤやタイヤ交換用のボンベや、あるいはスパナやジャッキといった数々の工具が並んでいた。いわゆるクルマの操縦性を確認するためのテスト。技術系の関係者が主体のテストだったのだ。というのに、件のデザイナーは、さも当然とばかりに、そのミーティングの輪に加わっていた。そう、BMWにとっては、さも当然のことだったのである。

ニュルブルクリンクの風景の一つでもあるBMWのブリッジ。数えきれない“駆け抜ける歓び”を見つめてきたのだろう。

ROWE Racing のBMW M6 GT3 23号車。総合5位、SP9クラス5位で今年のニュルを駆け抜けた。

Walkenhorst Motorsport powered by Dunlo のBMW M6 GT3 999号車。今年のニュル総合12位、SP9クラス12位。

Walkenhorst Motorsport powered by Dunlo BMW M6 GT3 101号車。今年のニュルは総合22位、SP9クラス18位。
「ドイツ人はクルマを走らせるんですよ」
彼らがこの場にいる必要性を、続く彼の言葉で理解することになる。
「クルマは走ってこそ意義があるものです。走る姿を確認せずに、ボディをデザインできませんよねぇ。なにか不思議ですか?」
「でも、意外に思いました」
「あなたの国では、クルマをリビングに飾るために購入するのですか?ドイツ人は不思議なことに、クルマを走らせる人種なのです」
そう言って、ニヤッと笑った。
「基本的にはスタジオでデザインをします。ですが、走る姿を見なければ、そのデザインがスピード感を演出できているのか、あるいは鈍重なイメージなのか判断できませんよね。だからこうしてサーキットに足を運ぶのです」
その言葉がストンと腹落ちしたのである。
「もっと具体的な話をしましょうか?たとえばフェンダーの隆起だとか、ボンネットのうねりは、クルマの躍動感に関係します。クルマがロールした時に、トレッドが頼りなく見えないだろうか。リアタイヤにたっぷりと荷重が加わっているような力強さが演出できているのだろうか。そんな部分は、スタジオでは確認できません」
デザインの好き嫌いは個人の主観なのかもしれない。だが、BMWというクルマは特に、走らせると力強く感じる。それはデザイナーがコースサイドに足を運んで、造形を確認しているからなのだ。そう確信した。

走る姿を見て、スピード感や力強さを演出。サーキットで造形を確認するという。

フェンダーの隆起、ボンネットのうねりは躍動感に関係するとデザイナーは語る。
「ドライバーは人間なんです」
ボディデザイナーがニュルブルクリンクにやってきて、走る姿を観察することの意味は理解した。だが、インテリアデザイナーまでもがその場に来るのは、どんな理由があるのだろうか。
「ニュルブルクリンクというサーキットは、危険と隣り合わせです。ドライバーの心理的な負担が大きいですね。それは木下さんも実感していることでしょう」
「はい、恐怖感を捨てきれません」
「だからインテリアのデザインが重要なのです」
「いったいどういうことなのでしょうか?」
「もしインパネの片隅に、刃物のような突起物があったらドライバーはどう感じるでしょうか?たとえそれが、手の届かない位置であり、たとえクラッシュしても影響のない場所であってもです」
「心理的に嫌ですよね」
「逆に、強固なボディに守られている感覚をドライバーが抱いていたらどうでしょうか?」
「安心して走れます」
「それが答えです。運転される方は人間です。心理的な影響を受けます。ですから、インパネの造形やAピラーの太さや形状が重要になってくるのです」
「ピラーが太ければ、それはロールケージに守られているような安心感がありますね」
「僕らはテストドライバーの声に耳を傾けます。サスペンションやエンジンを開発しているエンジニア同様にね」
BMWはそうしてドライバーの気持ちに寄り添っているのだ。思わず手を打った。
「もっと言いましょうか?テストドライバーがコクピットに座ってドアを閉じます。その時のズドンと閉じる音などにも気を配ります。その締まり具合でドライバーは安心感を得ます。すると速く走る気になりますし、爽快な気持ちでドライブできるようになるのです」
「ドアの締まり音も、サーキットで検証する?」
「ニュルブルクリンクだからなおさらそれがわかります。実はレーシングカーの開発現場にも足を運ぶことがあるんですよ」
「それは素晴らしい」
「えっ、日本では珍しいのですか?」
目から鱗が落ちた。造形デザイナーはアトリエで筆をふるうだけが領域だと思っていた。だが、テスト走行の現場にやってきて、ドライバーの声に耳を傾けるのだ。そうして走りのクルマができあがっていくのだ。
BMWは官能的なパワーユニットを持ち、前後重量配分に優れたシャシーを持っている。それを武器にBMWが走りの市民権を得ているのだと思っていた。だが本質はそれだけではなかった。デザイナーですらドライバーの気持ちに寄り添うことで、「Freude am Fahren(駆け抜ける歓び)」を構築していたのである。

インパネの造形、Aピラーの太さや形状などにより、ドライバーの安心感と、さらにモチベーションを演出する。

ドライバーの気持ちと寄り添い"歓び"を構築する。
「サーキットでデザインをする」
ニュルブルクリンクで学べること、それは操縦性や動力性能だけではない。ジャンプした直後のハンドリングや高速域でのスタビリティだけではなく、それ以前に、気持ち良くジャンプに挑めるのか、安心して高速コーナーに対峙できるのか、そんな検証ができるのがニュルブルクリンクというサーキットなのだ。
BMWはそれを十数年前からあたりまえのように取り組んでいるのだ。走りのクルマと言うブランドは、長い伝統のもとに手にしたものなのである。
デザイナーが発した最後の言葉 がいまでも記憶に深く残っている。
「僕が手掛けたクルマが一番素敵に見える瞬間は、マシンがアクセルを強く踏み込んでスライドしているときです」
キノシタの近況

今年から復帰したスーパー耐久。名門キャロッセのメインテナンスで激戦区のST4に挑戦している。準備不足がたたって開幕2戦目からの参戦ゆえ、戦闘力アップはこれからといったレベルだが、第三戦ではそれなりに勝負できるところまで熟成が進みつつ ある。ドライバーはラーマン山田と僕と、そして大嶋和也を招聘。なかなか豪華な布陣でしょう? 応援よろしくお願いしますね。
木下 隆之/レーシングドライバー

1983年レース活動開始。全日本ツーリングカー選手権(スカイラインGT-Rほか)、全日本F3選手権、スーパーGT(GT500スープラほか)で優勝多数。スーパー耐久では最多勝記録更新中。海外レースにも参戦経験が豊富で、スパフランコルシャン、シャモニー、1992年から参戦を開始したニュルブルクリンク24時間レースでは、日本人として最多出場、最高位(総合5位)を記録。 一方で、数々の雑誌に寄稿。連載コラムなど多数。ヒューマニズム溢れる独特の文体が好評だ。代表作に、短編小説「ジェイズな奴ら」、ビジネス書「豊田章男の人間力」。テレビや講演会出演も積極的に活動中。日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員。日本ボート・オブ・ザ・イヤー選考委員。「第一回ジュノンボーイグランプリ(ウソ)」
木下隆之オフィシャルサイト >