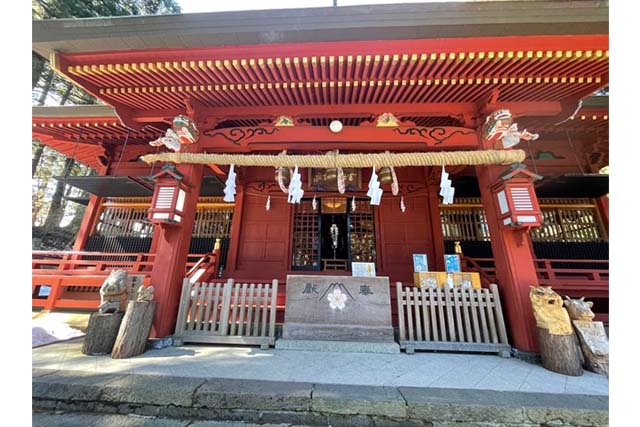311LAP2022.3.9
勝負は正々堂々と…
今年の冬の話題を独占したのは女子カーリングだったと思う。北海道ロコ・ソラーレが接戦に次ぐ接戦を展開。常に笑顔で互いに声を掛け合う姿は微笑ましかった。そして、このカーリングという競技、ライバルにダダ漏れであることを構うことなく、戦略を検討しあう。これって、新しいスポーツの姿ではないかと木下隆之が語る。
珍妙なスポーツ
いやはや、珍妙なスポーツがあるもんだね。そういって、カーリングをちょっとネタにしていた時期もある。僕が高校生の頃だった。
スキッパーが投じた20kgのストーンの前を、ホウキのようなブラシで激しく氷を掃く。次第にそれがスイープと呼ばれるテクニックで、ストーンの勢いを強めたり弱めたり、あるいはカーブやシュートが可能だというのは後々に知ることになったのだが…、無知で稚拙な高校生だった僕はその技が理解できなかった。
「珍妙なスポーツがあるもんだね」
友達とそう笑い合った。時のテレビではアニメの天才バカボンが大ヒットしていた。掃除の時間はカーリングを真似たりしていたのである。
今、そんなことをすれば炎上しかねない(笑)。まして、スイープを廊下掃除と重ねてしまうなどは言語道断。冬の話題を独占した北海道ロコ・ソラーレは日本国民のアイドルでありスーパースターなのである。この文章が誰の目にもとまらないことを祈る。
ほかにも、ちょっと珍しいスポーツに「カバディ」がある。この原稿を書くにあたって、YouTubeやウィキペディアで学習したところ、インドの国技だという。バレーボールサイズのコートで敵味方に分かれ、相手の体にタッチして自陣に戻るという競技。いわば鬼ごっこである。特徴的なのは、攻撃中には常に「カバディ・カバディ」と叫び続ける必要があることだ。息が切れたら得点にはならない。肺活量も求められるようで、なるほど過酷な身体競技。立派なスポーツだ。
ちなみに、「カバディ」に特別な意味はないそうだ。そこが珍妙である。
セパタクローも同様に滑稽だ。バドミントンサイズのコートでボールを蹴り合い、ボールを床に落としたら失点。相手のコートにシュートする。バレーボールのサッカー版であり、サッカーのバレーボールでもある。何を好き好んで足でバレーボールをしなければならないのか理由は定かではないが、見ていてちょっと微笑ましい。
だが、この原稿を書くためにセパタクローを観戦するうちに、競技の楽しさに気づく。足でネット越しにスパイクするわけだから、床運動の選手のような驚異的な跳躍力が求められる。アクロバティックな妙技に目が釘付けになった。
作戦ダダ漏れですが…
話を戻す。カーリングである。
僕がつくづく不思議に思うのは、戦略が筒抜けになることを厭わないという点だ。一投ごとに攻守が入れ替わるのだが、次のストーンを投げるまでの1分間に戦略を話し合う。
「ここに投げたらどう?」
ブラシをくるりと逆に持ち替えて、その柄の先で目標のポイントを指し示す。
「そだね〜」
「ここに置くと、相手に弾き出されない?」
「そだね〜」
シートと呼ばれるカーリング専用のリンクは長さ45.7m。声を張らないとあっちには言葉が届かない。敵の頭越しに声を響かせるのである。
氷上のチェスと言われるほど、戦略性が要求される。ただ敵のストーンを弾き出せばいいのではなく、わざと負けて次の回で有利な後攻を確保するなどといった、肉を切らせて骨を断つ作戦の応酬である。だというのに、作戦バレバレ覚悟で相談し合うのだ。
五輪は海外戦だから、日本語の意味はわかるまいとは思うけれど、青い目をしていて日本語堪能だったらどうするの? だったり、国際試合なんだから通訳を忍ばせることも容易に考えられるわけで、「そだね〜」というたびに、作戦が筒抜けにならないものかとドキドキしてしまうのである。
まっ、隠したってバレる、なのだろう。もしくは隠すほどの裏技ではないのかもしれない。あるいは、敵の裏をかくほど浅ましくはないのかもしれない。
日本古来の武道である剣道には、武士の思想が根付いている。コテ、メン、ドーの3種類しかターゲットがない。コテは小手である。メンは面である。ドーはもちろん胴である。喉元を突き刺す「ツキ」というのも技の一つだが、失敗すると危険であることから大人だけに許された技だ。アシー、とか、カター、といった技はない。
しかも、自分が狙ったターゲットを宣言しなければならないのである。小手を打つ瞬間に「コテー」と叫ぶ。腹を切り抜くには「ドー」である。竹刀を上段に振り上げて、「メン〜」なんて叫びながら腹を抜くなんてことは、武士の風上にもおけぬという理由で禁止なのである。正々堂々が剣道の思想なのだ。
ただし、滑舌良く「メン」「ドー」「コテ」と発音することは滅多にない。「ヤー」だったり「ウチョ〜」とか、ほとんど奇声である。したがって、剣道の試合会場には、大人の叫び声が鳴り響く。時にはそれが、切られた武士の断末魔に聞こえなくもない。
幼少の頃、気がついたら剣道を始めていた。だからこれが珍妙だと気づく前に常識になってしまっていた。改めて思えば、敵に狙いを宣告して竹刀を打ち込むのだから、どこかカーリングに似ている。という論法で言えば、カーリングにも武士道の精神が息づいているのかもしれない。
極秘テクノロジー
その点でモータースポーツは、隠し事の山である。特にF1のように高度なテクノロジーの集合体ならばなおのことだ。今年はF1も変革期を迎えている。タイヤが13インチから18インチに変更される。13から14じゃなく13から18というのだから、マシンのデザインが大幅に変わる。シーブンオフ中に、デザイン室でペンを走らせたデザイナーの手腕が問われるのである。公開テストだから公開するはずなのに、走行を終えると一目散にピットに駆け込み、シャッターが閉じられる。盗み見るなぁ〜である。
それほどの極秘技術の集合体であるだけに、コースアウトしようものなら晒し者である。サスペンションがもげてクレーンで宙吊りにされようものなら、デザイナーは顔面蒼白だ。宙吊りにされたマシンは風を受けてあられもない姿を晒す。クルクルとターンテーブルで舞うダンサーのように360度から衆目の的だ。そればかりか、高々と吊り上げられれば、普通では絶対に拝めないはずの腹や尻まで丸見えである。映像カメラマンがそんな決定的シーンを見過ごすはずもなく、電波に乗せて世界中に配信してしまうのである。
駆けつけたメカニックがマシンを毛布で覆うまでは、極秘機密も白日の元にさらされる。慌てて毛布で包んでも、もう遅い。
カーリングが戦略を晒してしまうのとは対象的に、レースではナイショなことが多い。最近のF1ではチーム間無線が公開されているから、およその作戦を想像することができる。ただし、配信部隊は時間差を設けている。いま聞いてももう遅いよね、というタイミングで流しているようだ。
まして、プランBだとかプランCだとか、暗号めいているからはっきりと認識することができない。
「このタイヤはまったくダメだ」
なんて無線交信しながら、トップタイムを連発するのはL・ハミルトンのお家芸である。
無線がライバル陣営に流れていることを承知で、ガセネタを流しているわけである。
ハミルトンには、カーリングの世界は奇異に映ることだろう。
ただし、それがモータースポーツの面白さでもある。カーリングが氷上のチェスだと呼ばれてはいるものの、本物のチェスが戦略をバレバレにしているとは聞いたことがない。やはり腹の中に仕舞い込んで、意表を突いているのかもしれない。
「そだね〜」の意味は実は、「ダメよ〜」だったりするのかもしれない。
「そだね〜」にも癒されるけれど「このタイヤはまったくダメだ」というバレバレのウソにもドキドキする。
キノシタの近況
今年のニュルブルクリンク24時間参戦に向けて、クラウドファンディングで協力を募ることにしました。コロナ禍で遠征を中断していましたが、今年は再挑戦することにしました。応援よろしくお願いします。