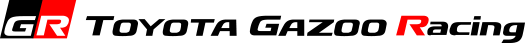318LAP2022.6.22
近代的レース戦略?
ニュルブルクリンク24時間レースから帰国したその足で富士24時間レースに挑んだ木下隆之は、チーム戦略を無視して攻撃的なドライビングに挑んだ。それはわがままな走りではなく、きわめて理論的な近代的レーススタイルだったのだ。
ひたすら攻撃的なドライビングが求められた
今月初頭は、ニュルブルクリンク24時間からその足で富士24時間に突入するというスケジュールだった。つまり、僕の思考と肉体はニュルブルクリンクと御殿場の区別がつかず、しかも、操るマシンはBMW・M2CSレーシングという点で共通している。日独でBMW.A.Gがカスタマー仕様として開発した、いわばワークスカーをドライブしたのである。
さすがBMWだけのことはあり、国内では散々乗り回し、もはや身体の一部と化すほど馴染んだマシンは、ドイツの名門シューベルト・モータースポーツのマシンに乗り換えても1ミリもフィーリングに違いがない。現地でのコクピットドリルはあっけなく終わった。さすがに耐久レース巧者ゆえに、勝つための細工に違いはあるものの、説明を受ける必要もなく終了。違いがあるとすれば、国内のマシンはToto BMWが販売しているということ、ドイツのマシンはシューベルト・モータースポーツが購入したものという違いでしかない。後はカラーリングだけ、というほどに品質に違いはなかった。
ただし、日独のレーススタイルの違いは明確である。攻撃的なレーススタイルでなければ勝ち抜けないニュルブルクリンク24時間では、ドライバーは常にフルプッシュ。マシンを労われだの温存しろなどと指示されることはない。
「ブレーキパッドは15時間で交換します」
「給油のためのピットストップは6周ごとです」
現地のチーフエンジニアが明確にスケジュールを伝える。
そこで僕は手をあげた。
「ブレーキパッドの温存や、燃費走行をする必要はありますか?」
「いえ、パッドは15時間で交換すると申し上げました。ですからフルプッシュでも構いません。燃料をどう節約しても、7周には延びません。全開走行でいいのです」
スタート前のチームミーティングはこんな雰囲気なのだ。マシンのデータを完璧に把握している。壊れることはないとの絶対的な自信を感じた。
さすが「ニュルブルクリンク24時間スプリントレース」を思わせる戦略である。
そのスタイルを国内で再現してみたら…
そんな攻撃的なスタイルのシューベルト・モータースポーツでクラス優勝をしてしまったものだから、帰国したその足で挑んだ富士24時間レースで、ドイツかぶれが抜けきらなかったのも納得していただきたい。
我々BMW Team Studieのドライバーオーダーは、こう決められていた。ニュルブルクリンク帰りで漆黒のノルドシュライフェに慣れているキノシタは夜中担当…とレースが組み立てられていた。雨が降ったら、場合によってはキノシタを行かせるかもしれないとの話もあった。つまり、悪条件要員である。ドライバーは5名である。だというのに、62歳の僕を夜中に走らせるとは、チーム監督もなかなか攻撃的なスタイルを貫くものだと一瞬たじろいだのだが、言ってみれば信頼の裏返しである。名誉な指示でもある。喜んで引き受けたのである。
ただし、歳を重ねるとわがままになるって話はどうやら本当のようだ。しかもニュルブルクリンク帰国直後でありニュルブルクリンクかぶれである。チームの指示はブレーキパッドを温存して走るようにとされていたのだが、夜中に回ってきた僕のスティントで全開走行を敢行。ドライバー間の口約束を無視してフルプッシュしてしまったのだ。頭では緩めろと神経伝達系に指示していても、右足がそれを受け付けない。予選タイムと同等のラップで周回したのである。
慌てたのはピットである。定められた2スティントをそつなくこなしヘルメットを脱ぐと、チームメイトが口々に僕にこう言った。
「お疲れ様でした。暴走列車様」
「いいタイムでした、トーマス君」
どうやらトーマス君とは、アニメの暴走列車からの命名とのこと。ブレーキパッド温存作戦を無視してタイムを刻み続ける僕に対する“イヤミ”なのである。
チームメイトの表情には笑みが浮かんでいるから、てっきり褒められるのかと思ったら、チーム作戦を無視しての暴走ぶりを揶揄したというわけである。
チーム監督も諦め顔でこう言った。
「アニキはニュルブルクリンク帰りだから、全開しかできない身体になっちゃったんだよ」
これが、暴走した僕への叱咤なのか、ダチョウ倶楽部ならぬ「押すなよ押すなよ」なのかは不明だが、僕は好意的に後者と解釈したのである。
きわめて理論的な戦略でもある
言い訳をするならば、昨年のレースではブレーキパッドを温存しすぎた結果、余力を残してゴールを迎えてしまった。体力の全てを絞り出し、最後の1滴まで力を使い果たしてゴールすることこそが完璧な戦略でありレースの勝ち方だと信じているからこそ、どこか燃え尽きずにゴールしてしまったモヤモヤが残った。だからチームは昨年の反省から、ややペースを上げることにした。それを実践したにすぎないのである。
ブレーキパッド担当者は、スタート前にこう言った。
「12時間を超えて1度パッド交換をします。場合によっては2度の交換になるかもしれません」
この意味が理解できなかった。スタートして半分の12時間もパッドが持つのだったら、1回の交換で24時間を走り切れるはず。ならばベテラン木下隆之が、パッドをギリギリまで使いきってしまおうと考えるのも道理であろう。
歳を重ねると頑固になる。言い訳も上手である。屁理屈も熟練のレベル。しかも、ベテランならではの技で、スタートしてしばらくすると、そのマシンが壊れるのか最後まで持ち堪えるのかがおよそ経験的に判断できるのだ。
20年前ほどのスーパー耐久はとにかくマシンの耐久性がなく、パッド交換も3度や4度ではなく、途中でオイル交換を強いられるような時代だった。ゴール間際は満身創痍。足をひきずりながらのゴールだった。という時代を経験していると、マシンの劣化状態は手に取るようにわかる。しかもニュルブルクリンクかぶれである。難攻不落のノルドシュライフェから帰国直後の僕の右足は、そう簡単に緩まないのである。
さらに、である。歳をとると、ああ言えばこう言うようになる
「俺様は全開で走る。その分を君たちが温存したまえ‼︎」
暴走列車と揶揄するチームメイトに向かって、そう啖呵を切ってしまう。
いわば、開き直りである
そしてその瞬間にピピンと閃いてしまったことがある。近代的レース戦略を、である。
思い起こせば耐久レースは、チームメイトがこぞってマシンを温存し、完調な状態でタスキを渡すのがセオリーとされてきた。だが、他のプロスポーツと比較すれば不自然である。例えばプロ野球には、先発がいてリリーフ陣がいる。最後の1イニングだけを担当する抑えのエースがいる。そのシステムが整っているチームが勝利するのだ。
先発ピッチャーは、自慢の速球を投げ続ける。大谷翔平しかり佐々木朗希しかり、飛ばすだけ飛ばして相手打線に捕まったらリリーフ陣にすべてを託す。だから大魔神佐々木がスターになり、高津臣吾がファイアマン賞を3度も獲得する。これが近代的な野球である。先発ピッチャーが完投を目指す時代ではないのだ。
野手でも同様に、ホームランバッターがバットを満振りする一方で、送りバントの名手が称賛される。箱根駅伝しかり、山の神がいて花の2区を飾るエースがいる。
近代的スポーツは役割分担なのだ。だがレースでは、ホームランバッターを揃えたがる。「4番バッターを揃えても勝てない」は野球の世界では常識であるにもかかわらずだ。という意味で言えば、攻撃的なドライビングで飛ばすドライバーがおり、マシンを温存するドライバーを組み合わせる。それこそチームワーク。理想的な近代的レース戦略だと思うのだ。
幸いチームメイトは、ブレーキパッドの温存も巧みだし、燃費もいい。それでもラップタイムを落とさない。レース巧者が揃っている。近代的レース戦略を成立させる駒が揃っているのである。ニュルブルクリンクで開眼してしまったのだ。新たなレーススタイルがアイデアとして浮かんだ。年齢を重ねると知恵を授かるものである。
とはいうものの、基本的にはチームの指示を守るのが基本である。その意味で言えば、我がBMW Team Studieは理想的なチームといえる。ドイツ帰りの還暦ドライバーのわがままと屁理屈を笑いながら、チームメイトは温存走行に徹してくれた。最後はトラブルを抱えたマシンをゴールまで導いてくれた。優秀なリリーフ陣が揃っている証だ。
もっとも、年齢を重ねると知恵を授かるだけではなく、ともすればドライバー生命を脅かしかねない内容を、シャアシャアと記事に綴ってしまうハートの強さをも備える。そんなわがままドライバーは使えないなぁと誤解されるのを覚悟で、自ら口を割ってしまうのである。
実は後日、チーム監督からメールが届いた。
「ギリギリでしたね」
そこには、クラックが入り破壊寸前のブレーキローターの写真が添えられていた。
それを目にしたわがままな還暦ドライバーは、こう感じたのである。
「マシンの性能をギリギリで使い果たしてゴールさせるなんて、吾輩のテクニックもまだまだ通用するわい」と。
ともあれ、ニュルブルクリンク帰りのわがままな還暦ドライバーを受け入れてくれるチームに感謝したい。そして、近代的レース戦略の正当性を証明してくれたチームメイトに頭が上がらない。というわけで、次は僕がリリーフをする番かもしれない。
キノシタの近況
クラウドファンディングを利用して叶ったニュルブルクリンク24時間参戦なのだが、支援者への恩返しの準備を始めています。現地で購入したお土産の整理も進めなければならない。一つひとつ丁寧に思い出を噛み締めながら梱包しています。
写真 WATARU TAMURA
alexandertrienitz