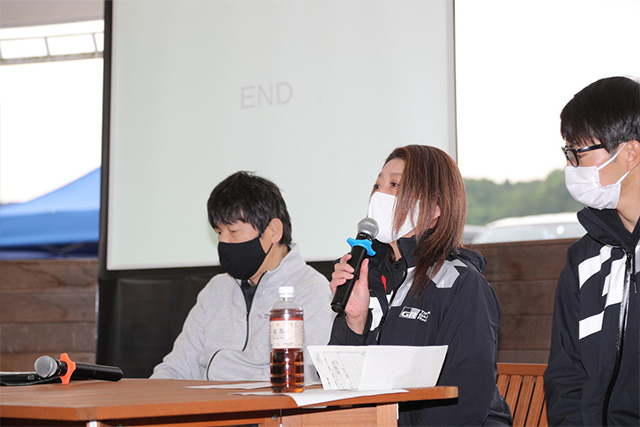333LAP2023.02.08
サーキットデビューのススメ
かつてはハードルの高かったサーキット走行も、いまでは身近な存在である。サーキット走行会も珍しくはないし、その気になればすぐにレースに参加することができる。かつて10円玉を握りしめてレース界の扉をこじ開けた木下隆之が、レースデビューを誘う。
ヒエラルキーの底辺から…
僕が初めて挑んだレースは「富士フレッシュマンシリーズ」。富士スピードウェイをステージに、たしか全7戦のシリーズ戦だった。
マシンの改造範囲は厳しく制限され、基本的にはノーマルパーツで構成される。ロールケージやバケットシートなど、安全装備を組み込んだだけのいわばアマチュアの入門カテゴリーで、参戦経費も抑えられていた。
参戦クラスはたくさん用意されていた。僕がデビューレースとして選んだのは、もっとも安価な「P1300」。プロダクション1300の略であり、排気量は1300cc以下。実質的にはKP61型スターレットのワンメイク状態だった。
排気量別に「P1600」、「P188」、たしか「P2000」だとか「P2500」だとかに区分されていたように記憶している。パルサーやAE86が、それぞれのクラスで走る。最速は、スカイラインRSターボのクラス。その中でもっとも遅く、もっとも経費のかからないクラスがP1300だったわけだ。
早朝から夕方までに、スタートからゴールまで10周のスプリントレースが次々に開催される。
参加台数は多かった。富士スピードウェイで出走可能な40台のグリッドは、つねに埋まっていた。予選は大混乱で、タイミングをしくじると、満足なクリアラップは得られない。しかもスリップストリームの使い方がタイムに影響するという都合で、多くのマシンが団子状態でストレートを疾走する。ビギナー参戦用のアマチュアカテゴリーとはいえ、たいそう盛り上がっていたのだ。
決してポピュラーなスポーツではなかったけれど…
当時のサーキットレースは、いまほど身近な存在ではなかった。ライセンスをどこで取得していいのかすらわからず、マシンをどこで借りていいのかもわからない。
だから、マシンレンタルが可能なのか否か、そもそもそんなシステムが存在しているかすら曖昧だった。
当時僕は大手出版社に勤務していた。月刊自動車専門誌「ル・ボラン」編集部に配属されていた。つまり、ゴリゴリの自動車業界であり、誌面にはレース結果などが掲載されていた。モータースポーツ担当はサーキットで取材していたはずだ。立場上、僕はまったくの門外漢ではない。それでもレースに参戦する仕組みがわからない。
しかも、である。中嶋悟さんがF1参戦を前にしていた頃であり、本人にたびたび雑誌の企画で試乗をしていただいていた。さらに言うと中嶋悟さんがF1に進出するときのマネージャーは、ル・ボラン編集部員だった。試乗をしていただいている間に関係ができた。というほどに僕は業界関係者であった。それほど深い結びつきがありながら、レース参戦の方法がわからない。かといって、F1ドライバーである中嶋悟さんに、ライセンスの取得方法をお聞きするのもはばかれた。
それでも猪突猛進でレース界の扉を開こうともがいた。
まず門を叩いたのは、東名自動車(現・東名パワード)である。
テレビ放映されていた「富士グラチャン」で見た東名自動車所属の高橋健二選手が速く、何も考えずに電話ボックスに飛び込んだ。そこに備えてあった分厚い電話帳からたどり着いた東名自動車に直談判、するとたまたま、趣味でレースをしていたメカニックが所有するKP61スターレットを貸してくれることになった。そう、日産系列のレーシングチームとコンタクトをとったらトヨタ車が出てきた…というわけである。アライアンス意識が厳格な現在と違って、社会が優しかったのである。
素人感丸出しのデビュー戦
デビューレースのラップタイムを、いまでもはっきりと記憶している。
初めて走る金曜日の練習走行は2分13秒がベストタイムだった。翌土曜日がいきなり予選であり、多くのマシンに混じって走っていたら2分9秒。一夜明けたら一気に4秒もタイムを短縮してしまったというのだから、いかにもアマチュアあるあるである。それでも予選は24番グリッド。スタートシグナルははるか遠くに霞の中に見えるだけだから、他のマシンが動いたらそれに合わせてスタートするといった牧歌的な感じである。
それでも不思議なことに、前のマシンを抜きたい一心でブレーキングを遅らせたりイン側にノーズを突っ込んだり遊んでいたら、ラップタイムは2分7秒まで短縮。気がつけば表彰台に立っていたというのだから、アマチュアの伸びしろとは恐ろしい。
もちろん、スリップストリームを巧みに使ったから…などという頭脳的な作戦が功を奏したわけではなく、ただ単にライバルの後ろについていったら、そこがベストな走行ラインだった、といったレベル。ライバルを抜こうとしたら、ブレーキングポイントが判明したということだ。つまり、つられてタイムが出ちゃったのである。
草野球のピッチャーが、いきなり140km/hが出たってことはないだろうが、レース界にはうっかりな偶然があるのだ。それが市井の青年を錯覚させた。挙句の姿が今の木下隆之である。
やはり資金的には厳しい世界だった
もっとも当時の僕は、プロドライバーになろうなどとは夢にも思っていなかった。というのも、デビュー戦だけで30万円が消えていった。マシンのレンタルと走行代金に札束が消えていく。レーシングスーツやヘルメットは先輩から借用した。マシンは大学の後輩から無償で借りた2トントラックで運んだ。メインテナンスなどチームに依頼する予算もあるわけもなく、ガソリンスタンドで給油だけして走らせた。タイヤの空気圧も無頓着で、目視でパンクしてなければそれで満足できた。当然、車中泊である。
そんな貧乏人が、金曜日から日曜日までのたった三日間で30万円を費やすなど、長くは続くはずがないと想像できた。今から40年前である。とてもじゃないけれど、就職したばかりの新人が手にする薄給で遊べる額ではない。
ただし、サーキットレースはとても刺激的だった。デビュー戦は社会人になって初めての夏。つまり、就職してから給料を貯めて3ヶ月。小遣いでレースデビューを果たしたわけだが、もう一度だけ挑戦して最後にしようと心に誓い、さらに3ヶ月間小遣いを貯めて再エントリー。12月の最終戦で、二度目の富士フレッシュマンを経験することになったのである。そこでは勝った。僕のレース人生の始まりである。
いい時代になりましたね
あれから40年。いまではレーシングカーのレンタルが盛んである。ネットで検索すれば、瞬時にサーキットデビューへの道筋が開ける。
競技ライセンスの取得方法はもちろんのこと、レーシングスーツの購入からヘルメットの顎紐の締め方まで、懇切丁寧に教えてくれる。時代は優しくなったのだ。
トヨタは積極的に、入門用ワンメイクレースを開催している。ブロドライバーの丁寧な指導付きだ。バケットシートの座り方からレクチャーしてくれる。ヘルメットひとつ手にしてサーキットに行けばいい。
そもそも、サーキット走行会が隆盛である。僕がたびたび講師として参加する砂子塾も頻繁に開催されており、常に満員御礼である。
自家用車でやってきてたっぷりと走行ができるのだが、当時と違ってマシンが壊れることも考えづらいし、スピンやクラッシュも少ない。電子デバイスが充実しているからだ。今やサーキット走行の危険性は以前より低くなっていると言っていいだろう。初めての草サッカーで足首を捻挫するよりも、サーキット初心者がクラッシュしたりマシンを壊したりする確率の方が少ないかもしれない。
もはや、10円玉を握りしめて電話ボックスからレース界の扉を開けるなどしなくてもすむ。寛容なレース界の到来を歓迎すべきだろう。
せっかくやってきた、レース寛容の時代である。週末にサーフィンするような気軽な感覚で、モータースポーツの扉を開けてみてはいかがだろうか。
キノシタの近況
日本列島を襲った記録的寒波にも不安がなかったのは、マイカーに最新のスタッドレスタイヤを履いたからである。トーヨータイヤの「オブザーブ・ギザツー」には鬼クルミが配合されている。アイスバーンを引っ掻くのである。削れたって天然だから環境にいい。
今冬再び大寒波がきたとしても、心配することはないのだ。