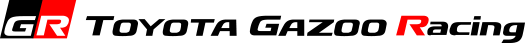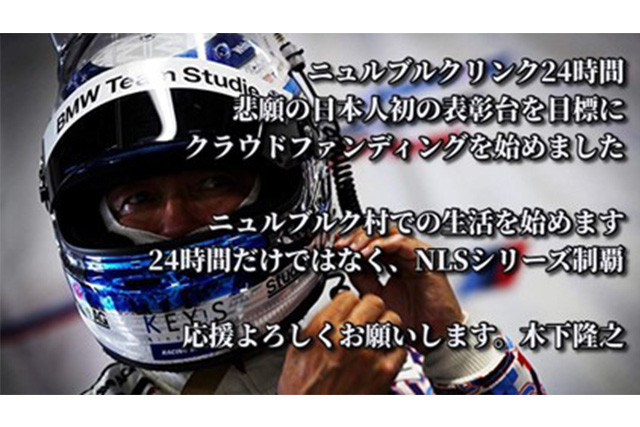336LAP2023.03.22
タイヤ交換コンマ5秒
技術の進歩に比例して速くなるマシンには驚かされる。その一方で迅速になるピットストップも、もはや観戦するに値するショーであり曲芸である。これまで数々のレースを経験してきた木下隆之が、ピット作業の変遷を辿る。
4輪交換は2秒
F1グランプリが開幕した。群雄割拠、実力拮抗が進んで、勝者を予想するのが難しくなった。2年連続ワールドチャンピオンのM・フェルスタッペンを要するレッドブルはシーズン前の好調を維持し、開幕戦を制した。僚友S・ペレスが2位。圧倒的なチーム力を誇示した。
そんな中でドライバーの激走を後押ししたのは、レッドブルのピットストップの迅速さだ。これまでの最短1.96秒は、伏兵ウイリアムズが記録した数字だが、レッドブルは平均して速い。
マシンが止まり、ジャッキアップして4輪交換、そしてマシンを落としてスタートするまでが約2秒。物理的にそんなことが可能なのか怪しむほどに速い。だが、現実にそれが目の前で行われている。
ピットマンはもはや、一つの職業として成立している。F1やNASCARのような最高峰のレースにかぎって…という注釈付きだが、タイヤ交換が得意な人材は、それ専門にチームに雇用されるという。これまでは…、あるいはF1やNASCAR以外では、タイヤ交換はメカニックの誰かがやる、というのが一般的である。走行が終わればスパナを握りボルトナットを締める。火花を散らせながら溶接する。そんなメカニックが、レースの本番だけは耐火スーツに着替えてタイヤ交換をするというのがパターンなのだ。チーム内で競ってみて、なんだか得意そうな奴が担当するといったイージーさである。タイヤチェンジマンを専用に雇うという余裕はない。
F1やNASCARのタイヤチェンジマンは、それだけで年収数千万円に達するという。かつてアメリカンフットボールで活躍した選手が、第二の人生でタイヤチェンジマンを選ぶこともあるという。花形のアスリートなのである。
「コース上の1秒もピットストップの1秒も同じ1秒なんだからな」
古今東西、チーム監督や重鎮がピットタイムの重要性をそう語ることでピットマンを鼓舞し続けてきた。
いや、コース上の1秒もピットストップの1秒も同じ1秒ではない。前後スリップストリームを使いあってきたドライバーがアンダーカットを狙った場合、1秒のロスは順位の差になる。表彰台に立てるか否か。シリーズチャンピオンになれるか否か。賞金の額に換算すれば、何億もの差になる。コース上の1秒もピットストップの1秒も同じ1秒ではない。だが、古くからそんな言葉でピットマンの価値を高めてきた。
それでも急いでいた…
いつからこれほどタイヤ交換が速くなったのだろうか。古き良き時代のレース動画を振り返ってみると、なんとものどかなピット作業が微笑ましく思える。日本のモータースポーツ黎明期、第一回グランプリあたりのピット作業はほとんどコントだ。
マシンがピットインする。
タイヤチェンジマンが駆け寄る。
ジャッキが差し込まれ、マシンが浮く。
ホイールナットを緩める。
ドライバーが、マシンから降りる。
タイヤチェンジマンの背中を叩きながら「ガンバレ頑張れ」と叫ぶ。
あらためてドライバーがマシンに乗り込む…。
そしてピットアウト。
タイヤチェンジマンを鼓舞するためにわざわざ降車し、あらためて乗る必要があるのか理解不能だが、そんなテンポなのだ。だからと言ってノンビリ作業をしているのではない。当人たちは本気で、1秒を争っているのである。
マシンから降りてタイヤチェンジマンを鼓舞したのはいまから50年ほど前のことだが、1990年頃のF1、つまりホンダの黄金期、セナプロ時代でさえ、ピットストップに要する時間は6秒以上だった。
もちろん、コンマ1秒を争っていた。それでも、6秒なのである。
コンマ5秒の世界はあり得るのか
6秒を2秒に短縮するのに30年ほどの月日を要しているのは、タイム短縮のための緻密な仕掛けが理由であろう。ピットに飛び込んできたマシンは、作業エリアに記されたラインに正確に止まる必要がある。タイヤチェンジマンがあらかじめインパクトレンチを構えたその場所に、数センチの狂いもなく止めることが要求される。
インパクトレンチの回転スピードは驚くほど高速だ。アンカーのネジ山も少ない。一瞬にしてナットが弾かれ、締め込まれる。
以前、プロ用のインパクトレンチを操作した経験がある。そもそも手首にずっしりとするほど重みがあり、ボタンを押して高速回転させると、手首が弾かれそうになる。それでも圧力を下げているようで、本番の圧力では怪我をするだろう。
ジャッキアップの高さも、タイヤが外れるギリギリの高さに抑えられている。
ドライバーはシグナルが青に点灯した瞬間にクラッチミート。ピットを離れる。
かつてのように、「イケイケいけ〜」なんて手を振りながらピットアウトを急かせるようなことはない。
かつてN・マンセルが自陣のピットを通り過ぎてしまい、ピットロードでは禁止されているバックギアで戻ろうとしたような、あんな珍事は起こらない。もたもたとまごつくタイヤ交換に苛立って、タイヤ未装着のまま発進してしまうことも最近では稀だ。
ピット作業はシステマチックになり、インパクトレンチやジャッキが高性能になった。チームの意識も変わった。
「コース上の1秒もピットストップの1秒も同じ1秒なんだからな」とは言いながらもチームはその重要性を理解していなかったあの頃とは、意識が違うのである。
チーム監督はピットストップロスを減らそうと口では言うものの、根底のところでは、タイムはコース上で稼ぐものという意識があったからだと思う。マシンの性能が拮抗しておらず、ライバルとのタイム差も十分にあった。ピットでコンマ1秒をロスしたところで、コース上で取り返せるという思いがあった。だからピットロスに無頓着だったのだろうと思う。
実際に、降車してタイヤチェンジマンの背中を叩きながら鼓舞したドライバーは、余裕で優勝していた。
ピットロードの速度が制限されていなかったことを思い出すのは難しい。というのも、そんな危険なことが行われていたとは、俄に信じられないからである。いまから30年ほど前のグループA時代、全日本ツーリングカー選手権でさえピットロード速度制限はなかった。
いまでも信じられないのは、筑波サーキットのあの狭いピットでタイヤ交換が行われているその脇を、僕らはアクセル全開で駆け抜けていたことだ。
当時僕はスカイラインGT-Rで全日本ツーリングカー選手権を戦っていた。4輪駆動であり、600馬力を超えるモンスター。そんなマシンでありながらアクセル全開でピットロードに駆け込んでくる。あるいはタイヤ交換後にアクセル全開で加速していく。いくら筑波サーキットのピットロードが短いとはいえ、ピットロードエンドでは150km/hを超える速度が出ていたはずである。
作業エリアは狭い。タイヤチェンジマンは、走行エリアに尻を突き出して作業をしていたはずである。僕もコンマ1秒を削り取るために、全開で通過していたはずである。
そんな危険なことをしていたはずなのに、記憶にないのだ。
そのシーンの動画をお持ちの方は、是非僕に提供していただきたい。
そんな危険な環境でコンマ1秒を削ろうとしながらも、タイヤ交換は牧歌的に進んでいた。決してピットストップロスを軽んじていたわけではなく、チームは頻繁にタイヤ交換の練習を繰り返していた。ガソリン給油とタイヤ交換のタイミングを合わせ、ドライバーチェンジのサポートマンの動きを確認し、ライバルを出し抜こうとしていた。だが、現在と比較すれば滑稽なほど遅い。
「F1なのにピットストップで2秒を費やしていたんだね。いまではコンマ5秒だものね。笑える〜」遠い将来、そんな会話がされる時代が来るのだろうか。
いや、いくらなんでもコンマ5秒はあり得まい。
いや、当時でも6秒は驚速であり、これ以上短縮させることはあり得ないと思っていたのである。
「タイヤ交換コンマ5秒」
あり得ないわけではない。
キノシタの近況
今年もニュルブルクリンクでの活動のためにクラウドファンティングを始めました。
24時間はトーヨータイヤのサポートにより完璧な体制で出場しますが、そこでパフォーマンスを100%引き出すために、NSLニュルブルクリンク耐久シリーズへの参戦を計画しているのです。ご支援のほどよろしくお願いします。