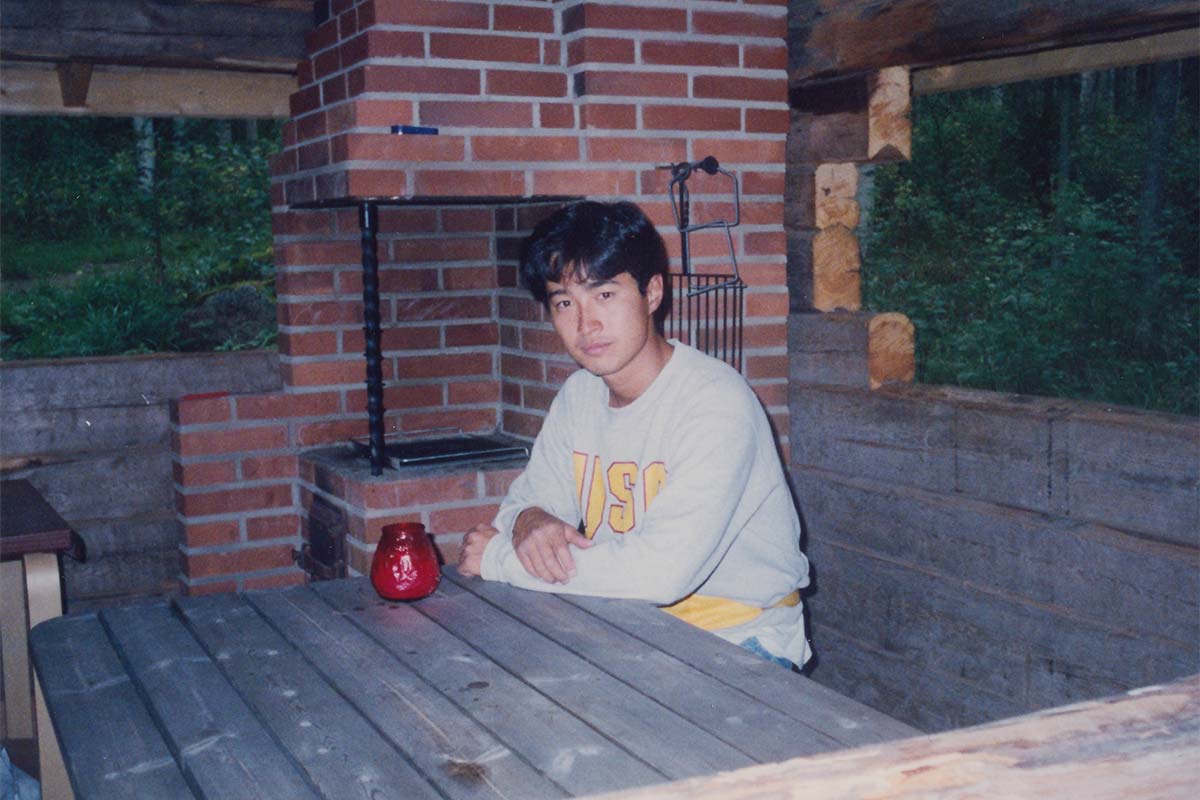真夏のフィンランドで体験した
ラトバラ代表の衝撃的ドライビング
WRCな日々 DAY34 2022.8.26
少し前の話しになってしまうが、今回は8月のフィンランドでの「強烈な体験」について書きたいと思う。それは、TGR WRTチーム代表のヤリ-マティ・ラトバラさんがドライブする、ラリーカーの同乗走行。想像していた以上の興奮と楽しさに、あれから2週間以上経った今も、思い出すだけでニヤニヤしてしまう。それくらい、車両年齢30歳近い「セリカGT-FOUR」のコ・ドライバー・シートは抜群に楽しかったのだ。
「ラトバラ代表のラリーカードライビングを体験しませんか?」というお誘いをチームから頂き、「もちろん!」と即答した。その時は最新のGR YARIS Rally1 HYBRIDを、彼がドライブするのだと勝手に思い込んでいた。だから、クルマがRally1ではなく、ラトバラさんが所有するST185セリカGT-FOURだと知った時は、正直ほんの少しだけ残念に思った。何しろ今から四半世紀以上前に活躍した「老馬」だ。しかも、近年の怪物的な性能のラリーカーと比べたら、改造範囲が遥かに狭いグループA時代の車両だから、助手席に乗ってもそれほど大きな驚きはないだろうと、大変失礼ながら思い込んでいた。
同乗走行の会場となったのは、ラリー・フィンランドの中心であるユバスキュラから140km程度西北に離れた、トゥーリという小さな町の近く。トゥーリはラトバラさんの出身エリアで、ラトバラ博物館とも呼ばれている「JM-Rally Parc Ferme」があることで知られている。ラトバラさんの子供時代の乗り物から、彼が乗ってきた数々のラリーカー、そしてトヨタの歴代ラリーカーが展示されていて、非常に見応えがある。2階には獲得したトロフィー、ヘルメット、レーシングスーツ、書籍といった展示物に加え、ファンからの贈り物までたくさん展示してあって、そういうものをちゃんと大切にしているのが、ラトバラさんらしいなあと思った。
実は、ラトバラ博物館には5年前に一度行ったことがあった。その時は偶然にも当時TGR WRTのドライバーだったラトバラさんがいて、彼自身が親切に館内を案内してくれた。自分がその昔クラッシュした時に潰したラリーカーのボンネットやラジエター、割れたホイールなどジャンクパーツを手に持ち、その時の話しを面白おかしく説明してくれたりと、本当にサービス精神が旺盛だった。そういったアクシデントまで含めて、ラリーという競技を心の底から愛しているのだなと思った。
今回は、各国のメディアと一緒に館内を回ったが、5年前にはなかったトヨタ歴代ラリーカーの展示スペースと、立派なワークショップも見学することができた。少し古いラリーカーをラトバラさんが大好きで、それをリビルドして近年フィンランド国内のラリーに出ていることは知っていた。しかし、ワークショップの規模や設備は趣味の領域を完全に越えていて、数多くの古のセリカGT-FOURがリビルド作業を受けていた。どうやら、ビジネスとしてもかなり需要があるようだ。
そこで思い出すのが、2018年に彼と一緒にドイツ、ケルンのTGR-E(旧TTEの活動拠点)を訪ねた時のことだ。ヤリスWRCのエンジン開発現場を見学することが主目的で、当時選手だったラトバラさんはとても熱心にエンジン開発者の話に耳を傾けていた。しかし、彼がもっとも興奮し、目を輝かせたのは、展示されていたワークスカーのST185セリカGT-FOUR(海外名はセリカ・ターボ4WD)に対面した時だった。ボンネットを開けてエンジンルームの中に顔を突っ込み、小さな電気部品や配線を真剣に観察。昔ワークショップのメカニックだったという、ベテランのスタッフを質問攻めにしていた。その時も「本当にセリカGT-FOURが好きなんだな」と思ったが、彼にとっては子供時代の憧れであり、永遠のヒーローカーなのだろう。
前置きがかなり長くなってしまったが、いよいよ同乗走行である。走行ルートは、ラトバラ博物館から少し離れたところにある農場地帯と、野原の未舗装路。それほど距離は長くないけれど、それでも十分にフィンランドらしさを味わえるコース設定だ。用意されたST185セリカGT-FOURは超ド派手なイエローのカラーリングが施されていたが、よく見るとワークスカー時代のリバリーがモチーフになっていた。僕の同乗走行枠はかなり後ろの方だったので、まずはコースサイドで走りを楽しむことにした。昔のラリーカーだし、まあのんびり走りでも楽しもうかと、「マッカラ」というフィンランド名物のソーセージを頬ばりながら、ラリーファン気分でクルマを待った。すると、突然、大きな納屋の角から黄色いセリカが轟音を響かせ、真横を向いて現れた。S字コーナーでクイックに向きを変えると、おびただしい量の砂利をはね飛ばしながら、激しくドリフト。体全体にビチビチと小石が当たり、ポカンと開いていた口の中には砂煙が入り込み、マッカラに農場の土の風味が加わった。
自分の想像の遥かに超越する速さ、迫力、そしてカッコ良さだった。決して四半世紀前の老馬などではない。これぞラリーカー! と快哉を叫びたくなる、堂々たる走りっぷり。ドライバーにしても、WRC通算18勝を誇り、数年前までワークスカーのヤリスWRCを自在に操っていたラトバラさんだ。何というか、とても貴重なものを見ているような気持ちになり、マッカラを慌てて飲み込み、真剣に撮影に入った。カメラのレンズを通して見るST185の走りもまた格別で、興奮しながらシャッターを無我夢中で押し続けた。
思い出して見れば、学生時代に初めて生でWRCを観た1992年の1000湖ラリー(現在のラリー・フィンランド)でも、ST185が走っていた。その年はST185のデビューイヤーで、ホワイトのボディに真っ赤な空豆風の、独特なカラーリングが施されていた。その翌年に観に行ったラリーGB(当時のRACラリー)では、カストロールカラーのST185をユハ・カンクネンさんがドライブ。リエゾン(移動区間)では彼のST185の後ろを延々と走り続け、チャンピオンマシンのエキゾーストサウンドと薫りを存分に愉しんだ。だから、自分にとってもST185は少し特別な意味を持つクルマで、そんな昔の思い出がラトバラさんの走りを目にしたことによって、一気に蘇ったのだ。ST185を老馬だなんて思うのは、自分が老いましたと宣言するようなものだと、55歳の誕生日を数日後に控えていた僕は反省し、お腹のあたりで上に行くことをやんわり拒んでいたレーシングスーツのジッパーを、無理やり締めた。同乗準備、完了である。
ラトバラさんは既に運転席に座っていて、普段クルマに乗っていない時のフレンドリーな表情とは違う、少し険しい顔つきだった。別に不機嫌なわけではなくて、それは選手時代によく見られた本番モードの時のお顔だった。クルマが古かろうと、隣に誰が乗ろうと、ヘルメットを被ってステアリングを握ったら常に全力で走る。それが「ラトバラ・スタイル」だ。
最近のラリーカーと比べると、室内はかなり簡素で鉄板剥き出し。名機3S-GTEのアイドリングは「ドリュッ、ドリュッ、ドリュッ」と野太く、あの時代のレーシングエンジンらしく荒々しいワイルドな振動が伝わってくる。準備が整うと、ラトバラさんはアクセルを踏み込んで回転を上げ、絶妙なタッチでクラッチをミート。その瞬間、予想を上まわる加速Gで身体がフルバケットシートにめり込んだ。「けっこう速いじゃないの」と思わず笑いがこみ上げたが、速度が上がっていくにつれて顔が引きつっていった。けっこうどころではない、すごく速い! かなり広いように感じられた道はどんどん幅が狭まっていくように見え、木々が迫る。そしてコーナーが近づくと、ガツンというこれまた強烈なラトバラ・スタイルの減速Gで首が前に持っていかれたが、それがすぐ横Gに変化。スルッと流れるリヤをやや大きめの、しかし目にもとまらぬ速さのカウンターステアでコントロールし、高速ドリフトに突入した。路面のうねりで飛び跳ねながらも、構わずドリフトでコーナーを駆け抜けていく。ああ、これは90年代のWRCグループAカーの走りだと、外から見ていた昔の映像と感覚がリンクした。しかもドライバーは、フィンランド系ドリフト走行の正統継承者であるラトバラさんだ。こんなに楽しい経験はないぞ! と、そこから先はただひたすらニヤニヤしっぱなしだった。
少し冷静になって走りを観察すると、ギヤシフトはWRカーのようなパドルシフトではなく、最新のRally1で採用されている縦方向のシーケンシャルシフトでもなく、懐かしのH型パターンだった。その昔はハンドルやペダルさばきだけでなく、シフトワークもラリードライバーの腕の見せ所で、ドリフト中に左手でカウンターステアを当てながら、素早く右手でシフトするといった妙技に、学生時代の僕はしびれていたものだ。そのシフトワークが今、視界の左端で行われているのだ。シフトワークだけでなく、ペダルワークも忙しく、ミッションを守るためかクラッチもけっこう踏んでいる。そして、やや曲がりにくいタイトターンでは、クルマをコーナーの向きと逆側に振ってドリフトさせてから、一気にスパンと反対方向に向きを変える「フェイント走法」を披露。ラトバラさんは両手両足を全て使いきって、ST185をコントロールしていた。その操作は現代のラリーカーの数倍くらい忙しく見え、いかにもクルマを操っているという感じが視覚でも伝わってきた。ラリードライビングがスポーツであることを、改めて実感した。
やがて、最後のセクションに入り、S字の揺り返しでドリフトしたまま納屋の角のコーナに進入。「ああっ、納屋にぶつかる!」と本気で身構えた。助手席に乗ってる自分の感覚では、納屋の角にノーズが突き刺さるように見えたからだ。しかし、当然のことながらST185は角をなめるようにギリギリでクリアし、フィニッシュ。5分程度の短い試乗時間だったが、もうお腹がいっぱいだった。走行を終えてようやくラトバラさんも笑顔になり、いつものフレンドリーな彼に戻っていた。ゲストを相手に、真剣に走ってくれてありがとうと、感謝の気持ちがこみ上げてきた。
同乗走行が終り「想像以上にクルマが速くて驚きましたよ」と伝えると、ラトバラさんは首を何度も縦に振り「そうでしょ、そうでしょ」と、まるでお父さんを褒められた子供のように嬉しそうだった。「エンジンは当時のグループA仕様で、吸気リストリクターもついているけど、370馬力くらいは出ている。ただし、このクルマ自体は当時のワークスカーではないので、無駄な部品も多く車重は1300kgくらいと少し重いんだ。前に持っていた元ワークスカーは1240kgで軽かったから、さらに速かったよ」と、説明にも力が入る。「速さ、という点でも最新のラリーカーに決して負けていない。このひとつ前の世代のST165は、自分がフィンランドの国内ラリーに出た時のデータでは、最新のRally2カーに対して平均で1kmあたり1.5秒近く遅かった。しかし、このST185はステージによっては1kmあたり1秒以下の遅れで走ることができる。今でも十分に速いクルマだよ」
今年のサファリ・ラリーでもそうだったように、コンディションが良くない路面で、Rally2は、Rally1より速かったりもする。そのRally2に1kmあたり1秒差に迫るというのだから、今の基準で考えても相当速い。僕も以前ヤリスWRC、シトロエンC4 WRC、スバル・インプレッサWRCといったトップラリー車両に何度も同乗してきたが、ST185の速さはそれらのクルマに負けていないように感じた。ラトバラさんによると、基本的には当時のオリジナルなコンディションを保っているというが、ダンパーはケース自体は昔と同じものながら、内部のパーツの性能は大きく向上していて、エンジンを司るコンピュータも処理が速い最新のものとなり、クルマ全体のパフォーマンスは90年代の当時よりもかなり高いようだ。また、タイヤも昔より性能が上がっているため、グリップレベルはかなりいいという。ラトバラさんは、勝田貴元選手のドライビングコーチも務めている、ユホ・ハンニネンさんをコ・ドライバーに迎え、このST185で精力的にラリーに出場し好成績をおさめている。少し古いクルマであっても、真剣に競技に臨み、ドライバーとしての感覚を持ち続けることは、チーム代表という今の仕事にとってもプラスになっているはずだ。
「改めて、ST185は本当にいいラリーカーだと思いました」と最後に伝えると、ラトバラさんは「僕もそう思うよ。きっと、カンクネンもそう言うと思うから、もし彼に会う機会があったら聞いてみたら?」とアドバイスしてくれた。そして何ともタイミングよく、ラリー・フィンランドの次のWRCイベントであるイープル・ラリー・ベルギーで、彼に会って話しを聞くことができた。カンクネンさんは、豊田章男TGR WRTチームオーナーと共に、水素エンジンのGR YARIS H2をWRCのステージで走らせるために、ベルギーを訪れていたのである。
「ST185は、自分にとって間違いなくベストなセリカだ。エンジンもハンドリングも素晴らしく、とてもコントロールしやすかった。とにかく走っていて最高に楽しかったし、多くの勝利を獲得してチャンピオンになったクルマでもあるからね」と、カンクネンさんは当時のことを嬉しそうに語ってくれた。
ST185セリカGT-FOURは、間違いなくトヨタのWRC黄金時代を支えた名車中の名車であり、四半世紀が経った今も、その魅力は少しも褪せていなかった。そして、GT-FOURという4輪駆動を示すグレード名は、GR-FOURというスポーツ4WDシステムの呼称として、GR YARISに受け継がれているのである。
古賀敬介の近況
フィンランド、ベルギーと1ヶ月近いヨーロッパの取材を終え久々に日本に戻りました。本当に中身の濃い充実した日々で、それほど長くいた感じはしなかったのですが、さすがに少しくたびれました。この写真はもちろん近況ではなく、文中でも触れた1992年に初めてWRCフィンランドを観に行った学生時代のものです。今回、その年にデビューしたST185に同乗走行して初心に帰りました。僕もリビルド……ではなくリフレッシュして、また次回の取材に臨みたいと思います。