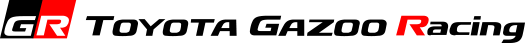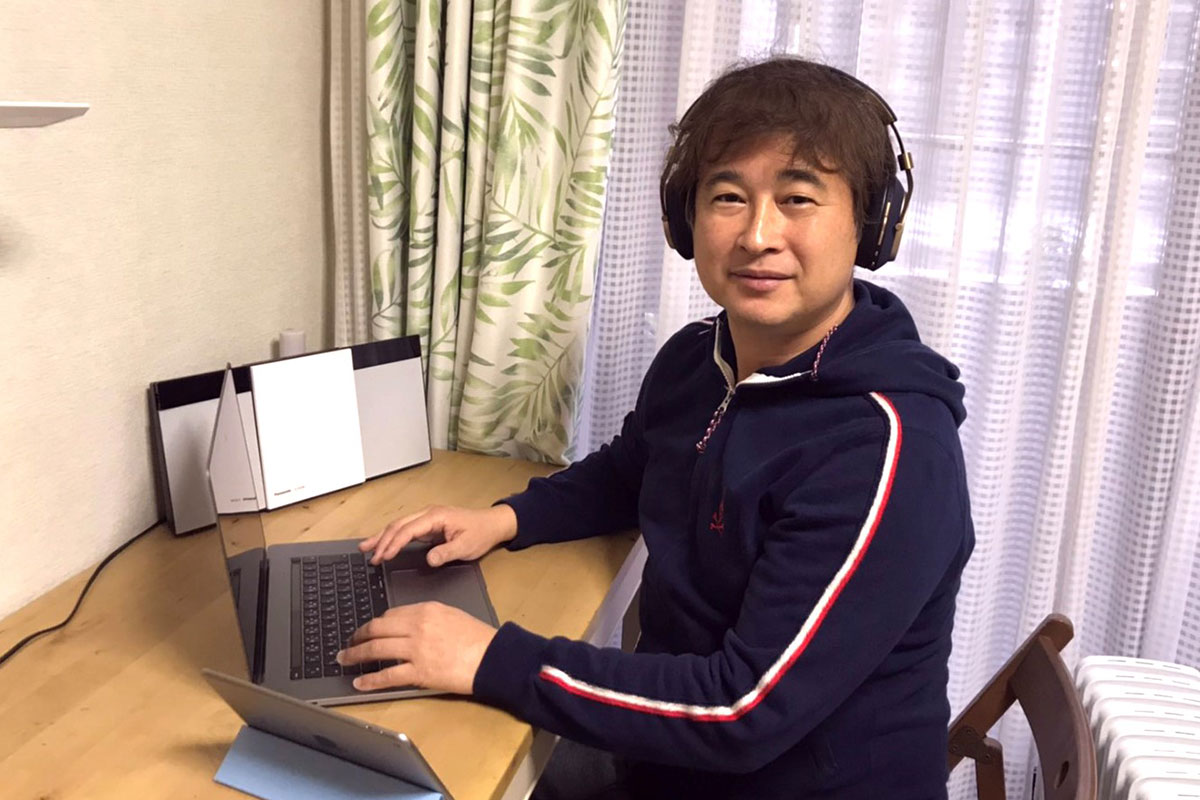かつて「世界一のラリー」と呼ばれた、
ポルトガルに思いを馳せる
WRCな日々 DAY5 2020.5.22
新型コロナウイルスの影響で多くのラリーが延期や中止を余儀なくされているが、本来ならば5月の第4週に開催される予定だった「ラリー・ポルトガル」もそのひとつ。主催者は人々の健康を最優先し、今シーズンの開催を中止すると発表した。間違いなく正しい決断だったと思うが、ポルトガルのラリーファンはさぞかし落胆したに違いない。
ポルトガルの人々は本当にラリーを愛していて、その昔は「世界一熱狂的なファン」といわれていた。あまりにも興奮し過ぎてステージ上に足を踏み入れ、路面が見えないくらい人で溢れるというのが、ラリー・ポルトガルの日常的な光景だった。その群衆の中をラリーカーは全開ドリフトで駆け抜け、一部の観客は闘牛のようにラリーカーに触れることを楽しんでいた。その時代の映像は動画サイト等で見ることができるが、現代の感覚でいったらあり得ないくらい危険だ。しかし、当時はそういった行為がまだ黙認されていた。彼らファンにとってラリー観戦は、1年に1度の「祭り」だったのだ。今でもスペインで危険な牛追い祭りが行われていたり、日本国内でも大怪我の可能性がある祭りが許容されているように、当時のポルトガルではそういった観戦スタイルも祭り、或いは文化のひとつとして捉えられていたのだ。
しかし、80年代に大きなアクシデントが起こったことによって、WRCは観客や選手の安全について、より真剣に考えるようになった。「モンスター」と称されたクルマが覇を競ったグループBが1986年をもってWRCから締め出されたのも、その発端はポルトガルでのアクシデントだったといわれている。WRCはより安全に行なわれなければならないという意識が高まり、ラリーカーの技術規定や、観戦エリアの安全に関するガイドラインが見直された。ワイルドだった時代を懐かしむ人々も多いが、安全性を大きく引き上げたからこそ、WRCは存続し、現在でも最高のエンターテイメントであり続けているのだ。
コース上に観客の姿はなくなったが、コースサイドの熱狂は現在も全く失われていない。ビッグジャンプで有名な「ファフェ」のステージを初めて訪れたならば、周囲の丘全体を覆う観客の多さにまず驚くことだろう。観客の「密集度」に関しては恐らくWRCナンバーワンであり、大規模ロックフェスの会場のようである。主役は、もちろんラリーカーと選手。WRCにはいくつもの素晴らしいジャンピングスポットがあるが、ファフェは間違いなくトップ3に入る名所だ。ジャンプ台の後方から撮影していると、ラリーカーは観客の森に向かって離陸するかのように見える。もちろん、現在は最大の安全性が確保されており、ステージと観戦エリアの間には十分なスペースが設けられている。安全に、これほど素晴らしいショーを見られるのだから、ポルトガルのファンは幸せだ。
その、ファフェのステージが「復活」したのは比較的最近のこと。しばらくラリー・ポルトガルはファフェが位置する北部を離れ、2007年から2014年にかけては南部のアルガルヴェ地方で開催されていた。さらに時代を遡ると、2002年から2006年までの5年間、ラリー・ポルトガルはWRCのステータスを失っていた。理由はいろいろあるが、多くの国がWRC開催に名乗りをあげ、主催者が競争に敗れたのも理由のひとつ。また、オーガナイズに不備があったともいわれている。いずれにせよ、かつて「世界一のラリー」と呼ばれていたポルトガルはWRCのカレンダーから姿を消し、ファンだけでなく選手も喪失感を味わった。
ラリー・ポルトガルは1973年のWRC創設初年度からシリーズの1戦に組み込まれ、数々の名勝負が繰り広げられてきた。そして、1975年大会でフィアット・アバルト124ラリーをドライブし優勝したマルク・アレンは、1987年までにポルトガルで通算5勝を記録し、ポルトガルの盟主と呼ばれた。そのアレンの最多勝記録に2017年大会の優勝で並んだのが、今年TOYOTA GAZOO Racing WRTで活躍中するセバスチャン・オジエである。オジエにとってポルトガルは特別な1戦であり、彼が記念すべきWRC初優勝を遂げたのも2010年のポルトガルだった。当時オジエはシトロエンの育成ドライバーで、WRカーによるシーズン参戦は2年目だった。その時、シトロエンのエースは絶対王者のセバスチャン・ローブ。オジエは、ローブとマシンは同じながらも二軍チームからのエントリーで、体制的にはやや劣った。しかしオジエは出走順も味方につけ、ローブと好バトルを展開。WRCポルトガル戦2連勝中だったローブを破り、初めてポディウムの頂点に立った。彼の、輝かしいサクセスストーリーの出発点である。
その時、取材をしていてとても印象に残ったことがある。タイヤメーカーのエンジニアに話を聞いた時、彼は「今、WRCでもっともタイヤの使い方が上手いのはオジエだ」と言い切ったのだ。当時はローブの全盛期で、ローブは誰よりもタイヤをマネージメントする能力が優れているといわれていた。しかし、そのエンジニアによれば、少なくともグラベルラリーにおいては、オジエの方がタイヤを上手に使っているということだった。当時、ラリーはポルトガル南部を舞台としており、ドライコンディションであれば路面は非常に硬質だった。平たい岩が露出している路面も多く、タイヤの摩耗が早く進んだ。タイヤ巧者として名高いローブでさえも、ストレスがかかる前輪の摩耗は厳しかった。
しかし、オジエは4本のタイヤをやさしく均等に使うドライビングに長けており、ライバルよりも1ランク柔らかいタイヤ、つまりグリップ力は高いが摩耗しやすいタイヤを選ぶことができたのだ。それが、ライバルに対する大きなアドバンテージとなり、今現在でも彼の武器である。タイヤを上手く使えるドライバーはチャンピオンになり得ると、当時僕はオジエのその後の成功を確信したことを覚えている。
2015年以降、オジエのポルトガル優勝は1回に留まっているが、それはラリーの舞台が北部に戻り、路面がやや柔らかくなりタイヤへの攻撃性が低下したこと、そしてグラベルステージでの出走順が不利に働くケースが多かったことが原因として考えられる。もし、予定通りにラリー・ポルトガルが今年開催されていたら、ドライバー選手権リーダーのオジエは不利な先頭スタートを担っていたはずだ。それでも、昨年オィット・タナックが優勝したことからもわかるように、ヤリスWRCとポルトガルのステージの相性は良い。オジエにとっては、最多優勝回数を6に伸ばす絶好のチャンスだっただけに、残念でならないだろう。
こうして原稿を書きながら、ポルトガルの素晴らしいステージ、そしてトップドライバーたちのビッグファイトが次々と頭に浮かんでくる。そして、仕事を終えて仲間と一緒に行ったレストランの食事も恋しい。自分の中で、ポルトガルといえばイワシ。シンプルに炭で焼いたイワシに、オリーブオイルを垂らしていただくのがポルトガル流だ。イワシの塩焼きなんて特別な料理ではないし、自宅だってできる。しかし、ポルトガルのイワシはアジのように立派で、身がふっくらしていて、そして何よりも味わい深い。日本で自分が焼くイワシとは、違う食べ物のように思えるくらいだ。一体何が違うのだろうか? サービスパークが置かれるマトジニョスの海岸沿いには、イワシを含むシーフードの名店がひしめく。1年に1回、行きつけのイワシ屋を訪れるのも楽しみのひとつだったので、それもまた残念至極。1日もはやく、世界が平常運転に戻ることを願うばかりだ。
古賀敬介の近況
5月も引き続きステイホーム中。電話やテレビ会議ソフトを駆使してテレワークに励んでいます。ほとんどお金をかけずにヨーロッパの人に長時間取材をできるなんて、考えてみたらすごい時代ですよね。それでも、やっぱり現場取材をしたい! WRC再開は、今のところ早くて8月のラリー・フィンランドです。その時、野山を駆けられるように今からトレーニングに励まないと!