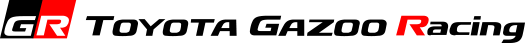335LAP2023.03.08
ライダーは四輪で通用するのか…?
二輪の世界選手権で9度のチャンピオンに輝いたバレンティーノ・ロッシが、四輪への転向を決めた。はたして二輪時代のように、天才的な走りが可能なのか? 多くのライダーとも親交の深い木下隆之が予想する。
ロッシが引退会見で語ったものは…
今から約1年半前の2021年11月、Moto GP第18戦バレンシアGP前日、バレンティーノ・ロッシが引退を発表した。記者会見場だったリカルド・トルモ・サーキットには、9度のワールドチャンピオンに輝いたスーパースターの別れの涙をひと目見ようと、多くのマスコミが集まった。だが、ロッシの表情は笑顔に満ち溢れ晴れやかだった。
これまでの栄光への祝辞に加え、今後の生き方に対しての質問があり、ロッシはこう答えた。
「これからも僕はサーキットに通う。バイクにまたがることからは引退したけれど、レーシングドライバーとしての人生を歩み出す」そう宣言したのだ。
あれから1年半。ロッシの姿はファナテックGTワールドチャレンジ・ヨーロッパが開催されるイモラ(イタリア)にあった。アウディの名門チーム「チームWRT」が走らせるアウディR8 LMS Evo IIのコクピットで、ステアリングを握っていたのである。
ゼッケンは、栄光のパーソナルナンバー「46」である。
3名のプロフェッショナルドライバーがコンビを組むファナテックGTワールドチャレンジ・ヨーロッパで、個人の希望ゼッケンが採用されることからも、チームが歓待していることがわかる。ロッシは四輪レースの世界では新人であり、パフォーマンスは未知数である。まずは先輩格のニコ・ミュラーとフレデッリク・バービシュ主導で戦略が組み立てられるであろう。だが、それでもゼッケンはロッシの希望が優先された。彼の存在の大きさが想像できる。
ファナテックGTワールドチャレンジは、近年隆盛を見るツーリングカー選手権である。マシンは、世界ツーリングカー格式のGT3もしくはGT4に限定されている。ファナテックGTワールドチャレンジ・ヨーロッパだけではなく、アジアシリーズもある。つまり、世界統一規格のマシンで戦うことで、世界展開されているのだ。特にヨーロッパシリーズはレベルが高く、いわば世界選手権の様相を呈している。
ロッシが加入したチームWRTは、アウディのワークス活動をサポートしてきた名門レーシングチームであり、過去にはル・マン24時間でもクラス優勝を果たした。
ファナテックGTワールドチャレンジ・ヨーロッパではチャンピオン候補であり、二輪で世界を制覇したロッシによる二輪四輪両制覇も夢ではない。
はたして通用するのか…
ロッシの四輪転向には、さまざまな議論が錯綜した。議題の中心は「はたして四輪で成功するのか…」である。ロッシの経歴は華々しく彩られている。1979年2月16日生まれた。イタリア国籍。現在44歳。
これまで数多くの勝利を積み重ねてきた。9度も世界選手権の王者に輝いた。ややヤンチャなキャラクターでありながら、圧倒的な速さで勝利をもぎ取っていく。史上最強のライダーと評価されている。そんな天才にとっては、四輪を制することなど容易いことのように思える。
これまでも、二輪から四輪に転向し、活躍したドライバーは少なくない。とくに国内では、たとえば高橋国光選手や都平健二選手、あるいは長谷見昌弘選手や星野一義選手など、こぞってライダーの世界で名を成した。多くがロードレースライダーではなく、モトロクスからの転向組だったという点も興味深い。
時代は日本のモータースポーツ黎明期であり、サーキットレースは限られていた。レーシングドライバーの存在がなく、自動車メーカーがモトクロスでの優秀な選手を四輪に転向させた。という背景があったにせよ、ライダーがレーシングドライバーに転向しても活躍したのである。
似て非なるもの?
四輪は二次元でのドライビングである。ステージはサーキットという平面だ。
一方のライダーも共に同じサーキットではあるものの、三次元の空間を踊るようにしてサーキットを駆け回る。身体剥き出しのまま体重を入れ替え、右や左に傾けながら、時には駿馬が前足を高々と掲げていななくように前輪を浮かせながら加速する。四輪の平面でのコントロールより、ライディングは複雑なような気がする。
バケットシートにしっかりと固定され、腕と足先以外の自由度がない四輪のドライビング姿勢と、身体はまったく固定されず、前後左右に体重を移動させながらのライダーとは、操縦方法が異なるような気がするのだ。
とはいうものの、バイクもクルマも動力付きの乗り物であり、2本と4本の違いがあるにせよタイヤが装着されている。それを、誰よりも速く走らせるセンスには違いはないのだろうか。バイクを趣味にする四輪レーシングドライバーも少なくなく、スポーツカーが好きなライダーも多い。バイクとクルマに共通項があることに疑いはないが、はたして…。
恐怖心と戦って来た男だからこそ
決定的な違いがあるとすれば、恐怖心であろう。レーシングドライバーである僕の感覚からすれば、ライダーに備わっている獰猛な闘争本能は尋常ではないと思う。
というより、ライダーの恐怖心の欠如はレーシングドライバーより優っているように感じる。生身の身体で300km/hオーバーで疾走するのは、ロールケージで固められたマシンにしっかりと固定されて到達する300km/hとは別次元であろう。そんな速度域で身体を傾け、縁石に膝を擦り付けながら攻める。
かつてはバイクのステップがコーナリングバンクの限界だったが、それが膝を擦るまでにバンクさせることが可能になった。最近では肘だ。近い将来、肩が擦るのではないかとまで噂されている。
そんな尋常ならざるアクロバチックなライディングは、恐怖心が麻痺していなければ不可能な芸当だ。ロールケージに守られているレーシングドライバーには想像できない危険な世界なのである。
二輪の世界で頂点を極めたライダーが、四輪レースで恐怖心を抱くことはないだろう。だが、それがドライビングを困難にするかもしれないとは思う。最近のクルマは安全になったことで恐怖心がなくなっている。特にファナテックGTワールドチャレンジ・ヨーロッパで使用されるGT3マシンは、数々の電子制御で武装されている。
ブレーキングでのタイヤロックを防ぐABSが組み込まれているし、加速時のタイヤの空転を防ぐトラクションコントロールも装備している。コーナリング時のスピンを防ぐ、電子的デバイスもある。誤解を恐れずに言えば、ドライビングはイージーなのだ。
だから逆に、コンピュータ仕掛けのマシンをコントロールするという、頭脳的なドライビングが要求される。根性試しでも恐怖心に打ち勝って攻めるのでもなく、冷静に走らせる能力が問われるのだ。
バイクにもABSやトラクションコントロールが常識になり、電子制御ハイテクデバイスを操る必要はあるが、それでも頻繁にコケるし、コケればすぐに怪我をする。クルマとバイクは根底のところで別物なのだ。
だからこそ、ライダーとして成功したロッシがドライバーとして通用するのか否かに興味が集中する。それはすなわち、バイクとクルマの違いを露わにしたいという興味なのである。
まずは慣れることが先決なのかもしれない
ちなみに、ファナテックGTワールドチャレンジ・ヨーロッパ開幕戦のイモラでは、予選51台中37番手のタイムを記録した。総合17位でチェッカーを受けている。
その数字だけで判断するならば、まだまだ苦戦しているかもしれないとの予想がたつ。マシントラブルやアタックのタイミングミスや、あるいは戦略的な不都合など、数字だけで判断できないのがレースであることを付け加えておこう。
今後のロッシに注目したい。彼の走りから、バイクとクルマの違いの何かを知ることができるかもしれない。
キノシタの近況
ドカ雪に備えてトーヨータイヤ「オブザーブ・ギザ3」に替えたんですよ。特に、氷に強い鬼クルミ配合のスタッドレス。だから降雪を期待しているんだけど、もう春の気配ですね。