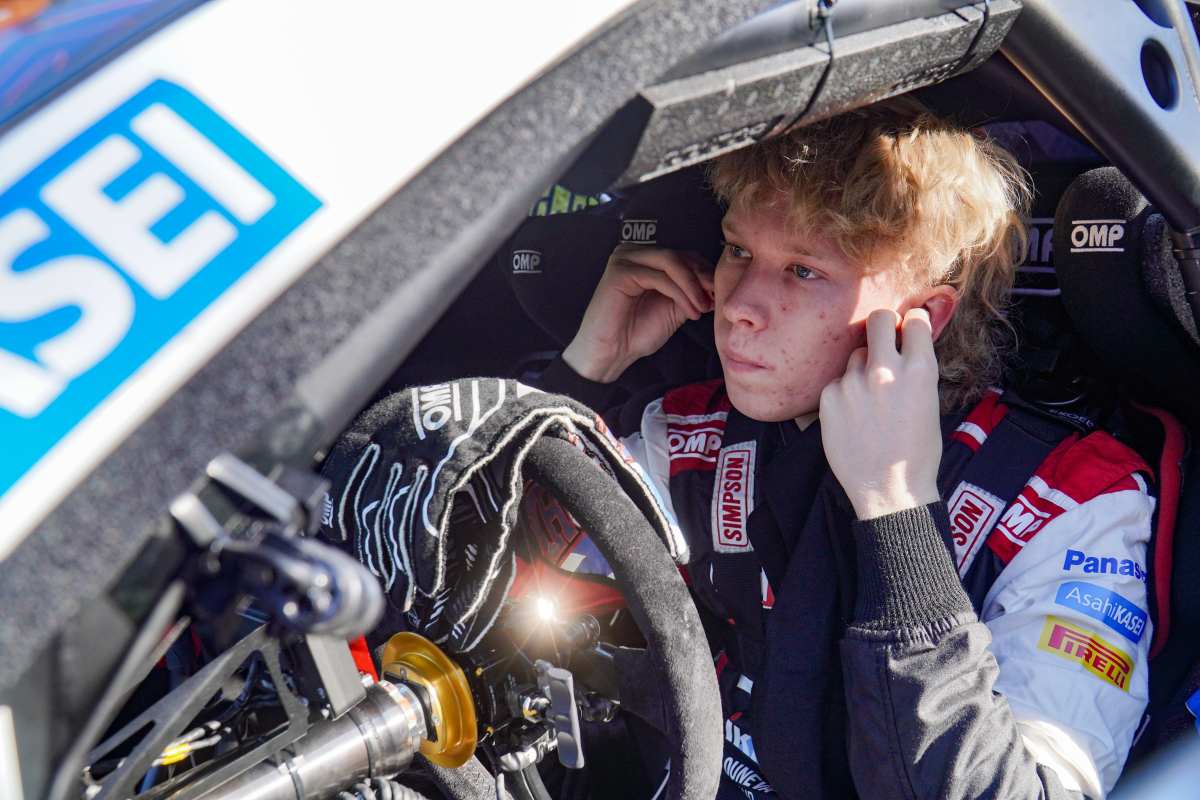タイヤ選択を誤った「魔の土曜日」を乗り越え
三年連続でマニュファクチャラーズタイトルを獲得
WRCな日々 DAY51 2023.10.13
4年ぶりにWRCを迎えたラリー・チリは、スムースな路面や適度な曲率のコーナーが続くこともあり、ドライバーが思いきり全開走行を愉しむことができるラリーになるだろうと考えられていた。しかし、実際はそれほど簡単には行かず、路面に合ったタイヤ選択と、そのマネージメントが勝敗に大きな影響を及ぼした一戦になった。
2019年にWRCとして初めて開催されたラリー・チリは、同じく南米を舞台とするラリー・アルゼンチンの2週間後に行なわれたこともあり、路面が非常にスムースで走りやすいラリーという印象を持った。アルゼンチンは岩や大きな石が転がる荒れた路面のグラベルステージも多く、それによってタイヤやサスペンションにダメージを負ったクルマも少なくなかったからだ。チリに向けて、各チームともダメージを負ったクルマの整備作業に追われ「アルゼンチンとチリの開催順序が逆だったら良かったのに」という、メカニックの嘆きも聞かれた。それくらい、アルゼンチンと比べるとチリのグラベル路面はスムースに感じられ、フィンランドやニュージーランドに近いキャラクターだと表現するドライバーが多かったと記憶している。
それから4年、久々にWRCに帰ってきたチリは、開催時期が前回の5月から9〜10月へと移るとともに、ステージの設定も大幅に変更された。太平洋をのぞむ風光明媚なステージが印象的だった土曜日以外は、ほぼ新ステージといえるほど大きく変わっていた。レッキで事前下見走行を終えたドライバーたちは、攻め甲斐のあるステージを称賛しながらも「曜日ごとに道のキャラクターが大きく異なる」と分析。特に金曜日のデイ1と、154kmという3日間で最長の距離を走る土曜日のデイ2の違いを指摘する声が多く聞かれた。
競技初日となった金曜日のデイ1は、ハイスピードなコーナーが多い一方で、道幅が狭いセクションも少なくなかった。さらに、道の表面はルースグラベルに覆われ、初日の出走順が1、2番手のカッレ・ロバンペラ、エルフィン・エバンスにとってはかなり不利な路面コンディションだったといえる。それでも、エバンスは午前中の3本のステージのうち2本でベストタイムを記録して首位に。ロバンペラもSS2で2番手タイムを刻み総合4位につけるなど、とても良いスタートを切った。
通常、同じステージを2回目に走行する際は、ルースグラベルが既に掃き飛ばされているため、タイヤのグリップ力が高まり出走順の不利は軽減される。ところが、金曜日午後の再走ステージに関しては午前中よりもさらにグリップが低くなったと感じたドライバーが少なくなかった。午前最速だったエバンスもそのひとりであり、思うようにタイムが伸びず総合3位で金曜日を終えた。同じくグリップ低下を訴えたドライバーたちの話しを総合すると、1回目の走行で確かに表層のルースグラベルは少なくなったが、その下から非常に硬い路面が露出し、タイヤが予想以上にグリップしなかったようだ。岩盤状の硬すぎる路面ではグラベルタイヤのトレッド面の凹凸が食い込みにくく、グリップを得にくくなることもある。断定はできないものの、それがグリップ低下の原因のひとつではないかと考えられる。
総合3位に順位を下げはしたものの、エバンスは首位オィット・タナック(Mスポーツ・フォード)と12.7秒差につけ、土曜日のデイ2で巻き返す余地は十分にあった。また、ロバンペラも38.7秒差ながら総合5位と、自力で表彰台を狙える位置につけていた。ところが、土曜日は彼らにとって大誤算の一日になってしまった。デイ2のステージの多くは、2019年大会でも使われたステージと重なっていた。そこで、改めて手許にあった4年前のデータおよびデイレポートを見返すと、路面は全体的にスムースながらタイヤの摩耗に関してはかなり厳しいステージが多かったと記されていた。2019年の金曜日は、早朝気温がかなり低く、午前中はステージ全体が深い霧に包まれとても幻想的な風景だったことを良く覚えている。そこで、当時TGR-WRTのドライバーだったタナックはライバルよりも1本多い2本のスペアタイヤを搭載し、軟らかめのタイヤ6本でステージに臨んだ。タナックはタイヤに優しいドライビングで知られるが、彼が2位以下のライバルに対するリードを大きく拡げて午前中を走りきった時、スペアも含む6本のタイヤはほぼライフを終えていた。
TGR-WRTとしても、もちろんその時のデータを確認していただろうし、見た目以上にタイヤに厳しい路面であることは認識していたはずだ。そして、初春の開催となった今年はさらに路面がアグレッシブ、つまりタイヤに対して攻撃的になっていたことを選手たちもレッキの時点で理解していた。普通に考えれば、タイヤの温度が上がっても摩耗に強いハードタイヤを選ぶのが無難な選択である。実際、ライバルチームの主要ドライバーたちは最低でも3本のハードタイヤを選び、アグレッシブな路面に備えていた。一方、TGR-WRTは3人のドライバー全員がソフトタイヤのみを選択。さらに、ロバンペラと勝田はスペアタイヤを1本しか搭載しないという、かなり攻めた戦略をとった。そのことからも、チームがソフトタイヤの使用に自信を持っていたことが伺える。
一般的には、タイヤサプライヤーから提供される情報をベースに、各チームのエンジニアが最適と考えるチョイスをドライバーに提案し、最終的にはドライバーが決定するというタイヤ選択プロセスを踏む。過去のステージのデータがあればもちろんそれを参考にするが、各ループのステージ合計走行距離、温度、路面コンディション、天気の変化、ドライバーのタイヤマネージメント能力など、数多くのデータを統合してタイヤを選ぶことになる。TGR-WRTは以前から科学的なデータ解析を積極的にタイヤ選択プロセスに取り入れてきたが、そこから導き出された答えはフルソフトが最適であるというもの。土曜日の午前中に関しては路面温度が低く、ルースグラベルも多いため総合的に見てハードよりもソフトの方がメリットが多く、摩耗に関しても最後まで持つに違いないとエンジニアは判断したのだ。ドライバーもまた、エンジニアの説明を聞いて納得し、ロバンペラと勝田はスペアタイヤ1本でも行けると考えたのである。
しかし、土曜日午前中の路面は、チームやドライバーの想像以上に「攻撃的」だった。オープニングステージのSS7ではロバンペラがベストタイムを、エバンスが3番手タイムを刻むなどソフトタイヤが上手く機能した。しかし、その時点でドライバーたちは既にタイヤ選択を見誤った可能性があることを認識していた。1本のステージを走っただけでも、タイヤの摩耗がかなり進んでいたからだ。そのため彼らは、続くSS8ではタイヤをセーブする走りに切り替えたが、それでも摩耗の急速な進行は抑えきれなかった。午前中最後のSS9を走りきったエバンスは後輪が2本ともトレッド面の剥離(デラミネーション)を起こしており、トップから56.2秒遅れの13番手タイムに。ロバンペラもリヤタイヤが完全にすり減った状態で走りきり、トップから46.7秒遅れの8番手タイム。さらに、勝田はデラミネーションが原因のパンクで1分27.8秒も遅れるなど、チームにとっては悪夢のステージになってしまった。
結果論になってしまうが、土曜日の午前中に関しては間違いなくハードタイヤが正解であり、ハードタイヤ4本、ソフトタイヤ2本で臨んだタナックがリードを大きく拡げる結果に。そしてタナックは、そのリードを最後まで守り抜きラリー・チリ二連覇を果たしたのだった。一方、TGR-WRTのエンジニアは自分たちのタイヤ選択が誤りであったことを素直に認めるが、少しでも条件が違っていたならば失敗ではなかった可能性もある。エバンスは、土曜日午前中最後のSS9でタイヤのデラミネーションに見舞われたが、その前の2本のステージは3、2番手タイムで走行し総合2位に順位を上げていたからだ。そして、問題のSS9にしても、中間地点まではベストタイムのタナックに迫る、2番手相当のタイムを刻んでいた。ステージの距離が1/3程度短かったならば、エバンスはデラミネーションで大きく遅れることなく総合2位となり、ソフトタイヤ6本の戦略は失敗ではなかった可能性もある。
チーム代表のヤリ-マティ・ラトバラは「チームは今シーズンここまで70回以上もタイヤを選んできたが、そのほとんどが成功だった。今日は上手く行かなかったが、このことから学ばなくてはならない」と、タイヤ選択のミスを振り返った。どのような優れたドライバーであっても、時々は失敗をおかすものだ。同様に、チームのエンジニアたちも、より良いタイムを出すためにリスクをとり、それが裏目に出ることもある。科学的な要素を取り入れたタイヤ選択プロセスは、データの量が増えれば増えるほど精度を増していく。そう考えれば、今回の失敗も将来に向けては有効なデータになるだろう。
土曜日午前中の遅れによりエバンスは勝機を失い、ロバンペラは表彰台から遠ざかった。それでも彼らは少しでも順位を上げ、できる限り多くのポイントを獲得するため最後まで全力の走りを続けた。そのことが最終日のポディウム争いの緊張感を高めることとなり、総合2位につけていたテーム・スニネン(ヒョンデ)のクラッシュ&リタイアにも繋がったといえる。いい走りを続けていただけにスニネンのリタイアは気の毒だったが、それによってエバンスは総合3位に、ロバンペラは総合4位に順位を上げた。さらに、ボーナスポイントがかかる最終のパワーステージでロバンペラがベストタイムで5ポイントを、エバンスが2番手タイムで4ポイントを追加加算したことにより、チームは2戦を残して三年連続となるマニュファクチャラーズタイトルを獲得。また、勝田も総合5位でフィニッシュし、チームの3台目としての役割をしっかりと果たしたのだった。
ラリー・チリでは優勝こそ逃したが、TGR-WRTはチャンピオンチームに相応しい戦いを続け、過去2シーズンよりも1戦早くタイトルを決めた。第11戦チリまでにロバンペラは3回、エバンスは2回、セバスチャン・オジエは3回優勝し、勝田も含めると4人で16回のポディウムフィニッシュを達成してきた。彼らドライバーとコ・ドライバーたちが素晴らしい仕事をしてきたことは改めて言うまでもないが、速く、信頼性の高いクルマを作りあげたエンジニアたちや、それをしっかりと整備してきたメカニックたちも称賛されるべきだろう。また、全力でステージを戦ってきた選手たちの胃袋を満たし、活力を与えてきたケータリングスタッフや、現場には行かなくともユバスキュラのオフィスでチーム運営全般に携わる人々など、裏方としてチームを支える人々の貢献も忘れてはならない。
2023年シーズンのマニュファクチャラーズタイトルを巡る戦いはチリで終了したが、残る2戦ではドライバーズタイトル争いがさらに激化することになる。タイトル獲得の権利を有するのは選手権リーダーのロバンペラと、彼を31ポイント差で追うエバンスのふたりのみ。彼らはもう、自分のことだけを考えて戦うことが許される。特に、少なくないポイント差を2戦で挽回しなくてはならないエバンスは、優勝だけにターゲットを絞りリスクを負った戦いを挑むことが予想される。タイトルがかかる終盤戦の舞台は、いずれもターマック。WRC初開催のセントラルヨーロッパ・ラリー、そして最終戦ラリージャパンでは、チームメイト同士によるし烈な戦いが、舗装路で繰り広げられることだろう。
古賀敬介の近況
2023年のWRCもいよいよ終盤戦。WRCだけでなくWEC、SUPER GT、そしてスーパーフォーミュラもタイトル争いの天王山を迎えます。そのため10月以降は取材が超過密スケジュールで、11月中旬のラリージャパンまでノンストップです。ここから先は体力勝負でもあるので、今年1月に買って以来まだ1メートルも走っていない(苦笑)自転車を引っ張り出し、体力増強に努めようと考えています。