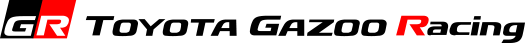あまりにもトリッキーなステージに驚愕
イープルで舗装ラリーの難しさを改めて知る
WRCな日々 DAY35 2022.9.9
昨年、WRCとして初開催されたイープル・ラリー・ベルギーを、今年初めて取材することができた。噂には聞いていたが、他のターマック・ラリーとは全く異なる、非常にユニークかつトリッキーなステージの数々に驚いた。頭に浮かんだキーワードはブレーキング、インカット、そしてマッド(泥)。この特殊なラリーを大きなミスをすることなく、全開で駆け抜けることができるWRCドライバーたちは本当に凄い! と改めて思った一戦だった。
イープルのステージは、その大部分が農場地帯の舗装路。ラリーが始まる前に全ステージをレンタカーで走って下見をしたが、舗装路面には農作業をするトラクターが畑の中から持ち込んだ土や砂利が多く出ていた。一部の路面は泥で完全に覆われ、法定速度内で普通に走っていてもタイヤが簡単にグリップを失い、挙動が乱れそうになるほど。おまけに道幅が非常に狭いため、路肩の未舗装部分に何度かタイヤを意図せず落としてしまい、その度に心拍数が高まった。
さらに、路肩の外側には幅も深さも1メートル以上あろうかという排水用の大きな溝が待ちかまえている。昨年の大会では、コントロールを失ったドライバーがこの溝にダイブし、クルマがはね上げられて横転する映像が多く見られた。そして今年も、カッレ・ロバンペラを始めとする何人かのドライバーたちが、この側溝に滑落して大クラッシュを喫した。道幅の狭さもさることながら、側溝の存在もこのラリーをデンジャラスなものにしている。また、側溝だけでなく、コンクリート製の見るからに頑丈そうな電柱も多くあり、それに当たってもクルマは大きなダメージを負ってしまう。コースを少しでも外れた瞬間、かなり高い確率で酷い目に遭う……。本当に恐ろしいラリーだと思った。
道幅が狭いステージは他のラリーでも多くあるが、イープルの場合は道が直線的で、スピードレンジがかなり高いのが特徴であり難しいところ。緩い高速コーナーの内側にはインカットできそうな未舗装エリアがあり、そこを通過するとさらに直線的にコーナリングラインを描くことができるため、タイムを削るためにはインカットがかなり有効であることは間違いない。ところが、コーナーによっては未舗装の路肩部分が30cm以上低くなっていて、かなり大きな段差になっている。そこに内輪を思いきり落としてインカットすると「ガスン」という鈍い音と共にクルマのフロアが舗装のエッジ部分に当たり、瞬間的にタイヤの接地が失われて挙動が乱れる。その度合いによってはステアリングが全く効かなくなることもあり、それが原因ではね飛ばされてクラッシュした選手も少なくなかった。
もっとも、カメラマンとしての立場から言うと、段差が大きいインカット可能なコーナーは最高の撮影スポットである。クルマが斜めに大きく傾き、まるでバンクを走っているかのような迫力あるシーンを撮影することができるからだ。そのため、コースの下見をする際は「このコーナーではどれくらいインに切り込み、クルマが傾くだろうか?」と、想像力を働かせながら各コーナーを観察していた。
インカットによって路肩の泥や砂利が舗装路面に掻き出され、出走順が後方になればなるほどダーティな路面を走らなくてはならなくなるのは、他のターマック・ラリーと同じ。ただし、イープルは道幅がかなり狭いので、泥を避けるためにコーナリングラインを大きく変えることはかなり難しい。ステージが終了した直後、僕もレンタカーでダーティになった路面を走ってみたが、ラインは一筋しかないように感じられ、狭いレールの上を走るしかない感覚だった。それでも、トップドライバーたちは僅かながらそのレールからタイヤを少しだけ外すなどして自分がベストだと思うラインを通過しているという。僕からすれば、ラインの選択肢はほぼゼロに思えるのだが……。全開でアタックしながらも、針の穴に糸を通すようなドライビングができるWRCドライバーの視神経、判断力、そして何よりも運転技術は一体どうなっているのだろうか?
TOYOTA GAZOO Racing WRT Next Generationの勝田貴元選手によると、コーナーごとにインカットをするかしないか判断し、する場合はどれくらいインにタイヤを落とすか、どのような角度でインに入るかを決めるのが非常に難しく、チームメイト同士でも常に情報交換をしているという。勝田選手が特に気をつけているのは、舗装路のエッジ部分がどのような状態になっているかで、ギザギザになっているコーナーはインカットによるパンクの危険性が高いため、かなり注意して走るそうだ。もちろん、全開でアタックしながら瞬間的にエッジの状態を見極めることは困難なため、レッキの時点でエッジのコンディションも細かくチェックしているという。また、ラリー本番でエッジを乗り越える際も、補強が比較的弱く切れやすいタイヤのサイドウォール部はなるべく接触させないようにして、トレッド面を当てて走るように気をつけているそうだ。
もうひとつ、このラリーで大きな鍵を握っているのはブレーキングだ。前述のようにイープルのステージは畑の中の直線的な道が多く、それをジャンクション=直角コーナーで結んでいるのが特長。コース図を見ると、まるであみだクジのようにギザギザしている。高速域からフルブレーキングで2速ギヤ程度のスピードまで一気にスピードを落とすコーナー、というかジャンクションが多くあり、フル減速、フル加速の繰り返し。泥が出ている路面でのフルブレーキングで、タイヤのグリップ限界を正しく見極めることは至難の業だ。しかも、イープルのステージは起伏が少なく、平坦なセクションが多い。二次元的で奥行きがつかみにくいため、ジャンクションまでの距離を正確に把握し、ブレーキングの開始ポイントを決定するのがとにかく難しいラリーだといえる。
サーキットであっても、例えば6速ギヤからフルブレーキングで2速までギヤを落とすようなタイトターンは難しく、オーバーシュートしやすいため、エスケープゾーンはかなり広く確保されている。ところが、公道が舞台のイープルでエスケープゾーンはネコの額ほどしかなく、しかもグリップレベルが異なる路面のジャンクションが次から次へと現れる。試しに、今大会最長だった全長22.32kmのステージで、直角かそれよりも鋭角な、フルブレーキングが必要なジャンクションがいくつあるのかを数えてみたら、何と40ヶ所近くもあった。その全てでギリギリのブレーキングを実践し、なおかつオーバーシュートしないように走り切るなんて不可能ではないかとも思うのだが、それをできてしまうWRCドライバーたちはやっぱり天才的な感覚を持っているのだろう。
以前、ヤリ-マティ・ラトバラTGR WRTチーム代表に、ブレーキングテクニックに関する取材をした時、彼は「ブレーキングのセンスが飛び抜けているドライバーだけが、ワールドチャンピオンになることができる。僕が同時代を過ごしたセバスチャン・ローブ、そしてセバスチャン・オジエはどちらもブレーキングの感覚が非常に優れていた。ロックするかしないかギリギリのところでブレーキの踏力を微妙に調整する能力が、彼らはずば抜けていたんだ。自分はどうしてもドカンと強くブレーキを踏む傾向があり、一時はセバスチャンたちのようなブレーキングに変えようと努力した。しかし、それによって全体的なドライビングのリズムが崩れてしまい、逆に速さを失ってしまった。ある程度キャリアを重ねてからブレーキングのスタイルを変えるのは本当に難しく、リスクを伴うことなんだ」と説明してくれた。
今年のイープルではオィット・タナックが優勝したが、彼もまた繊細なブレーキングに定評があり、トヨタ時代にはワールドチャンピオンに輝いている。彼を含め、少なくともここ20年くらいはブレーキングが特に繊細なドライバーが世界王者になっている。各ドライバーのブレーキングスタイルを観察する上でも、今回のイープルの取材は非常に意味があるものだった。ひとつ残念だったのは、ロバンペラのブレーキングを観察する機会があまりなかったこと。フルブレーキングしながらも微妙にアクセルを踏み込んでクルマの姿勢を安定させるという、彼が得意とするブレーキングテクニックを、次回のターマック・ラリー取材ではじっくりと観察したいと思う。
古賀敬介の近況
イープル・ラリー・ベルギーの取材で驚いたのは、畑の中が指定観戦エリアやメディア撮影ポイントになっていたこと。普通、畑の中に足を踏み入れることなど許されないと思いますが、農場主さんは「どうぞ、どうぞ」とウエルカム。とはいえ、できるだけ農作物を傷つけないように気をつけて撮影しましたが。もちろん、休業保証制度などはあるとは思いますが、このラリーに対する地元の人々の理解の深さを感じた次第です。