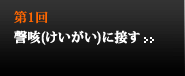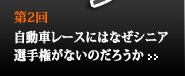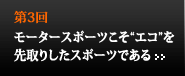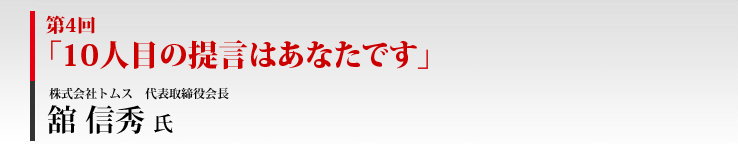![]()
トムス創業以来、37年間を振り返ると実に多くのドライバーと接してきたものだと感慨に絶えない。多くの若者が育ち、そして多くのことを我々に教え、多くの技術をもたらしてくれた。
印象的なドライバーを上げろと言われたら、トムスに関わったドライバーすべてが印象的であり、一人を特定することは難しい。それぞれのドライバーに深い思い出がある。
創業期の鈴木恵一や星野薫は言うに及ばず、小河等や関谷正徳、そして今日の脇阪寿一やアンドレ・ロッテラーに至るまで枚挙にいとまがない。
鈴木亜久里は19歳の時、西多摩郡瑞穂町にあった当時のトムス本社で、販売をしていた部品を全国のチューニングショップに送るための荷造り梱包のアルバイトをしながら、F3レースに参戦していた。そして、彼は見事にF1まで上り詰めて行き、今もチームオーナーとして活躍している。
トムスでアルバイトをしながらレースを続けたのは亜久里ばかりではない。関谷正徳もその一人であったし、黒澤琢弥もアルバイトをしながらレースを続けた。琢弥の場合は強烈だった。あのような強持ての顔ながら、彼は会社に誰よりも早く出社してきて、そして、会社の窓をとにかく綺麗に拭いてからトイレを掃除して、仕事に入るということを長年続けていた。あれは印象的だった。
小河等は、1987年にCカー(全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権)の鈴鹿1,000kmレースで第3ドライバーとして起用して優勝することができた。物静かな語り口ではあるが常に冷静沈着で、エンジニアに対するコメントの的確さと、マシンとタイヤをいたわる走りはチームスタッフ全員を魅了した。遅咲きではあったが、着実に成長していくドライバーとしてトムスのエース格となり、1992年にスポーツカー世界選手権(SWC)に挑み開幕戦のモンツァ1,000kmで見事に優勝を成し遂げた。生活の拠点はイギリスにあったものの、SWCの合間を見てスポット参戦すべく来日して出場した全日本F3000選手権鈴鹿大会で彼は亡き人となった。享年36歳という若さであった。トムスはゼッケンナンバーを1984年から『36』を冠してレースには出ていたが、それほどのこだわりがあったわけではなかった。しかし、この小河の死によって『36』にこだわることにした。36号車に乗り世界選手権で優勝し、36歳で亡くなった小河の番号として今からもこだわっていくつもりでいる。
F3でも実に多くの若い外国人ドライバーと接することができ、今でも育った彼らと交友が続いている。
1992年、リカルド・リデルはトムスにマカオGPのF3で初めて勝利をもたらしてくれた。その年、ジャック・ビルヌーヴがトムスからエントリーして全日本選手権でシリーズ2位に輝いた。とにかくやんちゃな若者だった。世田谷の本社に来る時は電車で来て、尾山台の駅からローラーブレードを履いて颯爽と会社に来る。
翌年の1993年はトム・クリステンセンである。マカオGPの翌週に富士スピードウェイで開催されていたインターF3チャレンジで、ミハエル・シューマッハと熾烈なバトルを展開した記憶が今でも鮮明に思い浮かべることができる。
1994年のミハエル・クルムは、1990年から本格参入したトムス独自製作のF3マシンを完成域まで高めてくれた。
1995年は、今年からF1レースに復帰したペドロ・デ・ラ・ロサ(BMWザウバー)である。彼は真面目というか、律儀な男で、日本で自分のレース人生が開花したと言っては連絡をくれる。
1996年と1997年は、今でも世界ツーリングカー選手権(WTCC)で活躍しているトム・コロネルが、1998年にはピーター・ダンブレックがトムスからエントリーし、マカオGPでトムスに2勝目をもたらしてくれた。その翌年(1999年)、ダレン・マニングはマカオGP全セッショントップで優勝し、 トムスに2連覇をもたらすばかりか、翌週に行われたコリアGPでも全セッショントップで特別ボーナスを手中に収めた。
2000年以降もジェームス・コートニー(2003年)、ジョワオ・パオロ・デ・オリベイラ(2005年)、エイドリアン・スーティル(2006年)、オリバー・ジャービス(2007年)、カルロ・バンダム(2008年)、マーカス・エリクソン(2009年)と続いた。
彼らは今でもレースの世界で活躍していてくれる。恐らく、トムスと関わらなくても彼らは立派にレース界で活躍できたであろう。しかし、運命というか、偶然性というか、これら多くのドライバーと係わり合いを持つことができた自分を幸せ者と思う。
海外のレースに行くと今でも感動するのが、サーキットのゲートを出る時、まだ10代と思われる男の子が近寄ってきてプロポーザル(提案書)を渡してくる。「トムスの舘」であることを知って近寄っているとは思えない。それが証拠に、日本人と見るや誰彼構わずプロポーザルを渡す。そのプロポーザルの内容はレーシングドライバーとしてこれからも活躍するからスポンサーしてくれ、という内容である。ハングリーさと直向(ひたむき)さを垣間見ることができる。
日本でも1990年代後半までは、「ドライバーになりたいんで是非トムスに入社させてください」とか、「ドライバーになるにはどうすればいいんですか」、「メカニックになりたいんですが入社させてください」という手紙や電話で相談されることが年間50件は下らなかった。
しかし、日本において最近はこのような相談が皆無になってしまった。このような現象にいささか危機感を抱いている。その背景には、恐らくレーシングドライバーやレースに関わる職業が魅力ある職業、稼げる職業ではなくなったことを物語っているような気がしてならない。
あの海外での若い子達が目を輝かせてスポンサーを募る光景に出会うたびに、このような姿勢こそ“速い”ドライバーを育んでいく土壌になっているのではないかと思う。
そして、これまで多くの外国人ドライバーと接して来て彼らに共通していることは、とにかくレースを楽しむために努力を惜しまないし、全てにわたって楽観的に物事をとらえる習性を身につけているということである。これは民族性や国民性ばかりでは片付けられないような気がする。
これからもレースにおいて多くの良い思い出を残していきたいと願っている。小生ばかりではなく、そう願っている関係者は多いはずである。
しかし、レース界もご多分に漏れず関係者の高齢化が目立ち、技術者も、ジャーナリストも若い人が育っていないように感じる。危機的な状態にある。だからこそ今を憂い、これから良くしていきたいと願い、自動車メーカーや、レースにおける立場の枠を超えてこの「クルマとモータースポーツの明日 9人の提言」というコラムに小生も含めて9人もの方々にご寄稿いただいた。
でも9人の提言だけではまだまだ声としては小さ過ぎると思う。「クルマとモータースポーツの明日」を良くして行くために、このコラムを読んでいただいている皆さんにも「10人目」、「11人目」の提言者としてご提言をいただきたいと願って止まない。モータースポーツをメジャーなスポーツとして確立するためにも。
【編集部より】
本コラムについてのみなさまからの声をお聞かせください。
“ジミーブログ”にてみなさまのご意見、ご感想をコメント欄にご自由に書き込みください。
また、今まで寄せられたご意見もご覧ください!


- 1965年、大学在学中にトヨタ・パブリカ700を駆ってレースデビュー。
1971年にトヨタ・ファクトリードライバーとしてトヨタと専属契約。
その後、1974年に株式会社トムスを設立し代表取締役社長に就任。
1982年、レーサーとしての現役を引退した後はチーム・オーナーに専念。
全日本F3選手権や全日本GT選手権など数々のタイトルを獲得し、1998年に㈱トムスの代表取締役会長に就任する。
現在はチームオーナーとして各参戦カテゴリー(スーパーGT、フォーミュラ・ニッポン、全日本F3選手権)の陣頭指揮を執る傍ら、(社)日本自動車連盟モータースポーツ評議会評議委員等、日本のモータースポーツの発展・振興に努めている。